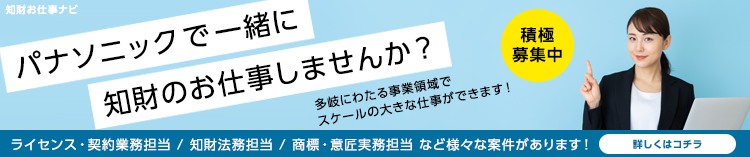この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成17ワ14972不正競争行為差止等請求事件 平成17ワ22496損害賠償等請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
| 関連ワード | 周知性 / 広く認識 / 商標登録 / 登録商標 / 混同行為 / 商品等表示 / 類似性(類似) / 観念 / 混同のおそれ(混同) / 表示の使用 / 先使用 / 不正の目的(不正競争の目的) / 差止請求(差止) / 不当利得 / ただ乗り(フリーライド) / 代理人 / 代表者 / 混同のおそれ(混同) / 品質等誤認表示(誤認) / 虚偽の事実 / 損害賠償 / 損害額 / 営業上の信用 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
7年
(ネ)
297号
表示使用差止等,同,家屋明渡等,売掛代金等請求各控訴事件
平成 7年 (ネ) 302号 表示使用差止等,同,家屋明渡等,売掛代金等請求各控訴事件 平成 7年 (ネ) 298号 表示使用差止等,同,家屋明渡等,売掛代金等請求各控訴事件 平成 7年 (ネ) 303号 表示使用差止等,同,家屋明渡等,売掛代金等請求各控訴事件 平成 7年 (ネ) 299号 表示使用差止等,同,家屋明渡等,売掛代金等請求各控訴事件 |
|---|---|
|
A①事件・B①事件・C事件控訴人 A②事件・B②事件被控訴人 (以下「一審原告」という。) 株式会社 丸優右訴訟代理人弁護士 村林隆一 同 山田一夫 同 平山 茂 A①事件・B①事件被控訴人 A②事件・B②事件控訴人 (以下「一審被告三田屋本店」という。) 株式会社 三田屋本店(旧商号 株式会社三田屋) A①事件被控訴人、A②事件控訴人(亡c訴訟承継人)(以下 「一 審被告b」という。) b 同(以下「一審被告d」という。) d 同(以下「一審被告e」という。) e 同(以下「一審被告f」という。) f 同(以下「一審被告g」という。) g右両名法定代理人母 b右六名訴訟代理人弁護士 藤巻一雄 同 横 清貴 同 崔勝 同 畠田健治 右横清貴訴訟復代理人弁護士 北川 豊 A①事件・C事件被控訴人 (以下「一審被告h」という。) h右訴訟代理人弁護士 阿部幸孝 |
|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2001/06/28 |
| 権利種別 | 不正競争 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一(A事件について)1 一審被告hを除く一審被告らの控訴(A②事件)に基づき、A事件原判決主文一項のうち、一審被告hを除く一審被告らに関する部分を取り消す。 一審原告の請求のうち、右取消しにかかる部分を棄却する。 2 A事件に関する一審被告三田屋本店のその余の控訴を棄却する。 3 A事件に関する一審原告の控訴を棄却する。 二(B事件について)1 B事件について、一審原告の控訴に基づき、原判決主文二項を次のとおり変更する。 一審被告三田屋本店は、一審原告に対し、金一八八八万四一四八円及び内金一四〇五万九五九〇円に対する平成五年五月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 2 B事件に関する一審原告のその余の控訴を棄却する。 3 B事件に関する一審被告三田屋本店の控訴を棄却する。 三(C事件について)C事件に関する一審原告の控訴を棄却する。 四(訴訟費用について)1 一審原告と一審被告三田屋本店との関係では、第一、二審及び本訴、反訴を通じて、一審原告に生じた費用(ただし、一審被告hとの間に生じた費用を除く。)の八分の七と一審被告三田屋本店に生じた費用の全部とを二分し、その一を一審原告の、その余を一審被告三田屋本店の負担とする。 2 一審原告と一審被告b、同d、同e、同f、同gとの関係では、第一、二審を通じて、一審原告に生じた費用(ただし、一審被告hとの間に生じた費用を除く。)の八分の一と右被告らに生じた費用の全部を一審原告の負担とする。 3 一審原告と一審被告hとの関係では、一審原告に生じた控訴費用の八分の二と一審被告hに生じた控訴費用は、一審原告の負担とする。 五(仮執行宣言)この判決は、主文二1につき、仮に執行することができる。 (以下、一審原告を「原告」、一審被告を「被告」という。)A、B、C事件に共通の前提事実(証拠を引用しない事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により認めることができる。)1 原告は、H家の長男i(代表取締役)、二男j(専務取締役)、三男a(常務取締役)によって昭和四一年三月一日に設立された。設立当時の商号は「株式会社丸優食品」、事業目的は「畜産物の生産及び販売等」であり、本店所在地は兵庫県三田市以下略であった。 右の当時学生であった四男c及び五男被告hも、昭和四四年までに原告の経営に加わった。 その後、原告の商号は「株式会社丸優」と変更され、本店所在地の表示も、住居表示の変更により「兵庫県三田市以下略」と変更された。 2 三田市内のはざま池に面するi所有土地(三田市以下略山林一三八八平方メートル。以下「本件土地」という。)上に原告の名義でレストラン用の建物(以下「本件建物」という。)が建築され、昭和五二年七月末から「三田屋」の表示(屋号)でステーキレストランの営業が開始された。 3 cは、昭和五四年九月四日、被告三田屋本店(当時の商号「株式会社三田屋」。以下「被告会社」という。)を設立して代表取締役に就任し、被告会社が右レストランの経営を行うようになった。 被告会社の事業目的は「飲食店、喫茶店及びレストランの経営、畜産加工食品の製造及び販売等」であり、本店所在地は、本件建物の所在地である兵庫県三田市以下略(後に兵庫県三田市以下略)である。 4 昭和五四年一一月一四日にiが死亡したことに伴い(母kも同月死亡)、 iの妻であるlが原告の代表取締役に就任し、aが専務に就任した(同人は、後に原告の代表取締役に就任した。)。 そのころから、原告(l、a)と被告会社(c)との対立が顕著になった。 5 被告hは、昭和五六年六月、兵庫県西宮市以下略の国道一七六号線沿いにおいて「山口三田屋」の屋号でレストランを開業し、同五七年六月ころ、原告を辞めて独立した(乙九六)。 6 被告会社は、本件建物においてレストラン営業を続けながら、直営店のほかフランチャイズ店を全国に多数有するようになったが、昭和六二年四月、本件建物から約二キロメートル離れた土地に、新店舗を建築し、ここにレストラン営業の本拠を移転した。 その後、本件建物は、被告会社の動産類が置かれているほか、特に利用されずに放置されている。 7 cは、本件訴訟が原審に係属中の昭和六二年八月一三日死亡し、妻である被告b、先妻との間の子である被告d、同e、bとの間の子である被告f、同gがcの地位を承継した。なお、被告会社の代表取締役には被告bが就任した。 8 被告会社は、レストラン経営の傍ら、「三田屋の手造りハム」の表示でハムの製造、販売を行っていたが、現在は、「三田屋本店 やすらぎの郷」の表示でハム等を製造、販売している。 一方、原告も、「三田屋の手造りハム」の表示でハムの製造、販売を行っていたが、昭和六二年以降は、「はざま湖畔・三田屋・総本家」の表示でハム等を製造、販売している。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 原 告 1 原判決主文一、二項を次のとおり変更する。 (一) 被告会社は、原告に対し、原判決別紙(一)被告会社標章(1)の標章(以下「被告会社標章」という。)をハム、ソーセージ、チーズ、ハム用ドレッシングの包装に付したハム、ソーセージ、チーズ、ハム用ドレッシングを譲渡し、引き渡し、譲渡又は引渡しのため展示してはならない。 (二) 被告会社は、前項標章(1)を前項の包装、チラシ、カタログに付し、同包装等を頒布してはならない。 (三) 被告会社は、株式会社「三田屋本店」なる商号を使用してはならない。 (四) 被告会社は、神戸地方法務局三田出張所においてなした商号「株式会社三田屋本店」の商号抹消登録手続をせよ。 (五) 被告会社は、その店舗、広告塔における原判決別紙(二)被告会社表示(2)、(3)、(4)、(5)の各表示(以下「被告会社表示」という。)を抹消せよ。 (六) 被告らは、自己又は第三者をして、原告の取引先に対し、原告の製造、販売にかかるハムが偽物である等と虚偽の事実を陳述し又は流布して、原告の営業上の信用を妨害してはならない。 (七) 被告会社及び被告hは、原告に対し、各自金一五〇〇万円及びこれに対する昭和五七年二月二六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 (八) 原告に対し、被告bは金七五〇万円、一審被告d、同e、同f及び同gは、各自金一八七万五〇〇〇円並びにこれに対する昭和五七年二月二六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 2 被告ら(被告hを除く。)の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被告らの負担とする。 4 1(一)ないし(三)、(五)ないし(八)につき仮執行宣言 二 被告会社 1 原判決中、被告会社敗訴部分を取り消す。 2 同被告に対する原告の請求を棄却する。 3 原告は、「三田屋総本家」の表示を使用し、又は、第三者をして使用させてはならない。 4 原告は、ハム、ソーセージ等の肉製品の包装及びドレッシングの容器並びにこれらの広告に、「三田屋総本家」「はざま湖畔・三田屋・総本家」の表示(以下、これらを「原告表示」という。)を使用してはならない。 5 原告は、被告会社に対し、金三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五七年一〇月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 6 被告会社に対する原告の控訴を棄却する。 7 訴訟費用は、第一、二審とも原告の負担とする。 8 5につき仮執行宣言 三 被告b、同d、同e、同f、同g (以下、この五名を総称する場合は、「被告c相続人」という。) 1 原判決中、被告c相続人の敗訴部分を取り消す。 2 同被告に対する原告の請求をいずれも棄却する。 3 同被告に対する原告の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は、第一、二審とも原告の負担とする。 四 被告h 1 被告hに対する原告の控訴を棄却する。 2 控訴費用は、原告の負担とする。 |
|
|
事案の概要
一 請求及び原審の判断 1 原告の本訴 (一) 被告会社に対する請求 原告は、「三田屋」は原告の周知表示であり、被告会社標章及び被告会社表示が原告の右周知表示と誤認、混同のおそれがあるとして、不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号、3条1項に基づき、右の標章及び表示の使用の差止めを求めた。 (二) 被告会社、c相続人及び被告hに対する請求 原告は、被告会社、c及びc相続人並びに被告hが原告の信用を毀損する行為をしているとして、法2条1項13号、法3条1項、4条に基づき、右行為の差止めと、過去の信用毀損行為に基づく損害賠償として、一五〇〇万円(c相続人に対しては、法定相続分により分割)及びこれに対する訴状送達の日(昭和五七年二月二六日)から完済まで年六分の割合による金員の支払を求めた。 2 被告会社の反訴 被告会社は、「三田屋」は被告会社の周知表示であり、原告の「三田屋」の表示は被告会社の右周知表示と誤認、混同のおそれがあるとして、法2条1項1号、3条1項、4条に基づき、① 右の原告表示の使用の差止めと、② 慰謝料及び名称使用料相当損害金として、九五七五万九七〇五円の内金三〇〇〇万円及びこれに対する反訴状の送達の翌日(昭和五七年一〇月一四日)から完済まで年五分の割合に基づく遅延損害金の支払を求めた。 3 原審は、「三田屋」の表示の周知性について、原告の主張を認めず、被告会社の主張を認めたが、原告の表示の先使用を認め、1(一)及び2①、②の各請求を棄却した。 そして、1(二)の請求については、信用毀損行為の差止め請求のみを認容し、損害賠償請求は棄却した。 4 これに対し、原告及びhを除く被告らが控訴を提起し、前記第一のとおりの裁判を求めた。 なお、被告会社は、当審で前記2①の訴えを変更し、差止めの対象となる表示を「三田屋」から「はざま湖畔・三田屋・総本家」等に改めた。 二 争 点 1 「三田屋」の表示の周知性 「三田屋」の表示は原告の表示として周知性を取得しているか、取得しているとしてその取得時期。また、被告会社表示(「三田屋」及び三田屋本店」)は被告会社の表示として周知性を取得しているか、取得しているとしてその取得時期 2 被告会社表示の周知性取得が先行しているとして、原告表示の先使用の成否、及び原告における不正目的の有無 3 被告らの法2条1項13号の不正競争行為(信用毀損行為)の存否 4 損 害 5 なお、法2条1項1号の不正競争行為(商品等主体混同行為)の存否については、原告及び被告らは、双方とも、相手方の商品等表示が主体混同を惹起すると主張しており、原告表示及び被告会社表示が類似している結果、混同のおそれがあることについて、当事者間に争いがない。 三 争点に関する当事者の主張 1 争点1について 【原告の主張】 (一) 原告は、遅くとも、昭和五二年八月以降、その製造にかかるハムを、 「三田屋」の表示を使用して販売していた。 右表示は、原告の製造、販売にかかるハム等の商品表示として、昭和五二年末には消費者の間で周知となっていた。 なお、原告は、昭和五一年秋から、松茸昆布やしぐれ煮の製造を始め、 これらを「三田屋」の表示を使用して販売するようになり、原告名義で商標登録出願も行っている。 (二) ハムの製造に伴う食品衛生法上の許可等は、当初、全て原告名義で行っていた。cは、原告の食品衛生法上の食品衛生管理者の立場でハムの製造に関与していたにすぎないものである。 (三) なお、本件レストランは、原告が、原告代表者であるi名義の本件土地上に本件建物を建設し、原告名義で飲食店営業許可を取得し、原告が経営していた。 (四) 被告会社がハムの製造を始めたのは昭和五六年九月初めからであり(しかも、それは保健所の許可を得ておらず、許可を得て製造を始めたのは、昭和六一年からである。)、それ以前に被告会社表示が周知性を取得することはあり得ない。 【被告らの主張】 (一) cは、昭和五二年七月末から本件建物でレストラン経営と手造りハムの製造、販売をしてきた。 cは、自らの製造した手造りハムを「三田屋の手造りハム」として販売したが、 右ハムはcの創意工夫により独特の風味をもって人気が上昇し、昭和五四年ころには周知性を取得した。 仮に、右時点において、周知性を取得していないとしても、cのテレビ出演その他テレビ、ラジオ、新聞雑誌等の宣伝とも相まって「三田屋の手造りハム」という表示は、さらに消費者の間に広く知られ、遅くとも、昭和五六年ころまでには、周知性を取得した。 (二) 仮に、レストランの経営が、当初原告の経営であったとしても、遅くとも昭和五三年三月以降はcが経営し、同レストランの営業表示として「三田屋」を使用してきた。 cは、昭和五四年九月、右レストランの個人経営を法人組織に改めて被告会社を設立し、自ら代表取締役に就任したが、被告会社は、引き続き被告会社表示を使用して、レストラン営業及びハムの製造、販売をしている。 (三) 原告が自らハムを製造し始めたのは、昭和五六年一〇月以降であり、 それ以前に、原告が「三田屋」の表示を使用してハムを製造、販売したことはなく、その表示が周知性を取得することもあり得ない。 原告は、当時、大手ハムメーカーと取引があり、原告が主体となって競業行為であるハムの製造、販売をすることは不可能であったため、ハムの製造、販売を原告から独立させ、cがその経営を行うようになったものである。 原告は、cの造る手造りハムが有名になってくると、原告の方でも販売させてほしいと言ってきたので、c及び被告会社は、採算を無視して、これを販売させてきた。 しかるに、原告は、代表者のiが死亡し、aが実権を握ると、昭和五六年一〇月ころから、自らハムを製造し始め、これを「三田屋の手造りハム」として販売し始めた。 2 争点2(原告表示の先使用)について 【原告の主張】 (一) 仮に、被告会社表示の周知性取得が先行しているとしても、原告は、 昭和五一年秋ころから「三田屋」の表示を使用して、松茸昆布やしぐれ煮の製造、 販売を行っており、また、それ以前から、右表示を使用してハムの製造、販売を行っており、昭和五二年七月末からは、右表示を使用して本件建物においてレストランの営業を行っている。 したがって、原告は、「三田屋」の表示を先使用しており、被告会社の請求は理由がない。 (二) また、現在の原告表示である「三田屋総本家」「はざま湖畔・三田屋・総本家」は、右「三田屋」の表示(以下「原告旧表示」ともいう。)と同一性を有し、かつ、被告会社の表示により似せるべく変更されたものではない。したがって、原告旧表示について先使用が認められる限り、現在の原告表示についても、 先使用の抗弁が認められる。 (三) 不正目的がないこと 被告会社の経営するレストランは、開店当初は、原告が経営していたにもかかわらず、cがこれを乗っ取ったものであるが、それまでは、原告が「三田屋」の営業表示を使用して経営していた。 また、前記のとおり、原告は、遅くとも昭和五二年八月以降、その製造にかかるハムを、「三田屋」の表示を使用して販売していた。 原告は、これまで継続して使用してきた原告旧表示の延長として、現在の原告表示を使用しているにすぎず、そこに不正目的はない。 【被告会社の主張】 (一) 仮に、被告会社の「三田屋」の表示が周知性を取得する以前から原告が「三田屋」の表示を使用していたとしても、原告の現在の商品表示である「はざま湖畔・三田屋・総本家」は、原告旧表示の「三田屋」の表示と同一とはいえず、 しかも、原告が現在の表示の使用を開始したのが昭和六二年以降であって、被告会社の「三田屋本店」の表示が周知性を取得した後であることは明らかであるから、 原告の先使用の抗弁は理由がない。 (二) 原告の不正競争目的 仮に、現在の原告表示である「はざま湖畔・三田屋・総本家」と旧表示である「三田屋」の表示に同一性があり、形式的に先使用が成立するとしても、次の事情に照らすと、原告の使用には不正競争目的があり、先使用の抗弁を主張することはできないというべきである。 すなわち、原告は、被告会社経営のレストランがテレビ等で有名になると、その名声にフリーライドする目的で、昭和五六年九月、スモークハウスを購入して、ハムの製造、販売を始め、更に、昭和五六年一二月一〇日には、子会社として「株式会社丸優三田屋」を設立し、ハムの販売を行うようになった。 なお、被告会社は、右子会社との混同を避けるため、昭和五八年八月八日、被告会社の商号を「株式会社三田屋」から現在の「株式会社三田屋本店」に改めたところ、原告は、昭和五九年一一月二六日、右子会社の商号を「はざま湖畔三田屋本店株式会社」と改め、さらに、昭和六三年二月二〇日「株式会社はざま湖畔三田屋総本家」と改めた。 原告が、子会社の商号に「はざま湖畔」を付加したのは、被告会社のレストランの広告宣伝に湖畔のレストランのイメージがあるのを後追いしたものである。 先使用が認められるためには、不正競争目的のないことが要件であるところ、右のとおり、原告には、不正競争目的の意図が存するのは明白であり、先使用の抗弁の主張は許されない。 3 争点3(被告らの信用毀損行為の存否)について 【原告の主張】 (一) cと被告hは、昭和五六年一一月中旬ころから、原告の得意先に対し「原告の商品は、被告会社の商品の類似品であり、偽物である」旨、虚偽の事実を直接又は電話で触れ回り、原告の営業上の信用を害した。 また、右の二人は、大阪高島屋に直接乗り込み「原告の商品は偽物である。原告と取引を続けるなら、高島屋が偽物を売っていると世間に訴える」等と脅したり、 原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を陳述し、その後もこれを繰り返した。 (二) 被告会社は、二度にわたり、新聞折り込み広告を三田市及びその周辺に各戸配布し、また、原告の最大手の取引先である高島屋各店に文書を送付し、虚偽の事実を流布した。 【被告らの主張】 (一) 昭和五六年一一月ころ、客の苦情から、原告がその作成にかかるハムを「三田屋の手造りハム」として大阪高島屋等に販売している事実が判明し、cは高島屋の担当者と会い、協議の結果、高島屋は、原告の作成したハムを「丸優のハム」として販売し、被告会社の作成した「三田屋の手造りハム」として販売しないことを確約した。 しかるに、その後も、客の苦情が絶えなかったことから、高島屋が原告の作成したハムをその後も「三田屋の手造りハム」として販売していることが分かり、cはやむなく抗議の手紙を高島屋へ出したのである。 (二) 被告会社は、昭和五〇年代後半ころから大丸株式会社(以下「大丸」という。)神戸店に小売価格の七〇パーセントで手造りハム等を納品していたが、 原告が、昭和五九年一一月二九日、大丸の担当者に対し、被告会社が保健所の製造許可を取得しておらず、「三田屋」の名称を不正に使用しているなどと申し向けたり、昭和六〇年五月一六、一七日、大丸の店内で、被告を誹謗中傷する文書を配布するなどの営業妨害の結果、大丸及びその顧客に混乱と迷惑を及ぼしたことに対するペナルティーとして、昭和六三年四月以降の納品の価格を小売価格の六五パーセントに低減させられた。 (三) また、被告会社は、昭和六〇年ころから西武百貨店株式会社(以下「西武百貨店」という。)の高槻店、つかしん店との、昭和六三年から同宝塚店との取引をしており、平成二年度の取引高は年間一二七四万円であった。 ところが、平成元年になって、原告は、「三田屋」の名称を違法に使用して、西武百貨店にハム等を納品するようになった。そして、販売の際には「三田屋のレストランで出しているのと同じハムである」と偽っていた。 被告会社は、この対応に苦慮したが、原告と正面から争うと大丸神戸店のときと同様の混乱が生じて被告会社の信用を失墜するのを恐れ、平成三年以降西武百貨店のこれらの店舗への納品を中止することに決定した。しかし、西武百貨店の求めにより、中元と歳暮の時期の納品は続けることとした。 4 争点4(損害)について 【原告の主張】 原告は、歳末の贈答用品として大量の買付けが見込まれた時期に、被告らから前記3のような不法行為を受け、その売上が当初の予想をはるかに下回ったばかりか、昭和五七年一月三一日限りで、大阪高島屋から原告との出店契約を解除された。 これらの損害は、少なく見積もっても金三〇〇〇万円を下らない。 【被告会社の主張】 被告会社の製造したハムと原告の製造したハムとは、風味が全く異なるため、被告会社の美味なハムと信じて原告の製造、販売したハムを買った多くの顧客の苦情が被告会社のもとに殺到し、現在に至っている。 原告は、被告会社の再三の抗議を無視し、現在もその製造にかかるハムの包装、 広告、販売に「三田屋」なる表示を使用し続けており、これに起因する被告会社の損害は次のとおり合計金九五七五万九七〇五円になるが、被告会社は原告に対しそのうち金三〇〇〇万円の支払を求める。 (一) 昭和五六年から現在に至るまでの被告会社の信用・名誉の棄損に対する慰籍料は、金一〇〇〇万円が相当である。 (二) 被告会社が原告に対し「三田屋」の名称の使用を許諾するとすれば、 その名称使用料は一か月金五〇万円を下らない。 そうしてみると、(原告が「三田屋」の名称を使用し始めた)昭和五六年一〇月ころから平成四年一〇月までの間の名称使用料は金六六〇〇万円を下らない。 (三) 前記3【被告らの主張】(二)の結果、被告会社は、平成元年から平成四年一一月末日までの間に金一三四五万九七〇五円の損害を被った。 (四) 前記3【被告らの主張】(三)の結果、平成三年度の売上は金六四四万円まで減少した。その損害額は金六三〇万円となる。 |
|
|
当裁判所の判断
一 争点1(原告表示及び被告表示の周知性)について 1 本件レストランの経営を巡る原告と被告会社との関係 (一) 前提事実に、証拠(a、cの原審供述のほか、後掲各証拠)及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。 (1) 原告設立後の営業内容 原告は、昭和四一年三月の設立後、大手ハムメーカーの肉加工の下請をするようになり、昭和四三年には、佐賀県内の大手ハムメーカーの工場内に九州工場を設け、cが工場長として赴任した。また、原告は、大手ハムメーカーの有する店舗を借りて、精肉の販売などの営業も行っていたが、昭和四六年には、JR三田駅前に五階建ての自社ビル(丸優ビル)を建設し、一階を精肉店とした。 九州工場では、オイルショックなどの影響により取扱量が減少したため、昭和四九年五月、cの判断で同工場は閉鎖された。cは、九州工場に赴任している間、陶磁器に興味を抱き、そのころから、三田青磁の復活を考えるようになった。 (2) ハムの製造、販売とレストラン経営の開始 ア cは、九州工場を閉鎖して帰郷したが、そのころからハムの製造、販売を考えるようになった。そして、cは、ハムの製造技術を収得するためドイツに赴き、同国内のハム製造工場に就職したが、ドイツのハムが日本人向けのハムとは限らないという考えもあり、当初の予定を切り上げて三か月ほどで帰国し、ハムの試作にとりかかった。 イ 右と併行して、原告は、ハムなどを製造することができるよう、昭和五〇年九月に本社工場にスモークハウス(薫製用施設)を設置し、昭和五一年五月二四日、神戸市北保健所に対し、本件建物の隣地にある原告本社工場の食肉処理場の一部を食肉製品製造業に変更する旨の食品衛生法上の届出をした(甲五〇の1ないし4)。 ウ そして、原告は、昭和五二年七月ころ、cの企画、立案のもと、はざま池畔に存する本件土地上に本件建物を建設し(本件建物の所有権の帰属については争いがある。【B事件】)、cを責任者(店長)として、「三田屋」の屋号(営業表示)でレストラン経営を開始した。 同年七月三〇日の開店に際しては、「株式会社丸優食品 テンダーレストラン三田屋 i」の名義で本件建物の上棟及びオープンの各挨拶状が出され(甲五九、六〇、 六一)、同日付読売新聞に「本場三田。牧場直営ステーキハウス。桜の木をいぶし、手づくりで丹念につくられた三田屋のオリジナル商品。 」と記載した広告が掲載され(甲一三三)、また、そのころ、「三田屋はマルユウグループを母体として、直営牧場では黒毛和種一五〇〇頭を常時飼育し、登録商標 本・三田肉 の名のもとに全国的に販売体制を整えております。」と記載したチラシが作成されている(甲二九)。 なお、原告の名義で、同年一〇月一七日付けで、営業所の所在地を本件建物所在地、屋号を「三田屋」、営業の種類を飲食店営業とする飲食店営業許可申請がなされ、同月一九日に兵庫県三田保健所から右許可が出されている(甲一一)。 エ 本件レストランでは、前菜として自家製のハムが提供されるようになったが、原告は、これと相前後して、右レストラン以外でも、「三田屋」の表示を使用したハムの販売を開始し、レストランの人気が高まるに従い、大手デパートにも出店して、「三田屋」の表示を使用したハムを販売するようになった。 (3) cによるレストラン経営の独立 ア 開店当初、cが責任者として本件レストランの経営に当たり、これを被告hが補佐していた。cは、前述した三田青磁を食器として使用し、青磁の大皿に薄くスライスしたハムを盛り、オニオンとドレッシングを添える前菜を提供したり、レストランでの生演奏を行うほか、高級外車を置くなど、レストラン経営に特徴を出すよう工夫を重ねていた。 イ cは、本件建物におけるレストラン営業を原告から独立させることを企図し、昭和五三年二月二七日以降、レストランの売上を原告に納入しなくなり、 同年四月一九日には、同人と被告hの連名で、原告に対し、「三田屋保有財産」と題する書面を提出し、独立するに当たっての財産の分配を要求した(甲六、一二二、証人mの原審証言)。 ウ 右の要求について、原告とc(被告会社)及び被告hとの間で何らかの明示の合意がなされた事実は窺えないものの、cは、そのころから、レストランの売上を納入しないかわりに、原告が中兵庫信用金庫に対して負担していた六〇〇〇万円の借入の返済資金を原告の口座に送金するようになり、原告もこれを黙認していた。 エ そして、cは、昭和五四年九月四日、本件レストランの経営を目的とする被告会社を設立し、代表取締役に就任した。 被告会社は、心身障害者を積極的に雇用したり、三田磁器の陶芸教室を開いたり、レストラン内でピアノ、琴、ジャズ等の生演奏をするなど、独自の営業活動を展開した(乙一ないし五)。 (4) 紛争の発端と顕在化 ア 昭和五四年一一月一四日にiが死亡し、iら兄弟の実母であるkも同月二九日に死亡した。iの死亡に伴い、妻のlが原告の代表取締役に就任し、aが専務に就任したが、実質的にはaが原告の実権を握るようになった。 イ cや被告会社は、レストランの売上を原告に納入しなくなった昭和五三年二月以降も、レストランで提供する食材の多くを原告から仕入れていたが、昭和五六年八月、原告におけるjの処遇を巡ってaとcとが激しく対立し、同年一〇月ころからは、原告と被告会社は断絶状態となり、ハムの製造は原告と被告会社とが各別に行うようになった。 ウ 昭和五六年一一月ころ、c、被告h及び被告会社は、原告が出店しているデパートに対し、原告の商品について「三田屋」の表示をさせないよう申し入れるなどし、本件の紛争に至った。 (二) 右の認定事実によれば、本件レストランが開店された昭和五二年七月末の時点での本件レストランの経営主体は原告であり、cはその使用人(店長)にすぎなかったが、昭和五三年三月ころ、cは、被告hとともに、原告からその経営を独立させ、被告会社がこれを引き継いだということができる。 もっとも、昭和五四年六月までの間、cに対して原告から給与が支払われていることが認められるところ(甲七)、右の事実によれば、原告が、cや被告hの独立を認めず、元の状態に戻ることを期待していたことが窺えるが、そのことから、直ちに、本件レストランの経営主体についての右の認定を左右するには至らないというべきである。 2 原告及び被告会社によるハムの製造販売の経緯 (一) 原告によるハム製造の開始 証拠(cの原審供述)によれば、前記のとおり、cは、昭和五一年八月にドイツから帰国し、同年九月ころから再びハムの試作にとりかかったが、その作業は、それまでに購入されていたハナキ製作所製のスモークハウスを使用して、原告工場内で行われていたこと、昭和五二年七月のレストラン開店後は、同店内にEC工業製のスモークハウスが設置され、そのころから本格的なハムの製造、販売が開始されたことが認められる。 右の事実に前記1で認定した事実経過を併せると、原告は、本件レストランの営業を開始した昭和五二年七月ころから、cを使用してハムの製造、販売を開始したということができる。このことは、その当時原告によって作成された新聞折込広告に、「三田屋の手作り商品」「本社技術陣が本場ドイツより持ち帰った技術に一本一本手作りにより丹念に仕上げられた最高級品 桜の木の香りを先様にお届け!」と記載されていること(甲二六の1ないし6)によっても裏付けられる。 (二) c及び被告会社によるハム製造の開始時期(昭和五三年三月から五六年一〇月までの期間中のハムの製造主体) (1) 被告会社は、昭和五二年七月に本件レストランの営業及びハムの製造販売を始めたのは原告ではなくてcであると主張するが、この主張が採用できないことは、これまでの説示により明らかである。そして、前記1(一)(4)イのとおり、 昭和五六年一〇月以降両者は別個にハムの製造販売を行うようになったというのであるから、問題はcが本件レストランの営業を独立させて経営主体となった昭和五三年三月から右の昭和五六年一〇月までの間のハム製造の主体をどう考えるかである。 (2) 被告会社は、遅くともcが本件レストランの経営を独立させた昭和五三年三月には、ハムの製造、販売を開始したと主張するところ、確かに、本件レストランにおいては、店内で燻煙したハムを前菜として提供していたほか、店頭で販売もしていたことが認められる。しかし、以下の事実に照らすと、その製造の主体は必ずしも明らかとはいえないし、また、その販売量がそれほど多かったとも思われない。 すなわち、証拠(甲六二、一四四、証人m、同n、同oの各原審証言)及び弁論の全趣旨によると、昭和五三年三月ころから同五六年九月ころまでにおける、原告の本社工場及び本件レストラン内に設置されたスモークハウスを使用したハムの製造工程は、次のとおりであったことが認められる。 ア 原料の豚の枝肉から、除骨、更に骨皮と脂肪の除去を経て、部位毎にブロックにカットし、血抜きをする。次に、形を整えてから、注射器によって、調味料と保存液を混合した液を肉に注入する。その後、液に漬け込み、一〇日から二五日間熟成、保存した後、漬け込んだ肉を水洗いし、塩分の濃度を調製する。 以上の工程は全て原告本社工場内で行われていた。 イ 残る工程は、ボイル工程とスモーク工程であるが、本件レストランに設置されたEC工業製のスモークハウスは、ボイル、スモーク及び乾燥の工程を一度にできる機能を有していたので、アの工程を終えた肉を本件建物に運んで、残りの工程を行っていた。 なお、原告本社工場に設置されていたスモークハウスでは、ボイル工程を別途行ってから、スモークハウスで燻煙し、乾燥させる必要があった。 ウ 右のようにして燻煙の終わったハムの一部は、本件レストランで提供、販売されたが、残部は、再び原告本社工場に戻され、真空パックされた上、原告の名で出荷された。 エ なお、これらの製造工程は、当初、cの指導のもと行われていたが、 その後、実際にハムの製造管理を担当していたのは、主にjであった。 (3) また、右に加えて、以下の事実も指摘することができる。 ア 前記1(一)(4)イのとおり、c及び被告会社は、レストランの売上を原告に納入しなくなった後も、原告から食材の多くを仕入れていたが、c又は被告会社が、原告に対してハムを販売し、その代金を得ていたことを窺わせる証拠はない。 イ 昭和五三年三月から同五六年九月までの期間において、原告はc(その後被告会社)に対し、本件建物内のスモークハウスの使用料を支払っていた(甲一五二)。また、原告は、右の期間においても、販売していたハム等に貼付されていたラベルに、「三田屋KMS」の登録記号を記載していたが、「KMS」は「株式会社丸優食品」もしくは「株式会社、丸優食品、三田屋」の略であった(甲五三の1、証人oの原審証言。なお、被告会社は、右の期間中、本件レストラン以外の場所で原告がハムを販売していたこと自体は争っていない。)。 ウ これに対し、c又は被告会社が、昭和五六年一〇月以前の時点で、本件レストラン以外の場所において、ハムを販売していたことを認めるに足りる証拠はなく、むしろ、証人oの原審証言によると、被告会社内に営業部が設置されて、 oが営業部長付として百貨店等に商品を売込みに行ったというのは、昭和六〇年九月であることが認められる。 エ なお、昭和五六年一〇月以降、原告は、本件レストラン内にあるスモークハウスを使用することができなくなったため、新たにスモークハウスを導入し、一方、被告会社も、原告から仕込み済みの肉を仕入れることができなくなったため、最初の仕込み工程を含む全製造工程を自社だけで行うようになった。 (4) 以上の(2)、(3)の事実を総合すると、昭和五三年三月から同五六年九月ころまでの間は、原告とc(被告会社)は、少なくともハムの製造に関する限り、従前からの協力態勢を継続していたものと推認され、少なくとも、本件レストラン以外の場所で販売されていたハムについては、その製造、販売の主体は原告であり、原告は、その製造工程の一部を被告会社が占有、管理する本件建物内のスモークハウスを利用して行っていたにすぎないというべきである。 また、c(後に被告会社)が昭和五三年三月以降に本件レストランで提供、販売していたハムについては、c(後に被告会社)が、原告から購入した仕込み済みの肉(半製品)を自己の管理下にあるスモークハウスで燻煙して製品として完成させた上、これを提供、販売していたものと認めるのが相当である。 被告らは、原告がそれまで大手ハムメーカーである伊藤ハムと取引をしていたため、競合商品であるハムの製造、販売を原告名義で行うことができなかったから、 cがこれを行っていたと主張するところ、確かに、昭和五二年当時、原告と伊藤ハムとの取引関係が継続しており、原告が本件レストランを開店した後、伊藤ハムから何らかの申入れがあったことが窺えるものの、その具体的内容は明らかとはいえず、そのことだけで右の認定が左右されるとは考えられない。 また、被告らは、c(後に被告会社)がハムの製造、販売の唯一の主体であると繰り返し主張するところ、その根拠とするところは、当初、cが中心となってハムの製造を行っていたことと、ハム製造の最終工程の一つであるスモーク工程が本件レストランのスモークハウスで行われていたことにあると考えられるが、これらの事実をもって前記の認定を左右することができないことは、既に説示したところから明らかである。 3 原告表示の周知性の有無及びその取得時期について (一) 前記認定事実と証拠(甲一二ないし一六、一〇八、一一〇、一三三、 一四四、一七三ないし一九一、一九八、一九九、二〇六ないし二〇八、検甲二一ないし三一、九〇ないし一一三、l及びaの原審供述)及び弁論の全趣旨によれば、 以下の事実が認められる。 (1) 前記のとおり、原告は、遅くとも昭和五二年八月ころから、ハムの製造を開始し、「三田屋」の表示を使用して販売していたが、その後、「三田屋の手造りハム」の表示で販売するようになり、現在は、ハムのほか、ソーセージ、ドレッシング等を製造、販売しているところ、その包装や容器に「三田屋総本家」もしくは「はざま湖畔・三田屋・総本家」の表示が使用されている。 (2) また、原告は、三田駅前店ほか直営店を複数有しているが、昭和五五年に三田市内に開店したニチイにも出店し、「三田屋」の表示を使用して営業していた(もっとも、ニチイ店がその後「三田屋総本家」もしくは「はざま湖畔・三田屋・総本家」という現在の原告表示に変更したか否かは不明である。)。なお、原告は、三田駅前店は「マルユウ」の表示、三田市銀座通り店は「コアラ」の表示を使用して営業を行っている。 (3) 原告は、食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品を指定商品として、昭和五二年二月、「三田屋」なる標章について、商標登録出願を行ったが、登録には至らなかった。 (二) 原告は、「三田屋」の表示は、遅くとも昭和五二年末には、原告のハム等の商品表示として周知性を取得していたと主張するけれども、この主張事実を認めるに足りる証拠はない。 すなわち、昭和五二年当時における原告のハムの販売量は不明であり、その販路については、原告の直営店以外にも販路の存したことは窺えるものの(甲一によると、ゴルフ場やファミリーレストランなどでも販売されていたことが窺える。また、甲一四二、一四三によると、昭和五六年当時には、原告の商品を取り扱うデパート等小売店が相当数存在したことが窺えるが、これらの小売店において、ハムを販売していたのか、精肉を販売していたのかは不明である。)、その具体的内容は明らかではなく、これを認めるに足りる証拠はない。 原告は、「三田屋」の表示を付したチラシを製作、配布したことが認められるが、右チラシは、その形態から、直営店の地元に配布されたものにすぎないことが認められる上、「三田屋」の表示を付したハムの記載が中心となっているものは少ない(甲二六ないし二九、一四六)。 また、原告は、昭和五一年秋から、松茸昆布やしぐれ煮の製造を始め、これらを「三田屋」の表示を使用して販売するようになったが、その販売量や販路を明らかにする証拠はない。 そして、後記4のとおり、「三田屋」という表示が広く周知されるようになったのは、昭和六〇年ころ、本件レストランの営業表示としてであって、原告が本件レストランを経営していた昭和五三年三月ころまでに周知性を取得していたことを認めるに足りる資料も存在しない。 (三) 以上によれば、原告の製造、販売するハムの商品表示(原告表示)が、被告会社の営業表示及び商品表示である「三田屋」に先立って周知性を取得したものと認めることはできず、仮に原告表示が周知性を取得したといえるとしても、その時期は、被告会社の右表示が周知性を取得した時期よりも後であるというべきである。 4 被告会社表示の周知性の有無と取得時期について (一) 前記1のとおり、本件レストランは、開店当初から「三田屋」の営業表示のもと、原告がこれを経営していたが、昭和五三年三月ころ、その責任者であったcがその営業を原告から独立させ、翌昭和五四年九月に設立された被告会社が、cから右レストランの営業を承継したというべきところ、この事実関係によると、本件レストランの「三田屋」という営業表示は、当初、原告の営業であることを示すものであったが、昭和五四年九月以降は、被告会社の営業であることを示す表示であったということになる。 被告会社は、その後、レストラン経営を拡張し、直営店のほかフランチャイズ店を全国に多数有するようになったが、それらの店舗にいずれも「三田屋」「三田屋本店 やすらぎの郷」などの営業表示を使用して、レストラン経営を行っている。 また、前記2のとおり、被告会社は、本件レストランにおいて、前菜として自家製のハムを提供していたが、被告会社が製造したハムを本件レストラン以外で販売するようになったのは、昭和六〇年以降であり、その際の商品表示は、「三田屋の手造りハム」であった。 被告会社は、現在では、「三田屋本店 やすらぎの郷」の表示でハム等を製造、販売している。 (二) 被告会社は、「三田屋の手造りハム」は、c又は被告会社の商品表示として(また、「三田屋」が被告会社の営業表示として)、昭和五四年ころまで、 遅くとも昭和五六年ころまでに周知性を取得したと主張する。 証拠(乙一ないし五)によれば、c及び被告会社は、本件レストランの営業を原告から独立させた後、心身障害者を積極的に雇用したり、三田磁器の陶芸教室を開いたり、レストラン内でピアノ、琴、ジャズ等の生演奏をするなど、独自の営業活動を展開したこと、その結果、昭和六〇年中には、このようなレストラン経営や同店で出される手造りハムに関する話題が、各種の新聞に掲載され、本件レストランの営業表示である「三田屋」更には「三田屋本店」は、被告会社の営業表示として、消費者の間に広く認識されるに至り、また、これに伴って、「三田屋(の手造りハム)」の表示も、本件レストランで提供、販売される被告会社のハムの商品表示として、右と同じように広く知られるようになったことが認められる。 したがって、「三田屋」という表示は、昭和六〇年ころ、被告会社の経営していたレストランの営業表示として周知性を取得し、被告会社は、そのころから周知性を取得した右表示を使用してレストラン以外でもハムを販売するようになったといえる。 5 まとめ 前記のとおり、原告は昭和五二年八月ころから、その製造、販売するハムに「三田屋」という表示(原告表示)を使用していたことが認められるが、被告会社の本件レストランに係る営業表示が、周知性を取得したのは、昭和六〇年ころであって(被告会社のハムの商品表示が周知性を取得するのもそのころといえる。)、原告表示がこれより先に周知性を取得したと認めることはできない。 二 争点2(原告表示の先使用の抗弁)について 1 前記一3、4のとおり、原告は、「三田屋」が被告会社の経営する本件レストランの営業表示及び同店で提供、販売されるハムの商品表示として周知性を取得する前の昭和五二年八月ころから、その製造、販売するハム等に「三田屋」という表示を使用していたこと、その後、「三田屋の手造りハム」という表示を経た上、「三田屋総本家」「はざま湖畔・三田屋・総本家」という原告表示を使用するに至っていることが認められる。 そこで、現在の原告表示である「三田屋総本家」「はざま湖畔・三田屋・総本家」と従前の原告の商品表示であった「三田屋」との間の同一性の有無について検討するに、前者の各原告表示は、「はざま湖畔」と「三田屋」と「総本家」とから成るところ、「はざま湖畔」は所在地を示すものであり、「総本家」にも特別な顕著性はない上、「はざま湖畔」も「総本家」も「三田屋」に比べ小さく記載されているから、これらの表示の要部は「三田屋」と解すべきであり、この「三田屋」の部分と当初使用されていた「三田屋」の表示とを対比するに、字体はほぼ同じであり(甲一〇八ないし一一〇によると、最も初期に使用された「三田屋」の表示には、アルファベットで記載されたものもあるが、昭和五二年に配布されたチラシや同年に出願された商標の字体は、現在使用されている原告表示の「三田屋」に類似しており、早い段階で、現在の原告表示のうちの「三田屋」の部分が使用されるに至ったと推察される。)、観念、称呼ともに同一であり、現在の原告表示の使用は、原告が当初使用していた表示の使用の継続として、同一性を有するものというべきである。 そうすると、現在の原告表示の使用は、被告会社の前記表示に先行するものとして、法11条1項3号の適用を受ける余地がある。 2 そこで、以下、原告の現在の原告表示の使用をもって、法11条1項3号所定の「不正の目的のない使用」といえるかどうかについて検討するに、当裁判所は、前記一1ないし4で認定した事実関係に照らすと、原告の現在の原告表示の使用には不正な目的はないものと認めるのが相当と考える。すなわち、 (一) そもそも、「三田屋」の表示は、原告が精肉等自己の商品の表示として、昭和五二年までに使用を開始していたものであって、同年七月末に本件レストランを開業するに際して、これを同レストランの営業表示としたものであり、そのころから開始されたハムの製造、販売に当たっても、「三田屋」が原告の商品表示として使用されていた。しかるに、昭和五三年三月にcが半ば強引に本件レストランの営業を独立させ、被告会社がこれを引き継いで発展させたものである。 そして、被告会社において、本件レストランの営業表示としての「三田屋」の名声を広め、昭和六〇年ころその周知性を獲得したとはいうものの、その間、原告としても、自己が製造したハム等に「三田屋」の表示を付することを継続していたのであって、前記一2(二)(4)で説示した昭和五六年九月までの両者の協力関係に照らすと、右の原告の行為が被告表示である「三田屋」の名声を高めるのに寄与した面も否定できないから、原告の行為をもって、単純なフリーライドと同視することはできないというべきである。 (二) 被告会社は、昭和五六年一〇月以降の原告の一連の行動(子会社の設立、商品表示の変更等)に照らして、昭和六二年に始まる現在の原告表示の使用には不正の目的があると主張する。 (1) 原告が昭和五六年一二月一〇日に子会社として「株式会社丸優三田屋」を設立したこと、これに対して、被告会社が昭和五八年八月八日に「株式会社三田屋」から現在の「株式会社三田屋本店」に商号を改めたところ、昭和五九年一一月二六日に原告が右子会社の商号を「はざま湖畔三田屋本店株式会社」と改め、 更に、昭和六三年二月二〇日に「株式会社はざま湖畔三田屋総本家」と改めたこと、以上の被告会社主張事実については、弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。 しかし、右の子会社の設立及びその商号変更の大部分は、被告表示が周知性を取得した昭和六〇年よりも前の時点でなされたものである上、子会社に関するこれらの事実が、原告において、ハムの製造、販売に際して、原告表示を使用することの是非について直接の影響を及ぼすものとも考え難い。 (2) また、被告会社の使用していた「三田屋」の表示が、現在の被告会社表示である「三田屋本店」に改められた後、原告の表示を「三田屋の手造りハム」から「三田屋総本家」「はざま湖畔・三田屋・総本家」と改めたことをもって、必ずしも、当初のままの表示を続けることに比べ、より類似性の高い表示にしたということはできず、右変更をもって、直ちに、被告会社の後追いということはできないと考える。 (3) 原告は、一時期、一部のハムの表示について「三田屋」の表示の使用をやめたことがあったことが窺えるが、全てのハムについてそのような措置をとったわけではなく、一時的なことであったにすぎないから、右の事実をもって前記認定を左右するには至らないと考える。 なお、被告会社は、鑑定書(乙一二〇)を提出するが、同鑑定書は、前提事実を異にするので、右判断の妨げにならない。 3 まとめ 以上によると、仮に原告の商品表示である「三田屋」が周知性を取得したとしても、被告会社の営業表示としての「三田屋」が、原告の右表示に比べ、先に周知性を取得したというべきであり、原告の被告会社に対する、表示使用差止請求は理由がないことになる。 一方、前記2のとおり、原告は、被告会社の営業表示が周知性を取得する以前から、「三田屋」なる表示を使用しており、現在の原告表示はこれと同一性を有するというべきであるから、被告会社も、原告に対し、原告表示の使用の差止めを求めることはできないというべきである。 また、被告会社の原告に対する損害賠償の請求のうち、原告表示の使用を理由とする請求についても理由がないというべきである。 三 争点3(信用毀損行為の存否)について 1 証拠(甲一、二、四、六三ないし六五、原告代表者a及びcの原審各供述、証人m、同oの原審各証言)及び弁論の全趣旨によると、昭和五六年一一月ころ、cと被告hが、原告が出店していた高島屋に対し、原告の商品について「三田屋」の表示をさせないよう申し入れ、その結果、原告は、昭和五七年一月以降、しばらくの間「三田屋」の表示を使用して出店することをやめたこと(現在、原告は、高島屋において、原告表示を使用して出店している。)、また、そのころ、被告会社が、「三田屋の類似品にご用心下さい。」「三田屋のニセモノ商品が出まわり」などと記載したチラシを配布したことが認められる。 なお、原告は、cと被告hが、原告の得意先に対し、「原告の商品は、被告会社の商品の類似品であり、偽物である」旨触れ回ったと主張するが、その発言内容を正確に認定するに足りる証拠はない。 また、原告は、cと被告hが、大阪高島屋に対し、「原告の商品は偽物である。 原告と取引を続けるなら、高島屋が偽物を売っていると世間に訴える」等と脅したりしたと主張し、これに沿う証拠(甲六三)もあるが、この発言内容についても、 これを正確に認定するに足りる証拠はなく、右のとおり、「三田屋」の表示をさせないように申し入れたということ以上の事実を認定することは困難である。 2 そこで、前記各行為が違法な信用毀損行為に当たるか否かについて、以下検討する。 (一) デパートに対する申し入れについて 前述したとおり、昭和五六年九月までの間、原告本社工場で仕込んだ肉を本件レストラン内のスモークハウスで燻煙し、被告会社において、これを本件レストランで提供するとともに、原告において、真空パックをした上、本件レストラン外で販売していたと認められるが、その限りにおいては、原告が販売していたハムは、本件レストランで提供されているハムと同じハムであるということができた。 確かに、昭和五六年一〇月以降、ハムの製造過程は、完全に原告と被告会社との間では分化し、それぞれ独自に製造するようになったのであるから、原告としては、「三田屋」の商品表示を継続して使用することができたとしても、本件レストランで提供されるハムと同じであると述べることは、虚偽の事実を述べることになり、仮に、原告がそのような表現を用いて商品を販売する場合、被告会社が、原告のそのような販売方法を阻止するため、デパートに対し、原告が「三田屋」の表示を使用して商品を販売することがないよう要請したとしても、そのことが直ちに不正競争行為ということはできない。 しかし、原告において、本件レストランで提供されるハムと同じであると述べて販売する方法をとっていないにもかかわらず、「三田屋」の表示の使用を阻止する行為に出ることは、前記のとおり、原告が「三田屋」の商品表示を継続して使用することができる以上許されず、さらには、原告の商品に不良品がなかったり、原告の商品を購入した顧客から被告会社に対し苦情が寄せられていないにもかかわらず、そのようなことがあったとして、デパートに対し前述したような要請をすることが許されないことはいうまでもない。 本件において、原告がデパートに対して自己のハムが本件レストランで出しているのと同じハムであると述べて販売したことを認めるに足りる証拠はないから、高島屋に対するc及び被告hの前記申し入れ行為には疑問が残るけれども、同人らがデパートに提出した文書の記載の内容や申し入れに際して述べた事実が、虚偽であるとまで認めるに足りる証拠はなく、また、申し入れの内容をそれ以上具体的に認めることのできる証拠もないから、両名の前記行為が違法な信用毀損行為に当たると認めるには不十分である。 なお、その後、被告会社、c、被告hが、デパートに対し、同様の申し入れを継続して行ったと認める証拠はない。 (二) チラシの配布について 前記チラシにおいては、原告の製造、販売するハムを「ニセモノ」とまで記載しているが、右の記載は、本件レストランにて提供するハムとは異なる製造であることを知らせるだけでなく、あたかも原告のハムが不良品であるかのような誤解を与えるというべきであり、信用を毀損する行為というべきである。 もっとも、被告会社が、その後、前同様のチラシの配布を継続したと認めるに足りる証拠はなく、右の行為による原告の損害を特定することは不可能である。 3 一方、被告会社は、原告が、被告会社が大丸や西武百貨店に対してハム等を納品するに際し、様々な営業妨害を行ったと主張する。 大丸における営業妨害の主張については、乙二二及び証人oの原審証言にはこれに沿う部分が存するが、原告の大丸担当者に対する申し入れの具体的内容、また、 店内で配布されたという文書の具体的記載内容を裏付けるに足りる証拠はなく、直ちにこれを信用することができないだけでなく、被告会社が主張する損害が、原告の右行為に基づくものであると認めるに足りる証拠もない。 また、西武百貨店における営業妨害の主張については、原告がハム等を納品する際「三田屋」の表示を使用することが許されることについては、前記二のとおりであり、原告が同百貨店において「三田屋のレストランで出しているのと同じハムである。」と述べて販売をしたと認めるに足りる証拠はない。 4 まとめ (一) 前記のとおり、デパートに対する申し入れについては、これを違法な信用毀損行為とは直ちにいうことができないと考えるが、それのみならず、現在、 被告会社や被告hが、デパートに対する申し入れだけでなく、原告の主張する信用毀損行為を継続しているという証拠はなく、また、将来、同様の行為が行われる可能性が高いともいえない。しかも、c相続人が本件差止めの義務を、当然に承継するとはいえないと考える。 そうすると、被告らに対して信用毀損行為の差止めを求める原告の請求は、理由がないというべきである。 (二) 次に、c及び被告hのデパートに対する申し入れについては、前記2(一)のとおり、違法な信用毀損行為であったということができず、また、被告会社の行ったチラシ(甲一、二)の配布については、これがどの範囲でなされたのか、 また、その結果、原告においてどの程度の信用が毀損されたかについてはこれを認めるに足りる十分な証拠があるとはいえないから、原告の被告らに対する損害賠償請求も理由がないというべきである。 (三) 一方、前記3のとおり、被告会社の主張する原告の営業妨害行為も認められないから、これを理由とする被告会社の損害賠償請求も失当というべきである。 四 A事件のまとめ 以上によると、A事件についての原告及び被告会社の請求はいずれも理由がないので、A事件に関する原告の控訴を棄却し、A事件に関する被告会社及びc相続人の控訴に基づき、A事件原判決主文一項のうち右被告らに関する部分を取り消した上、右取消しにかかる部分を棄却し(被告hは、右原判決主文一項につき控訴を提起していない。)、被告会社のその余の控訴を棄却する。 事実及び理由その二(B事件関係)【原告対被告会社】 |
|
|
当事者の求めた裁判
一 原 告 1 原判決主文二、三項を次のとおり変更する。 (一) 被告会社は、原告に対し、金二億一七九七万一八二八円及びこれに対する昭和五四年三月四日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 (二) 被告会社は、原告に対し、平成五年五月二六日から明渡済みまで一か月金一三〇万円の割合による金員を支払え。 2 被告会社の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被告会社の負担とする。 4 1につき仮執行宣言 二 被告会社 1 原判決中、被告会社の敗訴部分を取り消す。 2 原告の請求をいずれも棄却する。 3 原告は、被告会社に対し、原判決別紙物件目録記載の建物(本件建物)につき、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4 原告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は、第一、二審とも原告の負担とする。 |
|
|
事案の概要
一 請求及び原審の判断 1 原告は、被告会社に対し、被告会社が原告所有の本件建物及びその備品一式を不法に占有しているとして、 (一) 所有権に基づき本件建物の明渡しを求めるとともに、 (二) 不法占有に基づく賃料相当損害金として、 (1) 昭和五四年九月四日から平成五年五月二五日までの分二億一四一一万円(月額一三〇万円)及びこれに対する昭和五四年三月四日から年六分の割合による遅延損害金、 (2) 平成五年五月二六日から本件建物明渡済みまで一か月一三〇万円の割合による金員の支払を求め、 (三) 商品の売掛代金三八六万一八二八円及びこれに対する昭和五四年三月四日から年六分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 2 被告会社は、本件建物を建築したのはcであり、同人から本件建物の贈与を受けたとして、本件建物の登記簿上の所有名義人である原告に対し、真正な登記名義の回復を求めた。 3 原審は、本件建物を建築したのは原告であるとして、原告の所有権を認め、前記1の原告の請求のうち、(一)の請求の全部、(二)のうち、①昭和五四年九月四日から平成五年五月二五日までの賃料相当損害金一四〇六万二〇八八円(月額八万五三七五円)及びこれに対する平成五年六月一四日から年五分の割合による遅延損害金の支払、②平成五年五月二六日から明渡済みまで一か月八万五三七五円の割合による賃料相当損害金の支払を求める部分、(三)のうち、売掛代金三八六万一八二八円及びこれに対する昭和五七年二月二七日から年六分の割合による遅延損害金を求める部分を認容し、その余の請求及び2の被告会社の請求を棄却した。 4 これに対し、原告及び被告会社の双方が控訴を提起し、前記第一のとおりの裁判を求めた。 二 争いのない事実 1 本件建物について、神戸地方法務局三田出張所昭和五二年九月二七日受付第一一四五四号をもって、原告名義の所有権保存登記がなされている。 2 被告会社は、昭和五四年九月四日以降、本件建物及びその備品一式を占有している。 3 原告は、昭和五六年九月一二日から同年一一月一四日までの間、被告会社に対し、三八六万一八二八円分の商品を売り渡した。 三 争点及び当事者の主張 1 本件建物及び備品の所有権の帰属 【原告の主張】 (一) 本件建物は、原告が昭和五二年七月に田口工務店に請け負わせて建築したものであり、備品も原告が購入した。 原告は、その建築資金を中兵庫信用金庫から借り入れ、原告において返済した。 本件建物の登記名義は原告であり、その後の税金の支払も原告が行っている。 (二) 被告会社がc及び被告会社において返済金を出捐したと主張する原告名義の六〇〇〇万円の借入は、本件建物におけるレストランの開店営業資金のための借入であり、建物の建築費のためのものではない。 したがって、右六〇〇〇万円の借入の返済金の一部をc及び被告会社が負担したとしても、c及び被告会社が本件建物の建築資金を負担したことにはならない。 【被告会社の主張】 (一) 本件建物は、cが建築したものである。 cは、原告名義で中兵庫信用金庫から建築資金として六〇〇〇万円を借り入れて請負代金の支払をし、その後、cにおいて右借入金の返済をしていた。 (二) cは、昭和五四年九月、被告会社に対し、本件建物を右借入金残金の引受けという負担付で贈与した。被告会社は、その後、右の借入金を完済した。 2 賃料相当損害金の額 【原告の主張】 本件建物及びその備品の使用料相当損害金は、一か月一三〇万円が相当である。 3 相 殺 【被告会社の主張】 (一) 仮に、本件建物の所有権が原告に帰属するのであれば、被告会社が原告の口座に入金した七四四六万六四八八円(前記六〇〇〇万円の借入の返済金)は、原告の不当利得となる。 被告会社は、右不当利得返還請求権を自働債権として、原告の賃料相当損害金請求権と対当額において相殺する旨の意思表示をした(平成一一年四月一五日の当審第八回口頭弁論期日)。 (二) 仮に前項の相殺が認められないとしても(不当利得六〇〇〇万円が認められない場合、原告の請求する賃料相当損害金がこれを超える場合)は、前記A事件「第二 事案の概要」中の「三 争点に関する当事者の主張」4の被告会社の主張で述べたとおり、原告は、被告会社に対し、原告が被告会社に対して請求する三〇〇〇万円を超える損害賠償債務を負っているほか、次のとおりの内容の損害賠償債務を負っているので、被告会社は、右三〇〇〇万円を超える損害賠償請求権(差額)を自働債権として、対当額において相殺する。 すなわち、原告は、平成六年三月一日から平成一一年二月二八日までの間に、 「三田屋総本家」という商標を使用して、少なくとも合計一億一五〇〇万円(売上三〇六億六九二〇万六一七五円のうち七五パーセントが右商標を使用して得た売上であり、原告の営業利益は、売上の〇・五パーセントである。)の営業利益を得ている。 なお、本件の受働債権は、形式的には、不法行為に基づく損害賠償請求権であるが、その実質は賃料請求権であるから、相殺禁止条項は適用されるべきではない。 【原告の主張】 (一) 被告会社は、そもそも前記の六〇〇〇万円を支出したことはなく、原告が、昭和五六年五月一日に右六〇〇〇万円の借入金残金を一括して支払っている。 また、右六〇〇〇万円は運転資金であって、建築資金は別途原告が支出している。 (二) 仮に、被告会社が自働債権として主張する債権の存在が認められる場合には、原告は、被告会社に対する本件の損害賠償請求権を自働債権として右の債権と対当額で相殺する旨の意思表示をする(平成一一年二月二三日の当審第七回口頭弁論期日)。 すなわち、前記のとおり、被告会社が本件建物及びその備品を占有することにより、月額一三〇万円を超える損害が発生している。 |
|
|
当裁判所の判断
一 本件建物及び備品の所有権の帰属(争点1)について 1 前提事実、第二の二の争いのない事実及び後掲各証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 (一) 原告は、レストラン用地としての本件建物の敷地部分の土地開発について、各行政機関の許可や権利関係者の同意を得る手続を行った(甲九一ないし一〇〇、一〇一の1ないし5)。 (二) 本件建物は、昭和五二年七月ころに完成しているが、その建築請負契約書(昭和五二年四月二九日付け)には、原告が注文主として記載されているし(甲一三五)、所有権保存登記も原告の名義でなされている。 (三) 原告は、中兵庫信用金庫に対する右レストランの建築及び開業資金の借入申込書(昭和五二年二月二五日付け)に、「ステーキハウスのその内容は非常にユニークなもので、全国では初めて、他の大手レストランが真似しようとしても不可能に近いものです。丸優はこのレストランのために、昨年三月から社員二名西ドイツのフランクフルトに技術習得に派遣させ、八月には帰国してオープンを前にオリジナル商品の開発に取り組んでおります。そしてオリジナル商品七種はすでに販売されており、その数字はウナギのぼりです。又別の社員一名は昨年一〇月からアメリカ、ロサンゼルスにおいて研修を重ね、今年五月帰国し、スタッフメンバー一同五月から二ヶ月間オープンをめざし最後の仕上げをする運びとなっております。それは一食肉店としてのレストランではなく、食肉産業を担った内容のものです。ここで製造するオリジナル商品はマルユウ直売店、他あらゆるネットワークで販売されていきます。」と記載した(甲七〇の1)。 (四) 本件建物については、昭和五二年四月二九日付けで原告を注文主とする工事請負契約書(甲一三五)が作成され、同年九月二七日付けで原告名義の所有権保存登記がなされており(前記争いのない事実)、本件建物の固定資産税等も原告が支払っている(甲一〇五の1ないし6、一五二)。 以上の事実を総合すると、原告は、本件建物におけるレストラン経営を原告の営業の重要な柱として位置づけており、自己の借り入れた資金によって、本件建物を建築し、その所有権を取得したものと優に推認することができる。 もっとも、原告は、本件建物の建設及びレストランの開店に要した費用は一億三〇六二万二五三二円であったと主張し、その内訳を記載した明細書(甲七三)を提出するが、これに記載された個々の費目についての裏付けはなく、また、請負代金額についても、五五〇〇万円と記載されているが、甲一四四(aの陳述書)で三八〇〇万円の誤りであったと訂正されており、しかも前掲甲一三五によると当初の請負工事代金は二三〇〇万円であったことが認められるなど、右の明細書の記載内容をを直ちに採用することはできない。したがって、本件建物の建築代金の額を確定することはできないが、そうであるからといって、前記の認定を左右することはできない。 2 被告会社は、cが原告名義で中兵庫信用金庫から借り入れた六〇〇〇万円をもって本件建物を建築したと主張する。 しかし、証拠(甲一〇三の3、乙二四)によると、被告会社が主張する六〇〇〇万円の借入れは、本件建物が完成して本件レストランが開業した後である昭和五二年八月三〇日になされたものであることが認められるから、原告が主張するように、右の六〇〇〇万円の全てが建築資金ではなくて、開業資金であった可能性も否定できないし、また、前提事実2、3から窺われる当時のcの地位(当時、被告会社は未だ設立されておらず、cは原告の従業員にすぎなかった。)に照らすと、右の借主がcであったとする被告会社の主張はたやすく採用することができない。 もっとも、被告会社の主張するように、c及び被告会社が、昭和五三年四月以降、本件レストランの売上金をもって右の六〇〇〇万円を返済したことが認められるが、前提事実2、3から窺われる被告会社設立の経緯に照らすと、右の返済は、 本件レストランの経営が原告から分離独立するに際しての暫定的な処置にすぎないと考えることも可能であるから、この一事をもって前記の認定を覆すことはできない。 3 したがって、被告会社の主張は採用することができず、そうすると、同被告は、昭和五四年九月四日(被告会社設立の日)以降の占有を正当づける権原を主張立証しないから、その占有は違法といわざるを得ない。 二 賃料相当損害金の額(争点2)について 1 備品について 原告は、被告会社による不法占有の対象物として、本件建物のみならず、その中に存在した備品一式をも主張する。 確かに、昭和五二年七月の本件レストラン開店当初において本件建物内に相当数の備品が存在したことは容易に推察でき、前記一に説示したところからすると、それらの備品類も原告の所有であったと推認されるけれども、しかし、当時具体的にどのようなものが存在したかを認めるに足りる証拠は見当たらないし、これらのうちどの程度のものが何時まで本件建物内に存在したかも不明である。また、被告会社は、昭和六二年四月に本件建物でのレストラン営業を廃止し、別の場所に移転して営業を継続しているが(前提事実6)、その際に原告所有の備品を持ち出して使用していることを認め得る証拠もない。 そうすると、不法占有の対象物に備品一式をも加えるべきであるとの被告会社の主張は理由がない。 2 本件建物の賃料相当損害金について (一) 原告は、本件建物と前記備品と併せて賃料月額一三〇万円とする本件建物及び備品に関する賃貸借契約書(甲一七)を提出するが、右書面には被告会社の押印はなく、原告によって一方的に作成されたものであることは原告の自認するところであるから、これをもって原告の主張事実を認定する資料とすることはできない。 (二) そこで、本件建物の使用料相当損害金について検討するに、本件建物に類似した賃貸借事例の資料の提出はなく(もともと、本件建物は、郊外の幹線道路に面しない土地に所在しており、類似事例を得ること自体困難が予想される。)、建物の価格と利回りによって賃料を算定する方法に合理性を認めることができるところ、証拠(甲六六、六七、一五二の別紙38、40、一〇五の2ないし6)によると、昭和五四年ころの本件建物の価格は二〇四九万○一三〇円を下らないことが認められ、期待利回りを五パーセントとすると、月額八万五三七五円(年額一〇二万四五〇六円)と算定される。 これと同様の原判決の判断に対し、当審において、原告、被告会社ともに特段の立証を追加しないことをも併せ考えると、当裁判所も、右の金額をもって本件建物の昭和五四年以降の賃料相当損害金と認めるのが相当と考える。 (三) そうすると、原告が第二の一1(一)で求めている昭和五四年九月四日(被告会社が設立された日)から平成五年五月二五日までの間の賃料相当損害金の額は、一四〇五万九五九〇円となる。 計算式 1,024,506×(119/365+13+145/365)=14,059590 また、この間、毎日生じる賃料相当損害金につき、その損害ごとにそれぞれ損害が生じた日から遅延損害金(年五分の割合)が発生するところ、平成五年五月二五日時点における遅延損害金の合計は、四八二万四五五八円となる(閏年を三六五日とし、かつ、一日の損害額が閏年とそうでない年と同額として計算する。)。 計算式 (1,024,506/365)×[(5009+5010)/2]×(0.05/365)=4,824,558 平成五年五月二六日以降については、前日までの賃料相当損害金累計(前記一四〇五万九五九〇円)にその後の遅延損害金が発生する。 三 相殺(争点3)について 被告会社は、六〇〇〇万円の不当利得返還請求権等を自働債権とし、右賃料相当損害金を受働債権として相殺を主張するが、右受働債権は不法行為に基づく損害賠償請求権であるから、被告会社の相殺の主張は、主張自体失当というほかなく、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。 被告会社は、右受働債権について、形式的には不法行為に基づく損害賠償請求権であるが、その実質は賃料であると主張するが、独自の見解で採用することはできない。 四 B事件のまとめ 以上によれば、B事件に関する原告の請求は、 1 本件建物の明渡し 2 昭和五四年九月四日から平成五年五月二五日までの賃料相当損害金及び遅延損害金合計として一八八八万四一四八円及び内賃料相当損害金合計一四〇五万九五九〇円に対する平成五年五月二六日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払 3 平成五年五月二六日から明渡済みまで月額八万五三七五円の支払 4 売掛代金として三八六万一八二八円及びこれに対する昭和五七年二月二七日から支払済みまで年六分の割合による遅延損害金の支払(争いがない。ただし、 遅延損害金については、原告は、訴えを変更した際、昭和五四年三月四日を起算日として請求するが、その理由はなく、訴状送達の翌日である昭和五七年二月二七日から発生すると考える。) を求める限度で理由があり、その余は失当であり、B事件に関する被告会社の請求は理由がない。 よって、B①の原告の控訴については、原判決主文二項を本判決主文二1のとおり変更し、その余の控訴を棄却し、B②の被告会社の控訴を棄却する。 事実及び理由その三(C事件関係)【原告対被告h】 |
|
|
当事者の求めた裁判
一 原 告 1 原判決を次のとおり変更する。 被告hは、原告に対し、三八七万〇五八八円及びこれに対する昭和五七年二月二六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、第一、二審とも被告hの負担とする。 3 仮執行宣言 二 被告h 1 原告の控訴を棄却する。 2 控訴費用は、原告の負担とする。 |
|
|
事案の概要
一 原告は、被告hに対し、 1 商品の売掛代金として一二五万三〇三五円、 2 商品を持ち去った不法行為による損害賠償金として二六一万七五五三円(合計三八七万〇五八八円) 並びにこれらに対する訴状送達の日である昭和五七年二月二六日から完済まで年六分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 原審は、1の売掛代金及び遅延損害金(一部)を認容し、2の請求を棄却した。 これに対し、原告が控訴を提起し、前記第一のとおりの裁判を求めた(被告hは、控訴を提起していない。)。 二 当審における争点は、原告の主張する不法行為の成否であり、具体的には、 「被告hは、昭和五六年五月一一日から同年一〇月一日までの間、売上伝票を操作するなどして、二六一万七五五三円相当の原告の商品(ハラミ等)を無断で持ち帰った。」との原告の主張事実が認められるかどうかである。 |
|
|
当裁判所の判断
当裁判所も、原告のC事件に関する請求は、前記第二の一1の売掛代金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断する。その理由は、次に述べるほか、原判決(C事件)理由一ないし四に記載のとおりである(なお、原告は、売掛代金についても訴状送達の日からの遅延損害金の支払を求めるが、代金の支払時期を認めるに足りず、訴状送達の翌日である昭和五七年二月二七日から遅延損害金が発生すると解する。)。 原告は、前記第二の二の証拠として甲一四八を提出するところ、右証拠によっても、昭和五六年一一月末までの売掛残高は二三万九六七五円にすぎず、原審において自白が認められた右の期間と重なる売掛との関係も明らかとはいえず、結局、原告の右主張を認めるに足りないといわざるを得ない。 そうすると、原告が当審で不服の対象としている請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であるから、原告の本件控訴は理由がない。 (当審口頭弁論終結日 平成一二年九月一一日) |
| 裁判官 | 若林諒 |
|---|---|
| 裁判官 | 山田陽三 |
| 裁判長裁判官 | 鳥越健治 |