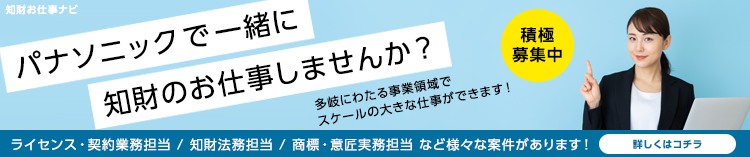| 関連ワード | 周知表示混同惹起行為(2条1項1号) / 周知性 / 広く認識 / 類似性(類似) / 印象 / 混同のおそれ(混同) / 商業登記 / 過失 / 利益額(利益の額) / 不当利得 / 代理人 / 代表者 / 得べかりし利益 / 識別力 / 混同のおそれ(混同) / 損害賠償 / 推定 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
11年
(ワ)
364号
商号使用禁止等請求事件
|
|---|---|
|
原告 株式会社高麗貿易ジャパン 訴訟代理人弁護士 裵薫 同 林範夫 被告 株式会社コリアワールドトレーディング 被告A 被告両名訴訟代理人弁護士 山枡幸文 |
|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2001/06/12 |
| 権利種別 | 不正競争 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 被告株式会社コリアワールドトレーディングは、原告に対し、金513万7842円及びこれに対する別紙遅延損害金目録②記載の金員を支払え。 2 被告株式会社コリアワールドトレーディングは、原告に対し、金299万8951円及びこれに対する平成10年10月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告Aは、原告に対し、金434万7265円及びこれに対する平成11年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用中、原告に生じた費用のうち10分の2を被告株式会社コリアワールドトレーディングの、10分の1を被告Aの各負担とし、被告株式会社コリアワールドトレーディングに生じた費用の10分の7と被告Aに生じた費用の10分の2を原告の負担とし、その余の費用を各自の負担とする。 6 この判決は、1項ないし3項に限り、仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
1 被告株式会社コリアワールドトレーディング(以下「被告会社」という。)は、原告に対し、金4729万9959円及びこれに対する別紙遅延損害金目録①記載の金員を支払え。 2 被告会社は、原告に対し、金299万8951円及びこれに対する平成10年5月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告Aは、原告に対し、金558万1044円及びこれに対する平成10年5月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
本件は、原告が、被告会社に対し、①被告会社が、旧商号「株式会社高麗貿易東京」を使用して営業を行ったことは、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、同法4条に基づきその損害賠償を、②原告と被告会社との在庫商品の売買契約に基づき、未払代金の支払をそれぞれ請求し、被告Aに対し、③上記在庫商品の売買は、被告Aが原告及び被告会社双方の代表取締役を務めている時に、被告Aによって原告と被告会社間でなされたものであって、商法265条1項の自己取引に当たるとして、同法266条1項4号に基づきその損害賠償を請求している事案である。 1 争いのない事実等(証拠の掲記のないものは当事者間に争いがない。) (1)ア 韓国法人である株式会社高麗貿易(以下「韓国本社」という。)は、韓国政府の中小企業輸出入活動支援の政策に基づき、公益法人である社団法人韓国貿易協会によって全額出資して設立された会社であり、韓国の中小企業の輸出入振興のための総合貿易商社という準公的な性格を有していた。 イ 原告は、韓国本社が全額出資する日本現地法人として、昭和61年に設立された各種韓国製商品の輸入販売等を目的とする株式会社であり、設立当初の商号は「株式会社高麗貿易大阪」であったが、平成元年8月25日に現商号に変更した。 原告は、当初大阪に本店を置いていたが、平成2年5月21日、東京に韓国商品総合展示場を開くと同時に東京支店を開設し(甲30、31)、平成5年4月1日、本店を東京に移すと同時に従来の本店を大阪支店としたものの、平成10年2月末に東京の本支店の廃止が決定され、同年5月31日東京支店を廃止するとともに、同年6月1日、本店を大阪に戻した(甲1)。 原告の代表取締役は、平成7年10月1日から、本店を大阪に戻した平成10年6月1日までは被告Aが、その後は現代表取締役であるBが務めている。 被告Aは、代表取締役の上記辞任と同時に取締役も辞任し、その後、同年8月31日に退社するまで従業員としての地位を有していた。 ウ 原告は、韓日の中小企業製品の輸出入窓口たる役割を担い、毎年、駐日韓国企業連合会及び社団法人韓国貿易協会東京支部が発行監修する駐日韓国企業名簿に、韓国政府指定中小企業製品貿易専門の総合貿易商社として登載されている。 また、原告は、全国各地において、韓国製品の販売のため精力的にイベントを主催するなどして、韓国の中小企業製品の輸出入販売において名声を得ており、こうしたイベントに対してしばしば感謝状を受けた。 エ 韓国本社は、経営が破綻し、平成10年9月3日付けで清算法人となり、同年12月に破産宣告を受けたが、Bは、その直前の同月4日、原告の全株式を1円で買い受けた(乙2の1・2、弁論の全趣旨)。 (2) 被告会社は、平成10年4月13日に、商号を「株式会社高麗貿易東京」として設立された各種韓国製商品の輸入販売等を目的とする株式会社であり、被告Aはその代表取締役を務めている。 被告会社は、本訴提起後の平成12年3月18日、現商号に変更し、同年4月26日、その旨の登記を経由した。 (3) 原告は、平成10年5月ないし6月ころ、被告会社に対し、別紙在庫商品目録の在庫商品(以下「本件在庫商品」という。)を合計994万8951円で売り渡した(なお、同売買契約の締結日について、原告は、同年5月28日であると主張し、被告らは、同年6月4日であると主張している。)。 被告会社は、平成10年6月5日、原告に対し同売買代金のうち695万円を支払ったが、残代金299万8951円は未払となっている。 2 争点 (1) 被告会社の旧商号の使用に関する不正競争防止法2条1項1号に基づく請求について ア 周知性 イ 類似性 ウ 混同のおそれ エ 旧商号の使用についての承諾の有無 オ 損害の発生及び額 (2) 本件在庫商品の残代金の請求について (3) 本件在庫商品の売買に関する商法265条1項違反を理由とする請求について ア 本件在庫商品の売買が自己取引に当たるか。 イ 相殺 |
|
|
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(被告会社の旧商号の使用に関する不正競争防止法2条1項1号に基づく請求)について (1) 周知性について 〔原告の主張〕 原告は、韓国中小企業製品の総合貿易商社として全国的に有名であるが、 被告会社が商圏とする東京ではとりわけよく知られている。 原告の販売業務は、イベントにより一般消費者を相手として小売を行うこともあるが、日常的には百貨店等の小売業者に対する卸売を基本としているから、 韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う東京の業者間において、原告の信用は揺るぎなく、その名は広く知られており、原告商号が周知であることは明らかである。 〔被告会社の主張〕 原告の主張は争う。 原告は、特に宣伝・広告を行っていないため、一般消費者に広く知られているといえないことはもちろん、韓国製品の小売業者の間においても、原告商号が、原告が主張するほど広く認識されているわけではない。また、原告商号は、 「高麗貿易」そのものではなく「高麗貿易ジャパン」であるから、なおさらその知名度は低い。 (2) 類似性について 〔原告の主張〕 原告商号「株式会社高麗貿易ジャパン」と、被告会社の旧商号「株式会社高麗貿易東京」とは、株式会社高麗貿易に続く語が「ジャパン」であるか、「東京」であるかの差異を有するだけであり、これらは、いずれも地名を意味するほか、何ら信用・名声等を化体する意味を有しない。 これに対し、共通する「株式会社高麗貿易」のうち、「株式会社」の語は法人の種類を意味するにすぎないが、「高麗貿易」の語はまさしく原告、被告会社の各商号の中心として識別の枢要部をなすものであり、そこには、原告の得てきた信用・名声が化体されている。 したがって、原告商号と被告会社の旧商号は類似するというべきである。 〔被告会社の主張〕 原告の主張は争う。 原告商号と被告会社の旧商号「高麗貿易東京」の類似性は、各商号の一部分を分解するのではなく全体として比較・判断すべきであるところ、両者の商号には、語尾に「ジャパン」と「東京」との差異部分があって、それらのカタカナで表示される英語と漢字との違いによって、視覚的にも称呼上もかなり異なった印象を与え、識別力を有している。 したがって、原告商号と被告会社の旧商号は類似するものではない。 (3) 混同のおそれについて 〔原告の主張〕 ア 原告の業務内容は韓国の中小企業製品の輸出入と販売にあるが、被告会社の業務もこれと同一であり、商業登記の目的欄の記載も、原告、被告会社ともに全く同一である。 イ 原告は、イベントによる小売のほか韓国製品の卸売を主たる業務としており、原告と被告会社は、共に、株式会社高島屋(以下「高島屋」という。)、株式会社ジェイエイエストレーディング、株式会社多慶屋、株式会社ビッグアロー、 全国農業協同組合連合会と取り引きしているが、これらは原告の主要な取引先であり、なかでも高島屋は原告の最も重要かつ大口の取引先である。 ウ 原告は、平成10年2月ころ、本店を大阪に戻して東京の支店を廃止することが決まっていたが、東京の商圏から撤退するものでなかった。 それにもかかわらず、被告会社は、そのころ、韓国本社の東京支店たる地位にあると詐称し、それを示すような「高麗貿易」の語句を含む被告会社の旧商号を用いることにより、高島屋を始めとする原告の上記取引先に混同を生ぜしめて取引を開始し、原告の東京における商圏を奪おうとしたものである。 〔被告会社の主張〕 ア 原告、被告会社ともに商業登記の目的欄の記載が同一であることは認めるが、その余の事実は否認する。 イ 原告がイベントによる販売を中心に行っているのに対し、被告会社は貿易業を中心に行っており、実際の業務内容は同一ではない。 また、原告は、本店を大阪に戻すと同時に東京から撤退し、被告会社が代わって韓国本社の東京支社の役割を果たすことになったものであるから、東京の商圏において混同のおそれはない。 (4) 旧商号の使用についての承諾の有無について 〔被告会社の主張〕 被告会社は、平成10年3月から5月ころ、韓国本社の社長C(以下「本社社長C」という。)が来日した際、本社社長C、原告代表者及び被告Aの三者の協議によって、被告Aが、東京で韓国本社とは資本関係のない被告会社を設立すること、その際、被告会社の商号を「高麗貿易東京」とすることについて了解を得た。 〔原告の主張〕 被告会社の主張は否認する。 なお、韓国本社及び原告が、被告会社に対しその旧商号の使用を承認する際には、「財産の処分」に準ずる行為として、韓国本社及び原告の取締役会の決議が必要と解されるところ、そのような取締役会決議がなされたことはない。 (5) 損害の発生及び額について 〔原告の主張〕 ア 原告は、被告会社の類似商号使用という不正競争行為によって、平成10年4月から、最も大口の取引先である高島屋との取引を失い始め、同年6月以降は、高島屋を含む東京本支店の取引先のすべてを失った。 これに伴い、原告は平成10年4、5月に高島屋の取引によって得られたであろう205万5914円の利益を失った。 また、原告は、東京支店における平成10年1月1日から同年3月31日までの90日間の売上利益の合計は585万8942円であったから、この期間当たりの売上利益を基準に日割計算すれば、別紙遅延損害金目録①の「損害発生月」欄の平成10年6月から平成12年4月までの各月(ただし、平成12年4月については同月25日まで)に、同目録の「元本」欄記載の金額の利益(合計4729万9959円)を失った。 また、被告会社は、類似商号使用という不正競争行為によって、上記金額の利益を上げているから、原告は同額の損害を被ったものと推定される(不正競争防止法5条1項)。 よって、原告は被告会社に対し、不正競争防止法2条1項1号、4項に基づき金4729万9959円及びこれに対する別紙遅延損害金目録①記載の遅延損害金の支払を求める。 イ 被告会社は、原告の東京圏における売上が減少したのは、原告が東京から撤退したことによるものであると主張するが、経験則上、いったん獲得した取引関係を維持するのはそれほど労力を要するものではなく、特に原告の営業は韓国から仕入れた商品を販売するのであるから、必ずしも東京支店がなければできないものではない。 〔被告会社の主張〕 原告の主張事実は否認する。 原告は、省力化を目的として東京から撤退したのであり、東京圏における営業の拠点を失って従来の取引先を放棄したことにより取引額が減少したものであって、被告会社の不正競争行為によって減少したものではない。 また、原告が得べかりし利益であると主張する金額は粗利益であるが、人件費・賃料等の一般管理費及び販売費その他の経費を控除すべきである。 2 争点(2)(本件在庫商品の残代金の請求)について 〔原告の主張〕 被告会社は、前記第2の1、(3)記載のとおり、原告から、平成10年5月28日、本件在庫商品を代金994万8951円で買ったが、代金299万8951円が未払となっている。 よって、原告は、被告会社に対し、同売買残代金299万8951円及び売買契約成立日の翌日である平成10年5月29日から商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。 〔被告会社の主張〕 原告の主張事実のうち、売買契約が成立した日が平成10年5月28日であることは否認するが、その余の事実は認める。 原告と被告会社の間で、本件在庫商品の売買契約が成立したのは、平成10年6月4日であり、その際、売買残代金299万8951円を同年9月末日までに支払う旨の合意をした。 3 争点(3)(本件在庫商品の売買に関する商法265条1項違反を理由とする請求)について (1) 自己取引の成否について 〔原告の主張〕 ア 被告Aは、原告の代表取締役に在任中の平成10年5月28日、原告の取締役会の承認を受けることなく、被告Aが代表取締役を務める被告会社に対し、 本件在庫商品を売り渡したものである。 本件在庫商品の売買代金994万8951円は原告の仕入原価と同額であり、原告が、通常の卸値で売却した場合には、558万1044円の利益を得ることができたから、被告Aの自己取引によって、同額の損害を被った。 よって、原告は、被告Aに対し、商法266条1項4号に基づき金558万1044円及びこれに対する売買契約日の翌日である平成10年5月29日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ 被告Aは、韓国本社の監査室長Dと、総務部長Eの立会いのもとで、本件在庫商品の売買契約が成立したと主張するが、この時、被告Aは原告の代表取締役であるとともに被告会社の代表取締役でもあり、そのような状況のもとにおいても、自己取引について原告の取締役会の承認が不要となるものではない。また、原告においては、平成9年3月31日から、非上場会社と500万円を超える売掛取引をするには韓国本社社長の決裁が必要とされていたから、韓国本社の監査室長D及び総務部長Eが立ち会っていたというだけでは、韓国本社の決裁を受けたことにもならない。 ウ さらに、被告Aは、本件在庫商品の売買契約が成立したのは平成10年6月4日であると主張するが、仮にそうであっても、商法265条1項が会社と取締役との間の取引に取締役会の承認を必要とした趣旨が、取締役がその地位を利用して自己の利益を図り会社を犠牲にすることを防止しようとしたことにあることからすれば、被告Aが内部決裁の手続をした同年5月28日の時点で取締役会の承認が必要であるというべきである。 〔被告Aの主張〕 ア 被告Aは、原告の取締役を辞任した後の平成10年6月4日、原告の東京事務所において、韓国本社の監査室長Dと、総務部長Eの立会いのもと、本件在庫商品の処分代金の支払について合意し、この時点で売買契約が成立したというべきである。 本件在庫商品の処分に係る決議書(甲12)の作成日は平成10年5月28日となっているが、同書面は売買契約書ではなく内部文書にすぎないし、その時点では売却予定の本件在庫商品を区分けして売却の準備をしていたにすぎないから、同決議書の日付を基準に契約日を決めるべきではない。 そして、本件在庫商品の売買については、韓国本社や、原告の取締役の全員が了解していた。 イ 被告会社は、当時韓国通貨ウォンが暴落しており、新規に韓国メーカーから商品を仕入れた方が売買代金価格より安く入手できたが、本件在庫商品は東京圏における規格商品的なもので、大阪ではすぐに買手がつかないものであったため、原告を支援するつもりで買い取ったものである。したがって、原告が主張するような通常の卸値で販売できた可能性は全くない。 また、原告は、同販売価格から仕入額を控除した粗利が得べかりし利益であると主張するが、他の経費を控除すべきである。 (2) 相殺について 〔被告Aの主張〕 被告Aは、平成10年5月末日をもって原告の代表取締役を退任した際、 原告との間で、退職金の支払に代えて同年6月から8月分の報酬の支払を受ける合意をしたが、同年8月26日から31日までの6日分の報酬の日割計算額金16万5788円の支払を受けていない。 また、原告は、被告Aのために住宅を賃借し、被告Aの毎月の報酬の中から翌月分の家賃15万円を差し引いていたが、被告Aに対し同年8月25日までの報酬の支払をする際、9月分の家賃15万円を控除するという計算違いをしている。 よって、被告Aは、原告に対し、金16万5788円の未払報酬請求権(平成10年8月26日から31日までの報酬)及び金15万円の不当利得返還請求権を有している。 被告Aは、原告に対し、平成12年2月3日の本件弁論準備手続期日において、上記合計金31万5788円の債権をもって、原告の被告Aに対する本訴請求債権とその対当額において相殺する旨の意思表示をした。 〔原告の主張〕 被告Aが、原告に対し、上記31万5788円の反対債権を有していることは認める。 |
|
|
争点に対する判断
1 争点(1)(不正競争防止法2条1項1号に基づく請求)について (1) 周知性について ア 原告は、韓国の公益法人である社団法人韓国貿易協会によって設立された韓国本社が昭和61年に全額出資して設立した日本法人であり、韓日の中小企業製品の輸出入窓口たる役割を担い、毎年、駐日韓国企業連合会及び社団法人韓国貿易協会東京支部が発行監修する駐日韓国企業名簿に、韓国政府指定中小企業製品貿易専門の総合貿易商社として登載されていること、原告は、全国各地において、韓国製品の販売のため精力的にイベントを主催するなどして、韓国の中小企業製品の輸出入販売において名声を得ており、こうしたイベントに対してしばしば感謝状を受けたこと、原告は、平成2年5月に東京支店を開設し、平成5年4月から平成10年6月までの間は東京に本店を置いていたことは、前記第2、1(1)記載のとおりである。また、証拠(甲11の1~7、甲21、32~39)によれば、原告の東京支店又は東京本店では、東京支店開設の翌年の平成3年以降、数十社の小売業者・通信販売業者等と取引をしていたことが認められる。 イ 原告が、韓日の中小企業製品の輸入窓口として、イベントを利用して一般消費者を相手に小売を行う業務のほか、韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う業者との取引も幅広く積極的に行っていた上記実情に照らせば、原告商号は、少なくとも韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う東京圏の業者間において、原告の営業を表示するものとして広く認識されていたというべきである。 (2) 類似性について ア 原告商号「株式会社高麗貿易ジャパン」と被告会社の旧商号「株式会社高麗貿易東京」とは、ともに「株式会社高麗貿易」との共通の文言が用いられているが、「株式会社」は会社の種類を表す語句であり、「ジャパン」は本邦を表す語(英語表記の日本語読み)であり、「東京」は本邦の首都ないしその地名で、「高麗」は「一般に朝鮮の称」を意味するから(岩波書店・広辞苑〔第五版〕)、「高麗貿易」とは韓国ないし朝鮮との貿易を意味する。 イ また、駐日韓国企業連合会及び社団法人韓国貿易協会東京支部発行の1997年度及び1998年度「駐日韓国企業名簿」(甲5、6)によれば、駐日韓国企業の中で貿易・製造業を営む会社として「高麗」の文字を含む会社には、原告のほかに「株式会社高麗商事」「高麗溶接棒ジャパン株式会社」の2社が記載されるのみであり、貿易・製造業を含むすべての業種を見ても「高麗貿易」との語句を含む会社は原告以外には存在しない。しかも、同「駐日韓国企業名簿」には、韓国企業名に「ジャパン」「東京支店」「東京事務所」等の語句を付した名称が数多く登載されるが、これらはいずれも韓国企業の子会社、関連会社、関連事務所等であることを示しているものと思われる。 ウ 以上のような語句の意味、他の駐日韓国企業の名称の実情に照らせば、 原告商号及び被告会社の旧商号の要部は、「高麗貿易」にあるというべきであって、各商号の語尾の「ジャパン」と「東京」との差異部分は要部には当たらないというべきである。 そうすると、原告商号及び被告会社の旧商号は、その要部が同一であって、各商号の語尾の差異部分について生じる称呼の違いや、カタカナと漢字の差異を含む視覚上の違いを考慮しても、被告会社の旧商号は、「高麗貿易」の語句を含む原告と同一の会社である、あるいは子会社、グループ企業等の原告と関連する会社であるとの認識を与えるものというべきであり、原告商号に類似することは明らかである。 (3) 混同のおそれについて ア 原告と被告会社は、その商業登記の目的欄には、1項に衣料品、日用品から工業部品に至るまで、数多くの商品が(1)~(16)項にわたり詳細に記載され、それら商品に係る「販売及び輸出入」「輸出入代行」「輸出入取引斡旋」を始めとして、「不動産の賃貸」「飲食店業」「イベントの企画」及びこれらの業務に「附帯関連する一切の業務」が掲げられているが、これらは全く同一の記載内容となっている(甲1、2)。 イ そして、前記(1)記載のとおり、原告の実際の販売業務は、イベントによる一般消費者を相手とした小売のみならず、韓国の中小企業製品を仕入れて小売・通信販売を行う業者との取引等であり、証拠(甲4、11の1~7)によれば、原告は、会社案内において、自らを「韓日両国の中小企業製品の輸出入窓口として役割を果たしている」と紹介し、その取引先には、高島屋、株式会社ジェイエイエストレーディング、株式会社多慶屋、株式会社ビッグアロー、全国農業協同組合連合会があることが認められる。 一方、甲10によれば、被告会社は、会社案内において、設立趣旨を「弊社は、14年間に渡って日韓の中小企業の輸出入の窓口としてその役割を果たしてきました(株)高麗貿易ジャパン東京の閉鎖により、その職員一同が新たな活動の場として設立した会社であります。元親会社である韓国の(株)高麗貿易との資本関係はございませんが、今後も弊社が日韓の中小企業の橋渡し役として活躍できるよう、今まで同様韓国中小企業側の様々な情報や供給に関わる支援を頂きながら、引き続き東京支社としての役割を務める事となりました。」などと記載して、 日韓の中小企業製品の輸出入窓口としての役割を強調し、また、主要な販売先として、原告の上記5社の取引先を含む8社が記載されていることが認められる。 そうすると、原告と被告会社は、いずれも韓国製品の製品を仕入れて小売を行う業者を相手に、韓日の輸出入窓口の役割を担う業務を行い、その主要な取引先5社が共通するなど、主要な取引先及び業務内容が同一であるから、被告会社が、前記のとおり原告商号と類似した旧商号を用いて上記営業を行うことは、原告の業務と混同のおそれ生じさせるものであることは明らかである。 ウ なお、被告会社は、原告が東京の本支店を廃止すると同時に東京の業務から撤退し、被告会社が代わって韓国本社の東京支社の役割を果たすことになったものであるから、混同のおそれはないと主張する。 しかるところ、被告A作成の陳述書(乙1、6)、監査室長D作成の確認書(乙2の1・2)、F作成の陳述書(乙15)、証人Fの証言、被告A本人(兼被告会社代表者)尋問の結果中には、原告の東京支社における大宏電機株式会社(以下「大宏電機」という。)との取引については、東京支社の廃止に伴い原告の大阪支社に引き継ぐが、その余の取引については被告会社が引き継ぐことになった旨の記載、供述部分がある。しかし、後記(4)のア(オ)記載のとおり、平成10年5月20日に韓国本社が作成した「東京支社閉鎖に関連する後続措置 通知」と題する書面には、「大阪支店長は、東京支社のすべての業務を徹底的に引き受けるようにする。」と記載されており(甲56)、また、後記(4)のア(ク)記載のとおり、韓国本社の任意清算人らは、被告会社の旧商号の使用承諾の有無について、被告A、原告代表者B、本社社長Cから事情聴取し、幹部6名による協議の上、被告Aに対し、 営業権無償譲渡に伴う利益金回収要求等を求めるとする結論を出しており、こうした事実からすれば、原告の当時の親会社である韓国本社は、被告会社が原告の東京支店の営業を引き継ぐことについて承諾をしていなかったと認めるのが相当であり、上記証拠中、これに反する記載、供述部分を採用することはできない。 (4) 承諾の有無について 被告会社 は、平成10年3月から5月ころ、本社社長Cが来日した際、本社社長C、原告代表者及び被告Aの三者の協議によって、被告Aが、東京で韓国本社とは資本関係のない被告会社を設立すること、その際、被告会社の商号を「高麗貿易東京」とすることについて了解を得たと主張する。 前記のとおり、Bが原告の全株式を取得した平成10年12月4日以前は、韓国本社が原告の全株式を有し、原告は韓国本社の決裁を受けて業務を行っていたこと、原告は韓国本社の子会社として設立され、そうした韓国本社との関係を示す趣旨でその商号に「高麗貿易」との文言が付されていることからすれば、韓国本社による被告会社の旧商号の使用についての了解があれば、被告会社の旧商号の使用は違法性を阻却され不正競争行為には該当しないものと解されるので、韓国本社及び原告が、被告会社の旧商号に使用について承諾していたか否かを検討する。 ア 証拠(甲17、51、52、56、乙1、2の1・2、6、7及び8の各1・2、17及び18の各1・2、被告A本人、原告代表者)によれば、次の事実が認められる。 (ア) 韓国本社は、平成9年の韓国におけるウォン為替の急落に伴って為替損を被り、経営状況が悪化したため、原告等の国内外支社の撤退、本社人員削減等を柱とする再建計画を立て、平成10年2月ころ、原告の東京本支店を廃止して、ひとまず業務を大阪に移すことを決定した。 (イ) 被告Aは、上記決定を伝えられ、平成10年3月1日から同月3日にかけて、韓国本社に赴き、本社社長Cから上記方針の説明を受け、同月11日ころ、当時原告の大阪支店長であったBと、原告の東京本支店の廃止、被告Aが設立を考えている新規法人の件について協議し、その後、同年3月27日から同月31にかけて、本社社長Cが来日した際、被告A、Bとともに、上記事項について協議し、東京の現地従業員は同年5月31日付けで解雇すること、原告東京本支店で扱っていた大宏電機との取引は、大阪支店が引き継いで取引を継続すること、東京本支店の廃止に伴い不要となった什器備品等は新規法人が引き取って使用すること、 被告A(東京支社長)は現地退職することとするが、原告は被告Aに対し同年8月まで給料を支払うこと等の取り決めをした。 (ウ) 被告Aは、同年4月13日、商号を「株式会社高麗貿易東京」とする被告会社を設立した。 (エ) 同年5月15日から同月16日にかけて、本社社長Cが来日し、被告A、Bの3名は、上記(イ)の事項を再度確認した。 (オ) 韓国本社は、同年5月20日、被告A及び原告大阪支店長Bに対し、「東京支社閉鎖に関連する後続措置 通知」と題する書面を送付した。同書面には、上記(イ)記載の内容が記載されているが、「業務引受引継ぎ指針」の項には、「大阪支店長は、東京支社のすべての業務を徹底的に引き受けるようにする。」と記載され、原告東京支社の大阪支店への引継ぎが大宏電機に限定した内容ではなく、また、被告会社が、原告の東京支社の業務の一部を承継するような記載は一切なかった。 (カ) 被告Aは、同年5月21日、韓国本社に対し、新会社「株式会社高麗貿易東京」を設立して、原告の東京支店の在庫を引き継ぐ予定である旨の内容を記載した連絡書をFAX送付したが、それに対する韓国本社からの回答はなかった。 (キ) 同年6月4日ころ、韓国本社の監査室長Dと、総務部長Eが来日し、被告A、Bとともに本件在庫商品の処理の件等を話し合った。 (ク) Bは、韓国本社に対し、平成10年8月29日付け書面で、本件訴訟の提起についての裁可を求めた。 被告Aは、同年10月8日付け書面で、韓国本社から上記訴訟の提起に関して釈明する機会を与えられたことから、同月20日付け書面により、韓国本社に対し、自らの言い分を伝えた。 韓国本社の任意清算人代表G、同室長Hは、同月23日、本社社長Cに面談したところ、本社社長Cは被告会社に対する本件在庫商品の処分及び「株式会社高麗貿易東京」の名称使用について承諾した事実はないとの報告を受けた。 その上で、任意清算人代表Gら6名の幹部で処理方針を協議した結果、被告Aないし被告会社に対し、①本件在庫商品の売却残金及び売上利益の速やかな入金要求、②商号名義変更及び営業権無償譲渡に伴う利益金回収要求等を求めるとの結論に達し、B及び被告Aに対し、その旨の報告をした(以下「本社清算人報告」という。)。 イ(ア) 被告会社は、上記アの(イ)~(エ)記載の事実経過の中で本社社長C、原告代表者及び被告Aの三者の協議によって、被告会社の旧商号の使用について承諾を得たと主張し、被告A作成の陳述書(乙1)及び被告A本人尋問の結果中には、以前に韓国本社の光州支社長が高麗貿易光州という商号で独立したことがある、本社社長Cから、新規会社設立後の同年5月に、新規会社が日本の法務局で「株式会社高麗貿易東京」の商号で登記された以上、同商号使用を了解すると言われたとの被告会社の上記主張に沿う供述部分があるが、仮に韓国において「高麗貿易光州」の商号を使用した例があっても、そのような事実が直ちに韓国本社が日本において被告会社の旧商号の使用を承認したことを推認させるものではないし、本社社長Cから了解を得たとの供述部分は、口頭で了解を得たというものであって具体性に欠ける。 また、乙7の1・2によれば、被告Aの手帳の同年5月16日の欄に、本社社長Cが来日した際の合意内容として「商号(株)高麗貿易東京に対しこれ以上問題視しない-法務局に登記完了」との韓国語による記載があることが認められるが、これについても被告Aが備忘のために記載したものであって、本社社長Cの承諾を客観的に裏付けるものではない。 さらに、監査室長D作成の確認書(乙2の1・2)には、同年6月4日ころ、韓国本社の監査室長D及び総務部長Eが来日した際、被告A及びBとともに、 被告会社が旧商号を使用することは問題にはならないとの結論を出した旨の記載があるが、監査室長D及び総務部長Eに旧商号使用についての決裁権限があることを認めるに足りる証拠はなく、韓国本社の意思として、被告会社の旧商号の使用を認めたことを立証する証拠としては採用できない。 (イ) そして、被告Aが述べる上記内容は、清算人代表Gらが、本社社長Cは被告会社の旧商号の使用について承認した事実はないとの報告を受けたことと食い違うものである。 もっとも、本社清算人報告には、「2 類似商号使用・この問題もAとC社長の主張が異なり、仮にC社長が許可したとしても、これは商号使用を許可しただけで、営業権の使用まで許容したことではない。」との記載もあり、同清算人も本社社長Cの言明に多少の疑問を抱いていることが窺われる。しかし、本社清算人報告における最終的な協議の結果は、上記のとおり、被告会社の旧商号の名義変更を求めるというものであるから、結局、本社清算人らは、被告Aの言い分を採用せず、本社社長Cが被告会社の旧商号使用を承諾していないとの結論に至ったものと推認される。 (ウ) なお、本社清算人報告の内容について、被告A作成の陳述書中には、Gは、事実関係を十分に確認していない状態で一方的に原告側に立って決定するなど不当に業務処理をし、結局、原告の全株式をBに1円で売却したから、同人の作成に係る本社清算人報告の内容は信頼することができない旨の記載(乙5)、 及び「原告代表者は、韓国本社の社長以下経営陣が健在の時には合意によってどうしようもなかったのですが、後で本社が清算される事になり社長以下経営陣が全員交代し、結局破産される過程でB(原告代表者)が任意清算人と親密ということを利用」したものであるとの記載(乙6)があるが、上記被告Aの陳述書のほかには、Gが上記のような原告側を不当に優遇する業務処理をしたことを裏付ける証拠はない。 これに対し、本社清算人報告の内容は、前記のとおり、GのみならずHも同行して確認し、Gが任意清算人という立場で報告していること、被告Aからの意見を聴取した上で調査していること、幹部6名で協議した上での結論であることなど、具体的かつ客観的な内容であるから、上記被告A作成の陳述書のみから、 直ちに本社清算人報告の内容が信用できないとすることはできない。 (エ) 結局、本社清算人報告の上記内容は信用に値するものであって、この内容に照らせば、前記(ア)記載の被告A及び監査室長Dの供述ないし記載部分を、韓国本社が被告会社の旧商号の使用を承諾したことの証拠として採用することはできず、その他、韓国本社が被告会社の旧商号の使用を承諾したことを認めるに足りる証拠はない。 (5) 以上認定の事実によれば、被告会社が原告の商号と類似する旧商号を用いて営業をしたことは、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するというべきであり、また、被告会社の代表取締役である被告Aには上記不正競争行為をするについて少なくとも過失があったものと認められるから、被告会社は原告が被った損害を賠償する義務がある。 (6) 損害の発生及び額について ア(ア) 原告は、被告会社の類似商号使用という不正競争行為によって、原告は平成10年4、5月に高島屋の取引によって得られたであろう205万5914円の利益を失ったと主張する。 そして、甲11の1~5によれば、原告東京支店の高島屋通信販売事業部に対する平成10年1月から5月までの売上高の推移は以下のとおりであることが認められる。 上記売上の推移によれば、被告会社が設立された平成10年4月13日頃から原告の高島屋に対する売上が減少していることが推認される。 しかしながら、そのほかに、上記売上の減少が被告会社が高島屋と取引をしたことによるものであることを認めるに足りる証拠はなく、かえって、被告A本人尋問の結果及び原告の東京支店に勤務していた証人Fの証言中には、被告会社は、原告の東京本支店が閉鎖になる半月くらい前の平成10年5月中頃から取引先への挨拶回り等の準備を開始し、高島屋等との具体的な取引は、同年6月になってからであるとの供述があり、これらに照らせば、上記売上の推移のみから、同売上の減少が被告会社が高島屋と取引を開始したことによるものであると推認することはできない。 したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。 (イ) 次に原告は、東京支店の平成10年1月1日から同年3月31日までの90日間の売上利益を基にして、平成10年6月から平成12年4月までの間、同売上利益に相当する利益(期間に応じて日割計算)を失ったと主張する。 しかしながら、被告A本人尋問の結果によれば、東京本社には閉鎖前6、7人の従業員がいたことが認められ、原告は、平成10年6月以降、これらの従業員を解雇するとともに東京にあった事務所を閉鎖したものであるから、被告会社が東京において営業を開始しなかったとしても、原告において東京本支店が健在のころの東京圏での取引による利益に相当する額を上げることが可能であったとは経験則上認めることができず、東京本支店閉鎖前の利益額をそのまま原告の損害であるとすることはできない。 なお、原告は、いったん獲得した取引関係を維持するのはそれほど労力を要するものではなく、必ずしも東京支店がなければできないものではないと主張する。しかし、乙16の1・2によれば、平成9年1月から12月までの原告東京支店の売上利益は7085万1616円、売上利益から販売費・一般管理費を控除した営業利益は-1987万円、経常利益(税引前当期利益も同じ)は-2126万6160円であることが認められ、被告会社が営業を開始した前年における原告東京支店の営業利益、経常利益が赤字であり、取引関係を維持するために、売上利益を上回る販売費・一般管理費を要していたものである。したがって、いったん獲得した取引関係を維持する場合であっても、得べかりし利益の算定において、販売費・一般管理費を考慮しない売上利益を基準にすることはできないというべきである。 したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。 イ また、原告は、被告会社は類似商号使用という不正競争行為によって上記アにおける原告主張の金額と同額の利益を上げているから、原告は同額の損害を被ったものと推定される(不正競争防止法5条1項)と主張する。 しかし、上記アにおける原告主張の金額は、原告の売上減少額ないし原告の従前の東京支店における売上額であって、この金額をもって直ちに被告会社が得た利益とすることはできない。そこで、被告会社が実際に得た利益額について検討する。 (ア) 証拠(乙22及び23の各1~3)によれば、被告会社の利益は次のとおりであることが認められる。 (イ) 被告会社は、旧商号を用いて営業をしていたものであるから、被告会社のすべての売上が不正競争行為によるものというべきであり、その利益の算定に当たっては、同売上に対応する販売費・一般管理費を考慮して被告会社の利益を算定すべきであるというべきところ、平成10年度及び平成11年度の営業利益はいずれも数万円程度の赤字となっている。 (ウ) しかし、販売費・一般管理費に含まれる被告Aが得ている上記役員報酬は、実質的には被告A自身が決定するものであるから、その額が直ちに適正なものであるということはできない。 そして、乙13によれば、被告Aが原告在職中に得ていた給与は、基本給26万6020円、職務手当25万円(住宅賃料15万円を含む。)、家族手当6万2154円、海外勤務手当23万0770円、食事手当2万円の合計80万8944円であることが認められる。 上記給与のうち、海外勤務手当は、原告が韓国本社の子会社であり、 取締役ないし社員を韓国から本邦に派遣したことに伴う手当という趣旨のものと解されるが、被告会社は、被告Aが自らの意思で設立しその経営に当たっているものであるから、被告会社において被告Aが海外勤務手当の支給を受ける理由はない。 また、乙25によれば、被告Aの住宅家賃15万円は、被告会社の地代家賃として計上されていることが認められる。 そうすると、被告会社の利益の算定に当たり、被告Aが得るべき適正な役員報酬月額は、原告において従前得ていた報酬(82万8944円)をもとに、上記事情を考慮して住宅賃料15万円及び海外勤務手当23万0770円を控除した44万8174円が相当であるというべきである。 (エ) 乙25によれば、被告Aは、平成10年度分の役員報酬は6月分から支給を受けていることが認められ、また、被告Aが平成10年5月末日まで原告の代表取締役であったことからしても、被告会社における平成10年度分の役員報酬は6月から12月までの7か月分を計上するのが相当である。 そうすると、役員報酬の相当額は、平成10年度は役員報酬月額の7か月分に相当する313万7218円、平成11年度は、12か月分に相当する537万8088円となる。 これをもとに、上記(ア)の計算表を修正すると以下のとおりとなる。 被告会社は、平成10年6月から実質的に営業を開始して、平成11年12月までの19か月間に、上記営業利益の合計427万5299円を得たものであるから、被告会社が得た利益の月額は22万5015円とするのが相当である。 (オ) そうすると、被告会社の不正競争行為により被った損害は、平成10年6月から平成12年3月までの各月は22万5015円、同年4月1日から、 旧商号の変更登記がなされた日(この時点で、被告会社の営業を示す外部的な表示が現商号に変更されたものと認められる。)の前日である同月25日までは18万7512円(上記月額を30日分として日割計算)、合計513万7842円と推定される(不正競争防止法5条1項)。 (6) 以上によれば、原告の被告会社に対する不正競争防止法2条1項1号、4条に基づく損害賠償請求は、金513万7842円及びこれに対する別紙遅延損害金目録②記載の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 2 争点(2)(本件在庫商品の残代金の請求)について 被告会社が、平成10年5月ないし6月ころ、原告に対し、本件在庫商品を合計994万8951円で売り渡したこと、被告会社は、同売買代金のうち695万円を支払ったが、残代金299万8951円が未払となっていることは争いがない。 そして、後記3の(1)ア記載のとおり、同売買契約が締結されたのは平成10年5月28日であり、そのころ本件在庫商品の引渡しがなされたこと、原告と被告会社との間で、残代金299万8951円を平成10年9月30日までに支払う旨の合意をしたことが認められるから、原告の被告会社に対する本件在庫商品の売買残代金の請求は、金299万8951円及びこれに対する売買残代金の支払日の翌日である平成10年10月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。 3 争点(3)(商法265条1項違反を理由とする請求)について (1) 本件在庫商品の売買が自己取引に当たるか。 ア 証拠(甲12の1・2、13、14、41の1・2、45、乙1、2の1・2、 3、4、6、14、被告A本人、原告代表者)によれば、次の事実が認められる。 (ア) 被告Aは、原告の本件在庫商品を被告会社が買い取ることとし、平成10年5月28日付けで、本件在庫商品について、その帳簿価格(仕入値)相当額(合計947万5193円)を「売上高」に、その消費税相当額(合計47万3758円)を「仮受消費税」に、同「売上高」及び「仮受消費税」の合計額(994万8951円)を「売掛金」にそれぞれ計上する内容の決議書を作成した。 本件在庫商品は、倉庫会社である有限会社大曽根商店(以下「大曽根商店」という。)に保管してあったものであるが、被告Aは、本件在庫商品を被告会社が買い取るため、平成10年5月29日、大曽根商店に指示して、本件在庫商品を他の在庫商品と区別させた。 なお、大曽根商店が作成した、同年6月1日時点において預かっている原告の在庫商品の一覧表(甲45)の中には、本件在庫商品は含まれていない。 (イ) 同年6月4日ころ、韓国本社の監査室長Dと、総務部長Eが来日し、Bとともに本件在庫商品の処理の件が話し合われ、非上場会社で新規の取引先と300万円以上の信用取引(売掛取引)をする場合には韓国本社の決裁が必要となるため、被告会社は、原告に対し、994万8951円のうち695万円を同月5日までに原告の口座に送金することとし、残額299万8951円を平成10年9月30日までに支払う旨の合意をした。 (ウ) 原告が、東京支店における従前の通常価格で、本件在庫商品を売却した場合の利益率は、別紙在庫商品売上予想額一覧の「利益率」欄記載のとおりであり、同利益率から本件在庫商品の通常価格での売上金額を算出する(帳簿額÷(1-利益率))と、同一覧の「売上予想額」欄記載の金額となり、その合計は1478万9477円となる(なお、甲13中の「WONIL-2」及び「人参茶(東一)3g×110TB/WB」の売上予想額は、用いる利益率ないし計算方法に誤りがある。)。 (エ) 被告Aは、原告から仕入れた本件在庫商品を、被告会社の商品として、原告における上記通常価格に近い金額で売却した。 イ 自己取引の場合は、単一人が双方の会社代表者として意思表示をするものであり、複数人の意思の合致はないのであるから、当該行為者の売買等の意思が客観的、外形的に明らかになった時点で契約が成立したものと解すべきところ、以上の事実関係によれば、本件在庫商品の売買が成立したのは、被告Aの売買の意思を客観的、外形的に明らかにする決議書が作成された平成10年5月28日であると解すべきである。 被告Aは、平成10年5月28日付けの決議書は、内部文書にすぎないから、同決議書の日付を基に売買の日付を判断すべきではないと主張するが、同文書がたとえ内部文書であったとしても、本件在庫商品を売上として計上するとともに、その代金相当額を売掛金と計上するという、まさに同日に売買契約が成立したことを前提とする会計処理に関する決議書であって、被告Aが本件在庫商品を原告から被告会社に売却する意思が客観的、外形的に示されていることは明らかである。 また、大曽根商店に保管してあった本件在庫商品がいつ搬出されたかは必ずしも明らかではないが、大曽根商店は、少なくとも被告Aが原告の代表取締役の職にある平成10年5月29日中に、被告Aの依頼により被告会社の在庫として区別して保管し、少なくともその時点で被告会社が引渡しを受けたというべきであり、こうした保管態様も、上記5月28日に成立した売買契約に基づく事情として理解できる。 ウ そうすると、本件在庫商品の売買は、被告Aが、原告及び被告会社双方の代表取締役として行ったもので、原告の取締役会の承認を要するところ(商法265条1項)、同承認がなされたことを認めるに足りる証拠はない。 エ なお、商法265条が取締役と会社間の取引につき取締役会の承認を要する旨を定めている趣旨は、取締役がその地位を利用して会社と取引をし、自己又は第三者の利益をはかり、会社ひいては株主に不測の損害を蒙らせることを防止することにあると解されるから、株主全員の合意がある場合には、別に取締役会の承認を要しないというべきである。そこで、同年5月28日当時の原告の全株式を有していた韓国本社の承認があった否かについて検討する。 上記のとおり、同年6月4日に、韓国本社の監査室長Dと、総務部長Eが来日し、Bとともに本件在庫商品の処理の件が話し合われ、被告会社が、本件在庫商品の帳簿価格994万8951円のうち299万8951円を残し、695万円を6月5日までに支払うとの支払方法の合意がされている。しかし、それは、被告会社と新規に300万円以上の売掛取引を始める場合には韓国本社の決裁が必要となるため、売掛金残額を300万円未満にするための合意であって、その際、本件在庫商品の処分行為を行った被告Aの責任について何らかの協議がされたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 さらに、本社清算人報告においても「商品処分代金回収については、Aの主張どおり監査室長と総務部長が口頭合意したことを確認する。」とあるものの、その一方で「協議結果①在庫商品無断搬出 売却残金および売上利益の速やかな入金要求」とされ、本社清算人報告の見解は、韓国本社が上記6月4日の時点で本件在庫商品の処分行為に係る被告Aの責任をも含めて合意したとの結論は出していない。 また、韓国本社の監査室長Dと、総務部長Eとに、被告Aの本件在庫商品の処分行為の責任についての決裁権限があったことを認めるに足りる証拠もない。 なお、被告A作成の陳述書(乙1、3、4、6)、監査室長D作成の確認書(乙2の1・2)、証人Fの証言、被告A本人尋問の結果中には、上記6月4日の時点で本件在庫商品の売買に関する事後処理を協議したが、その協議内容は、被告Aが協議された支払方法に従って同売買代金を支払えばすべての事後処理を終了するという趣旨のものであった旨の記載、供述部分があるが、いずれも原告の取締役会の承認に代わり得る韓国本社の合意を認めるに足りるものではない。 したがって、6月4日の時点で本件在庫商品に関する事後処理が協議され一定の結論が出されたものと思われるが、この時点で韓国本社が、本件在庫商品の処分行為を行った被告Aの責任を問わないことを前提とする承認を与えたとの事実は認められない。 オ そうすると、被告Aは、商法266条1項4号に基づき、原告が被った損害について賠償責任を負うというべきである。 そして、本件在庫商品の売却によって原告が得られたであろう粗利益は、原告が東京支店における従前の通常価格で売却した場合の売上合計額1478万9477円から、被告Aが定めた売買代金額994万8951円を控除した484万0526円となり、原告が被った損害賠償額は、同粗利益から、本件在庫商品の売却に必要と思われる経費として、広告宣伝費、通信費、運賃、見本費を控除した額とするのが相当である。 乙16の2によれば、原告東京本社の平成9年度における上記費用は、 広告宣伝費が55万円、通信費が269万3086円、運賃が183万7899円、見本費が80万6527円(合計588万7512円)、売上高は、4億7891万2520円であることが認められ、上記経費の合計額の売上高に占める割合は1.2%となる。 本件在庫商品の売上合計額1478万9477円の1.2%は、17万7473円となるから、上記粗利益から同金額を控除して原告の被った損害の相当額を求めると、466万3053円となる。 被告Aは、当時韓国通貨ウォンが暴落しており、新規に仕入れた方が売買代金価格より安く本件在庫商品を入手できた、本件在庫商品は東京圏における規格商品的なもので、大阪ではすぐに買手がつかないものであるから、原告が主張するような通常価格で売却できた可能性はないと主張するが、上記のとおり、設立したばかりの被告会社が原告の従前の通常価格に近い価格で売却している以上、従前から取引をしていた原告が同価格で売却することができなかったとは考えにくく、 その他に被告Aの同主張を裏付ける証拠がない以上、被告Aの同主張を採用することはできない。 なお、原告は、被告Aの損害賠償債務について商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を請求するが、原告と被告会社間の本件在庫商品の売買契約が商行為に当たるとしても、被告Aの負うべき損害賠償債務は、Aの商法265条1項に違反した行為により生じたものであって、同売買契約によって生じた債務には当たらないというべきであるから、被告Aの負うべき損害賠償債務について商事法定利率(商法514条)は適用されない。また、被告Aの上記損害賠償債務は期限の定めのない債務であるから、これに対する遅延損害金は、被告Aに対する訴状送達の日の翌日である平成11年1月24日を起算日とすべきである。 (2) 相殺について ア 被告Aが、原告に対し、16万5788円の未払報酬請求権(平成10年8月26日から31日までの報酬)及び15万円の不当利得返還請求権を有していることは当事者間に争いがない。 イ 被告Aが、原告に対し、平成12年2月3日の本件弁論準備手続期日において、上記合計金31万5788円の債権をもって、原告の被告Aに対する上記損害賠償債権とその対当額において相殺する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著である。 ウ 以上によれば、被告Aの相殺の主張は理由がある。 (3) そうすると、原告の被告Aに対する商法265条1項違反を理由とする請求は、434万7265円及びこれに対する平成11年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 4 よって、主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 小松一雄 |
|---|---|
| 裁判官 | 阿多麻子 |
| 裁判官 | 前田郁勝 |