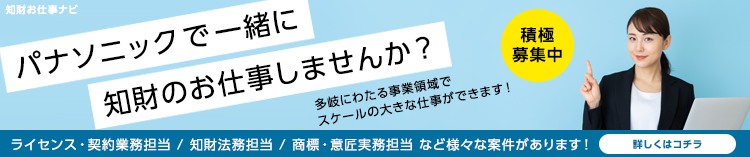| 関連ワード | 周知性 / 他人の営業 / 類似性(類似) / 呼称 / 混同のおそれ(混同) / 表示の使用 / 自己の氏名 / 誤認混同 / 差止請求(差止) / 営業上の利益 / ライセンス / 侵害 / 混同のおそれ(混同) / プログラム / 品質等誤認表示(誤認) / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
5年
(ワ)
1278号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1995/09/28 |
| 権利種別 | 不正競争 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求の趣旨
一 被告は、芸名として「音羽」なる名称を称し、また、自らの主宰する舞踊会に「音羽流」なる名称を冠し、右両名称を表札、看板、印刷物、書面に表示する等して使用してはならない。 二 訴訟費用は被告の負担とする。 三 仮執行の宣言 |
|
|
事案の概要
一 原告の活動 Aは、昭和九年、六代目Bの命を受けて家元として日本舞踊音羽流を創設し、芸名をCと称していた。同人が昭和四二年二月九日に死亡すると、その妻であるDが、二代目Cを襲名して音羽流の二代目家元となった(争いがない。以下、Aを「初代C」といい、Dを「二代目C」という。)。 原告は、初代Cの甥であるが、昭和四八年、三代目Cを襲名して音羽流の三代目家元となり、「音羽流」「音羽」の表示を使用して、日本古来の日本舞踊の研鑽と振興のために舞踊会を催し、同流の門弟を指導し、教授者を養成し、もって音羽流の日本舞踊を広める等の活動をしている(甲第六ないし第一〇号証、第二一、第二二号証、原告本人)。 二 被告の行為1 被告は、初代Cに師事し、名取として「E」と称していたが、昭和六一年五月頃、原告を家元とする音羽流を退流した(争いがない。)。 2 被告は、右退流後も「E」と称し、昭和六二年頃から、「清派音羽流」の表示を使用して、弟子を募集し、発表会を催すなどの舞踊活動をしている(争いがない。)。 3 被告は、平成五年一二月初め、歌舞伎の音羽屋一門の当主である七代目F(以下「F」という。)から、「證 E 右の者に日本舞踊流派音羽流(清派)の創流を音羽流宗家として許可します」との書付け(以下「本件書付け」という。)を授与された(乙第一二号証、被告本人)。 三 原告の請求 「音羽流」「音羽」の表示は原告の営業であることを示す表示として周知性を獲得しているところ、 被告が使用している「清派音羽流」「音羽」の表示は「音羽流」「音羽」の表示と同一又は類似するものであり、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の営業上の利益を害されるおそれがあると主張して、不正競争防止法2条1項1号、 3条に基づき、被告が芸名として「音羽」なる名称を称し、また、自らの主宰する舞踊会に「音羽流」なる名称を冠し、右両名称を表札、看板、印刷物、書面に表示する等して使用することの停止を請求。 四 争点1 「音羽流」「音羽」の表示は、原告の営業であることを示す表示として周知性を獲得しているか。 2 被告の「清派音羽流」「音羽」の表示は、「音羽流」「音羽」の表示と類似し、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の営業上の利益が害されるおそれがあるか。 3 被告の「清派音羽流」「音羽」の表示の使用について、不正競争防止法11条1項2号の自己氏名の善意使用に該当する等、違法性阻却事由があるか。 |
|
|
争点に関する当事者の主張
一 争点1(「音羽流」「音羽」の表示は、原告の営業であることを示す表示として周知性を獲得しているか)【原告の主張】1 原告は、音羽流の三代目家元として、次のような日本舞踊の営業活動を行っている。 (一)自ら舞踊会、講習会に出演し、出演料等の対価を得る舞踊活動(二)門弟を指導し、授業料等の対価を得る教育活動(三)門弟に対し、一定水準以上の者について一定の試験を経て初段から五段までの段位を認め、より水準の高い者には名取として「音羽」の姓を冠した芸名を称することを許し、更に水準の高い者には教授として自らの門弟に音羽流独自の舞踊を「音羽流」の名称を使用して指導する権限を与え、受験料、昇段料、名取料等の対価を得る活動。 これらの活動について、原告は、各事業年度ごとに事業計画を立て、これを具体的に実現するための予算を組み、当該年度の支出はこの予算に従って行い、支出の結果については毎会計年度ごとに決算をし、支出の適否を検討している。 したがって、原告が、家元として行っているこれらの活動は、文化・芸術活動というべき側面はあるが、一面では、これらの活動を維持・継続するため、経済上の収支計算の上に立って行われている事業活動でもあるから、不正競争防止法2条1項1号所定の「営業」に該当する。 2(一)「音羽流」が原告の営業表示であることは、1記載の事実から明らかである。 (二)また、各名取の称する「音羽」の姓を冠した名取名も、営業表示である。 (1)すなわち、わが国における家元制度においては、流派の名取は家元の統制権によりすべて同一の姓を称しており、それを名乗るためには家元の許可が不可欠である事実を前提にすれば、「音羽」の姓を必ず称していることによって原告の前記営業を表示しているといえるのである。 (2)仮に、「音羽」の表示は営業表示それ自体ではないとしても、原告が事業活動の実施・遂行のために他人にライセンスしてきた表示ないし名称とみるならば、 不正競争防止法2条1項1号にいう「他人の営業を表示するもの」はその趣旨からしてその「他人」の営業表示のみならずライセンスに供する表示をも含むものであると解することにより、同じ結論となる。 (3)更に、この「他人」を、音羽流の主宰者である原告に限定することなく、例えばフランチャイザーとフランチャイジーのように、冒用者以外のすべての正当な表示の使用者ないし一群の使用者グループ(本件の場合は音羽流一門)と解釈することも可能である。 3 「音羽流」「音羽」の表示が現在周知性を獲得していることは明らかである。 (一)「音羽流」「音羽」の表示は、以下のとおり初代Cの時代に周知性を獲得しており、これが二代目C、原告と承継されている。 (1)音羽流は、昭和九年に初代Cにより創流されたものであるが、初代Cが高名な六代目Bの弟子であったため、創流当初から音羽流、Cの名前は日本舞踊界を中心にして世間一般に広く知れ渡り、この時点で既に「音羽流」「音羽」の表示は関西の日本舞踊界において周知性を獲得した。 (2)初代Cは、戦争中は目立った活動ができなかったが、昭和二〇年代後半、当時関西唯一の日本舞踊の組織として関西邦舞協会が組織化され、その役員となった。 この時点で、「音羽流」「音羽」の表示は、関西の日本舞踊家を中心として広く一般の人に知れ渡るようになった。 (3)初代Cは、昭和三五年、音羽流家元として、伝統ある日本の著名な流派のほとんどがその構成員となっている全国規模の組織である社団法人日本舞踊協会(関西邦舞協会もこれに発展的に吸収された。)に加盟し、この時点で、「音羽流」「音羽」の表示は、広く一般の人に知れ渡るようになった。 (二)仮に右(一)の事実が認められないとしても、「音羽流」「音羽」の表示は、原告が三代目Cの襲名披露をした昭和四八年一〇月二八日には、日本舞踊界において周知性を獲得したことは疑いがない。 すなわち、原告が昭和四八年音羽流家元三代目Cを襲名した際、その有名な音羽流の三代目家元が決定したということで日本舞踊界の注目を集め、原告側でも案内状を各方面に出して三代目襲名を通知した。また、各芸能新聞も原告の三代目襲名の事実を大きく取り上げて報道した。更に、襲名披露は大阪の新歌舞伎座で行われ、F以下著名人が多数出演する盛大なものであった(甲第八ないし第一四号証)。 以後原告は、日本はもとより、海外においても幅広く日本舞踊活動を行っている。現在、原告を家元とする音羽流は、全国各地に約二五〇〇名の門弟を擁しており、そのうち自らの門弟に指導する資格を有する名取教授は約五〇〇名、一定の技能は習得しているが指導はできない単なる名取は約二五〇名である。 4(被告の主張について)(一)被告は、原告が二代目Cが健在であるのに無断で三代目Cを名乗った旨、あるいは二代目Cと原告との間には断絶がある旨主張するが、二代目Cと原告との間で、音羽流を主宰する家元の地位を譲渡する旨の合意がなされており、音羽流の構成員もこれに賛同したため、断絶は存在しない。 原告は幼少の頃から初代C、二代目C夫婦に引き取られて実の子供同然にして育てられたものである。このような環境にあった原告が三代目Cを承継したことは、 いわば当然の成り行きであり、二代目CことDも、喜んで音羽流家元の地位を原告に承継させたのである(甲第七号証)。 (二)被告はまた、原告は初代Cの独特の舞踊である「振り」と「手」を承継していない旨主張するが、原告は、初代C死亡後、同人の同じ六代目B門下の兄弟弟子であったGに約四年間指導を受け、さらに、ある踊りについては二代目Cからも指導を受けているし、古参の者たちと一緒に踊りの会を催す等して勉強を続けているのであり、当然に、初代Cの音羽流の踊りを承継し、高度の舞踊技術を修得している。しかし、そもそも、司法権には日本舞踊団体における踊りの技術の判断権限はないのであるから、本件訴訟では、原告の踊りがどのようなものであるかは全く問題とならない。 【被告の主張】1 原告は、後には体裁を整えたが、当初は二代目Cが健在であるのに無断で三代目Cを名乗ったものである。 したがって、二代目Cと原告との間には断絶があり、舞踊そのものも、初代Cの独特の舞踊である「振り」と「手」を継承しているのは二代目Cまでであり、原告は、音羽流を名乗っているとはいえ、その間には法的同一性はなく、新たな流派を創流したものとみるのが相当である。 2 「音羽」流の名跡は、原告に固有のものではなく、「音羽」を屋号とする尾上家にその淵源を有しており、「音羽」の名跡は「宗家」を筆頭に形成されているヒエラルキーにおける一門全体の呼称である。 (一)原告は、歌舞伎の音羽屋を宗家としている。 「音羽屋」の名称は、広辞苑第四版三七一頁にも「歌舞伎俳優Bとその一門の屋号」と解説されているとおり、周知のものである。 「宗家」とは、「伝統的芸能の世界で、流派の開祖、最高責任者である家元の別称。または家元を統括する家」(講談社「日本語大辞典」)という意味を有する。 (二)歌舞伎は、「近世の初めに流行した踊りに始まる、日本の代表的演劇」(前同書)であり、踊りとは切り離せない関係にある。このように歌舞伎の中で演じられた舞踊や歌舞伎から発した「歌舞伎舞踊」は、日本舞踊の主流をなす一形態であるといわれる(前同書)。現在でも、歌舞伎の公演では、芝居だけでなく、日本舞踊もその演物として必ず取り上げられている。 六代目Bは近代歌舞伎を代表する名優であり、舞踊にもすぐれており、日本俳優学校も創立している(前同書)。このように芸の発展に意欲的であった六代目Bが「音羽屋」の踊りを発展継承させるために、弟子のうちからHを選び、流派名を「音羽流」と名付けて舞踊に専念させたのが、初代Cなのである。 したがって、初代Cの「音羽流」舞踊は、まさしく音羽屋を宗家として成り立っているのである。 現に、原告の三代目C襲名披露の際などには、原告自身、六代目Bの没後に尾上家を継いだF(やはり舞踊にすぐれていることが前同書に記載されている。)を特に招いて出演してもらっているのである。 二 争点2(被告の「清派音羽流」「音羽」の表示は「音羽流」「音羽」の表示と類似し、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の営業上の利益が害されるおそれがあるか)【原告の主張】1 被告の「清派音羽流」「音羽」の表示が原告の営業表示である「音羽流」「音羽」と同一であるか全体としてきわめて類似していることは明らかである。 2 原告と被告は、日本舞踊活動という同種の営業をしており、地域的にも、大阪を中心として活動している点で重なっている。 被告の「清派音羽流」の表示は、原告の「音羽流」の表示ときわめて近似しており、被告が原告を家元とする音羽流一門に属する者であるか、又はその正当な分家等、原告との間に業務上、組織上何らかの特殊な関係があるかのように誤認されるおそれがある。原告らの音羽流においては、教授となった場合に、自分の弟子を指導する会に自己の名前を冠して「音羽流貴水会」「音羽流鶴寿会」などといった名称を付するのが通常であり、一般人にはこれら原告の事業の一環として使用されている表示と被告の「清派音羽流」の表示とは区別がつかない。「清派」と表示することによって、より一層原告の音羽流と関連がある一派であるとの意味が強まる。 被告の具体的な表示の使用方法をみても、例えば甲第五号証の入場券の表示においては、「音羽流」の表示が大きく前面に出され、その後に括弧書きで小さく付随的に「(清派)」と記載されているのである。一般人がこの表示を見て、原告の主宰する音羽流の舞踊活動の一環としてされているものと誤認することはあまりにも当然のことである。 また、被告が「音羽」の芸名を冠していれば、原告の主宰する音羽流の一員、関係者であると誤解されるおそれは強い。現に、そのように誤解していた者が多数存在する。 なお、誤認混同を生じる表示の使用差止請求権の要件として、不正競争の意図は不要である。 3 右のように誤認混同が生じる結果、原告が新弟子を失い収益を減少させる等、 営業上の利益を害されるおそれがあることは明白である。そればかりか、被告の行う正当でない音羽流の日本舞踊が流布される結果、原告の事業に対し、誤解された評価が与えられる危険性もあり、原告の存立自体にも影響を及ぼしかねない。 4 (被告の主張について)(一)被告は、被告の活動は「営業」に該当しない旨主張するが、被告は、自らの主宰する「清派音羽流」の活動において、門弟を指導する際月謝を取得し、免状を交付する際も一〇万円、五〇万円といった額の金員を受領しているから、それが営業活動であることは明らかである。芸術活動としての目的の有無は何ら関係がない。 (二)被告は、藤間流の例を挙げるが、他の流派の事情がどうであれ、音羽流では分派等は一切認められず、原告も一切承認したことはない。他の流派が分派を認めているか否かは本件とは無関係である。 【被告の主張】1 被告の活動は「営業」に該当しない。 すなわち、被告は、六歳の頃から初代Cの指導を受け、原告が三代目Cを名乗る前から「E」を名乗っており、「音羽流」については、「営業」としてではなく、 六代目Bに源を発し、初代Cが作り上げた日本舞踊の一つの形式を完成させた芸能の流れとして認識している。 被告は、右のような芸術活動としての音羽流の舞踊の継承を目的としているのみであり、原告のいうような家元制度のもとでの「営業活動」を行っているものではない。被告が名取料などとして弟子から徴収する金員は実費かこれに毛が生えた程度のものであり、「営業」行為性はないといってもよいくらいであり、少なくともかなり希薄であるといえる。これは、六代目Bから音羽屋の日本舞踊を継承発展させることを命じられた弟子のHが初代Cを名乗って創流したことを大切に思う被告が、音羽の舞踊の「手」と「振り」を後世に継承することのみを願っていることの反映である。原告は踊りをもっぱら「営業」とみているかもしれないが、それは被告のとらえ方とは異なっており、同列の営業行為というのは当たらない。 2 被告の活動が原告の活動との間で混同を生じることはなく、原告の営業上の利益を害するおそれはない。 (一)被告の舞踊活動は、大阪とはいえ、南部の河内長野市が中心である。これは、被告の居住地であり、稽古場も自宅としていることによるのであり、創流(乙第二号証)も、その後開いた勉強会(甲第三号証)や舞踊会(甲第五号証)などもいずれも河内長野市内において行っている。原告の「営業」は大阪市内を中心としているのであり、被告の右舞踊活動とは実質的にはほとんど地域的な重なりはない。 (二)また、被告は、原告の「営業」としての音羽流との混同を生じないように、 その舞踊活動の表示を自らの芸名の一字をとって「清派 音羽流」としているのであって、不正競争の意図は微塵もなく、舞踊会では同一流派から派生した流派について、同じ流れを組みつつも、流派としては別派であることを表象する文字を付加して流派名としている場合が多くみられるところである(乙第一一号証の藤間流の例)から、混同は生じていない。 (三)現実にも、被告は、原告に弟子を取られたことはあっても取ったことはなく、原告の音羽流とは競合関係にない。 三 争点3(被告の「清派音羽流」「音羽」の表示の使用について、不正競争防止法11条1項2号の自己氏名の善意使用に該当する等、違法性阻却事由があるか)【被告の主張】1 被告は「音羽」の名跡については原告が使用する前から使用しているものであり、また、被告にとって「E」は自己の氏名に相当するから、不正競争防止法11条1項2号にいう自己氏名の善意使用に該当するというべきである。 前記のとおり、被告は、六歳の頃から初代Cの指導を受け、原告が三代目Cを名乗る前から「E」を名乗っている。 被告は、初代Cから手ほどきを受けてこれこそ音羽流というその独特の「振り」と「手」を継承しているのであり、これに対し、原告は、初代C、二代目Cから手ほどきを受けておらず、現にその踊りは本来の音羽流とは離れているから、そのような原告よりも被告の方が正統な音羽流の継承者である。したがって、被告が新流派を創るときに音羽流の流れを組んでいることを標榜することは何ら異とするに足りず、むしろ「音羽」を名乗らない方が不自然である。 2 原告は、原告が三代目Cを襲名した後は原告が被告に対し名取名「E」を貸与した旨主張するが、被告は原告からその使用を認められたものではない。被告は、 原告が初代Cの芸の継承発展より「事業」ばかりを追求している態度を潔しとしない思いがあったので、原告のもとにある音羽流とは一線を画してきたが(自己の弟子について師範・名取の資格を原告から取得したり、認定料を支払ったりするという関係は一切なかった。)、形式上は原告のもとにある音羽流に籍だけが残っていることになるため、昭和六一年五月頃原告に対してその籍を抹消してほしいと申し出たにすぎない。 原告は、被告が音羽流を退流する際、原告に対し、「E」の名称を原告に返還し、以後自らの弟子を指導する際や発表会等でも「音羽流」「音羽」の名称は使用せず、弟子にも右名称を使用させない旨確約した旨主張するが、被告は「E」の名称を返上したことはないし、以後「音羽流」の名称を使用することを一切控えるというまでの約束をしたことはない。「E」は被告自身の名であり、これを返還するということはありえない。 甲第四号証(テープの反訳文)のどこからも、法的な意味をもつような名称不使用の合意がされたと認めることはできない。 3 仮に被告が原告を家元とする音羽流から退流したときに「音羽流」の使用を控えることとしたものであるとしても、被告は、平成五年一二月初め「音羽流」「音羽」の名称の淵源である宗家音羽屋の当主であるFから本件書付けを授与され、新たに「音羽」の名跡を名乗ることを許されたものであるから、新たに宗家から許諾を得た「音羽流」「音羽」の名跡の使用について原告から制約を加えられるいわれはない。 (一)そもそも「音羽」というのは、初代Cに由来しているのではなく(まして三代目Cである原告に由来するものではなく)、初代Cが師匠であった歌舞伎俳優六代目Bからその屋号「音羽屋」を使用することを許された流派名であることは一【被告の主張】2記載のとおりである。 したがって、「音羽屋」の当主は、家元より上位の「宗家」としての地位を有しているのである。 (二)被告は、本件紛争が生じてから、思い余って、六代目Bの跡を継いで音羽屋の当主としての地位にあるかねて昵懇のFを訪ねて相談したところ、同人も、音羽流の「宗家」としての立場で、かねがね音羽流三代目家元である原告の踊りが初代Cの伝えた音羽流の舞踊とは全く異なったものであり、このままでは音羽流の舞踊が正しく継承されないことを憂慮しており、また初代Cの弟子に対する原告の強引で排他的な扱いについて心を痛めている旨話し、改めて、初代Cの直接の愛弟子で同人が築いた音羽流の舞踊を正統に継承している被告(一時は初代Cが養子として跡を継がせたいと考えていたこともある。)に対し、音羽流舞踊を後世に伝えるため「音羽」を名乗って舞踊活動を続けることを許し本件書付けを授与したのである。 もともと「音羽流」は、初代Cが創流したとはいえ、歌舞伎の尾上家を宗家とし、その流派名も尾上家の屋号「音羽屋」を頂戴したというものである以上、別途音羽屋の総帥であるFから「音羽」の名跡をとって「清派音羽流」を名乗ることを許された被告が、混同を避ける配慮をしたうえで「音羽流」の名跡を使用することは不正な競争には該当せず、原告がこれを妨害する根拠はない。 また、Fの屋号が「音羽屋」である以上、必ずしも原告の音羽流の宗家が音羽屋であるか否かは関係がなく、音羽屋の総帥であるFが、原告との混同を避けて「清派音羽流」として被告に自らの屋号の「音羽」の名称を許すことができることは当然であり、原告が容喙すべきところではない。 したがって、現在の被告の「清派音羽流」はまさしく被告自身の名である。 (三)原告が歌舞伎の音羽屋を宗家としていること、音羽屋の名称が周知のものであることは一【被告の主張】2記載のとおりであり、原告が音羽屋(尾上家)との関係を否定するとすれば、原告が「音羽」の名称を名乗ること自体が、他人の名声に便乗した営業活動をしていることになり、不正競争行為を構成することになるのである。 原告が本件訴訟において伝統芸能の世界における世襲的な伝承制度としての「家元制度」を根拠にしている以上、原告が音羽屋を宗家とする関係にあることを否定することはできず、原告の名跡は自立したものではなく、歌舞伎界の「音羽」屋の周知性に依存しているのであるから、原告より上位にある宗家が被告に対して「音羽」の名称の使用を許諾したことについて、原告にこれを覆す権限はない。 原告の音羽流においても明確な債権債務関係を規律する規約などは存在せず、原告の主張も事実として家元制度として行われているところを法的保護の対象として構成しているだけであり、その意味では古典芸能の世界における事実としての「宗家」との関係も等しく服するべき規範であることを否定することはできない。 (四)原告が宗家と家元の関係について種々主張しているところは、天に唾するものといわなければならない。 原告が問題としている「音羽」の名跡が歌舞伎の音羽屋にあることは原告も争えない事実であり、原告が「音羽流」を名乗ることが正当化されるのは、六代目Bの許しを得たからにほかならない。原告は本来なら名義使用料を支払うべき立場であるのに、対価を支払っていないなどといい、尽くすべき礼儀を尽くさずこれを無視していることを捉えて、宗家は法律上の地位ではないなどというのは、原告が非礼な態度を取っていることを自白しているにすぎない。 近代法の発想からいえば、宗家としてこれらの請求をしても何ら不思議はないのであるが、もともと家元でも宗家でも近代法の成立以前の世界のものであり、そもそも権利義務を大前提とした法律的な世界ではない。したがって、宗家としても、 家元から対価を持ってくれば受け取るが、持ってこないからといって請求するというようなことはしないものである。 このような世界に近代取引社会と同じ法的保護を求めるのがそもそも少々無理があるのであり、それをあえて不正競争として保護を求め、裁判所もこれを保護することがあるのは、その「競争行為」が不法性を帯びる場合についてまさしく不法行為としてこれをとらえているからにほかならない。 本件における不正競争防止法との関わりでは、宗家と家元との関係は主たる法律問題ではなく、原告より高次の立場から被告が「音羽」の名跡を許されたということを被告は主張しているのであって、それ以上でもそれ以下でもない。 【原告の主張】1 被告は、初代Cから名取名として「E」の貸与、使用許諾を受けたものであり、舞踊活動を離れた日常活動では、I又はJという名称を使用していたから、 「E」は被告が舞踊活動をする際に自己の事業を表示する名称であることは明らかであり、被告の「自己の氏名」には該当しない。 2 被告は、右のとおり初代Cから名取名「E」を貸与されていたが、原告が三代目Cを襲名した後は、原告が、被告に対し名取名「E」を貸与し、「音羽流」の名称を使用して日本舞踊の指導・普及活動の事業を行うことを認めることとなった。 被告は、昭和六一年五月頃、大阪市<以下略>内の音羽流舞踊教室家元稽古場において、原告に対し、病気を理由に自らの意思で音羽流からの退流を申し入れ、原告はこれを了承したが、その際、被告は、原告に対し、「E」の名称を原告に返還し、以後自らの弟子を指導する際や発表会等でも「音羽流」「音羽」の名称は使用せず、「J」の名前で細々と舞踊活動を続け、弟子にも「音羽流」「音羽」の名称を使用させない旨確約した。原告は、被告が舞踊活動を続ける際に「音羽流」「音羽」の名称を使用することを懸念し、被告にそのようなことがないことを確認したうえで、被告の退流の申出を承認したのである。その際のやりとりは、稽古場で音楽を流すために用意されていた録音装置によって録音されたテープの反訳文(甲第四号証)により明らかであり、被告は原告から「E」の名称の貸与を受けていることを前提に、原告に対し、右名称を返すことを確約している。 3 被告がFから本件書付けを授与されたことは、被告が、「音羽流」「音羽」の表示を使用することを正当化する根拠とならない。日本舞踊における「音羽流」「音羽」の名称の使用権、使用許諾権は、全面的に初代Cに帰属し、現在はその継承者の原告に帰属している。それは、①「宗家」の地位が不明であること、②原告とFとの間には契約関係は存在せず、音羽流においてFの地位は事実上尊重されるものにすぎないこと、③「音羽流」「音羽」の表示の使用は自己氏名の使用に該当しないことから明らかである。 (一)そもそも、被告主張の根拠とする「宗家」の地位が不明である。被告の主張は、被告が原告(家元)より上位にある「宗家」の当主であるFから「音羽流」「音羽」の名称の使用を許諾された以上、原告にこれを覆す権限はないというだけであり、宗家の地位が法律上のものか事実上のものかという点や、宗家と家元・一門とはどのような関係にあるのか、法律的になぜ、家元が宗家に従う義務があるのかを全く明らかにしていない。 日本舞踊の家元という地位は、どの流派でも基本的部分は共通しており、各名取との契約関係も様々な儀式、指導、対価支払等があり、過去の裁判例でもある程度明確にされている。 これに対し、宗家の地位の内容は一義的でない。流派によっては、原告の家元のような地位のことを「宗家」と称していることもあり、宗家が存在しない流派もある。どのような権限があるのか、あるいは単なる象徴であるのかについては疑問があるにもかかわらず、被告は、Fの地位、同人と原告及び被告との関係を明らかにしていない。 (二)原告とFとの間には契約関係は存在せず、Fの地位は事実上尊重されるものにすぎない。 初代C、二代目C及び原告と、六代目B及びFとの間の関係は、前者が後者を尊敬し重んじるという関係にはあるが、それは事実上の象徴的な地位にすぎず、例えばフランチャイジーとフランチャイザーというような法律的な契約関係は全く存在しない。 また、家元やその一門が宗家や宗家筋の指示に絶対服従しなければならないという慣習法や事実たる慣習も存在しない。Fが「音羽流」「音羽」の名称の付与に関与していた場合に原告がその結果に異議を述べないとか、差止請求権を行使しないというような合意をしたこともない。 Fが、自分が宗家や家元となって、日本舞踊の流派を創設すること自体は全くの自由であり、原告の関知するところではない。しかし、その流派の名称が原告の流派と類似している場合には、原告にそれを差し止める権利が発生することは当然である。被告が原告の営業と誤認混同を招来する名称を使用するのを原告が甘受しなければならない義務は存在しないのである。 音羽流の家元の地位にあった初代C、二代目C及び原告と、「宗家」たる六代目B及びFとの関係が事実上のものであったことは、以下の点からみて明らかである。 (1)原告を家元に指名したのは宗家ではなく、宗家は家元の選定手続には何ら関与しておらず、何らかの許可手続がされたわけでもない。原告の挨拶文に「F様のお許を得まして 三代目Cを襲名致すはこびと相成りました」(甲第八号証)と記載されていても、それは形式上の権威づけのためであり、実際に、許可、認証のような儀式、意思表示がされたわけではない。 (2)宗家から家元にその地位を認める免状や書き札が渡されたことはない。 逆に、家元から宗家に対し、家元の地位取得の対価、宗家としての活動の対価、 その他金銭が支払われたという事実もない。 (3)家元と宗家との間で、以後の継続的な舞踊指導関係、営業関係を確認するための契約はもちろん、その合意の成立を確認する盃事のような儀式も一切行われていない。 (4)宗家は家元及びその一門に対して、舞踊指導は全く行わない。 (5)宗家は、歌舞伎が専門であり、音羽流の舞踊の型を習得しているわけではないし、日常的に日本舞踊の普及活動をしているわけでもない。 (6)家元は、宗家に対して、自己の門弟の構成内容、舞踊活動内容その他も一切報告せず、宗家もその活動内容について全く関知しない。 (7)宗家は、家元による名取の取立てに全く関与しない。 (8)宗家が音羽流の舞踊会に特別出演する場合には、その都度個別的に正当な額の出演料が支払われている。 (9)宗家は、人事・運営方法・経理・会の開催・その他いかなる事項についても、音羽流の活動に命令・指示・介入をした事実は一切存しない。 (10)家元・一門から宗家に対して行う行為としては、宗家の関西での公演の際の切符手配と楽屋への挨拶のみである。このような行動は、契約関係に基づくものではなく、何かの対価として行われているものでもない。また、強制的・義務的なものでもない。単に、高名な人物であり初代Cゆかりの人物ということで、尊重しているだけである。 (11)宗家から家元、一門に対して、破門、戒告その他何らかの制裁処分が行われたことは一度もなく、そのような処分制度も存在しない。 (三)「音羽流」「音羽」の表示の使用は不正競争防止法11条1項2号にいう自己氏名の使用に該当しない。 (1)Fは、自分自身の氏、略称、雅号、芸名、筆名として「音羽流」「音羽」の名称を使用したことは一度もない。世間一般においても、「音羽流」「音羽」の名称が、同人を示す名称として認識されたことはない。 不正競争防止法11条1項2号が自己氏名についてはやむを得ないものとしてその使用を認めた趣旨からして、「音羽流」「音羽」の名称が、原告の営業上の利益を侵害してまで使用を認めなければならないようなFの自己氏名でないことは明白である。 (2)また、芸名が同条同項同号にいう自己氏名に該当する場合があるとしても、 本件における被告の「E」という芸名の使用は自己氏名の使用には当たらない。 「E」という芸名は、原告が引き継いだ初代C主宰の音羽流において、被告が貸与された芸名である。日本舞踊界において、名取名は、その流派にとどまっている場合においてのみ使用を許され、その流派から離脱した場合にはこれを返還しなければならないものであることについては、争いがないはずである。 (3)仮に「音羽流」「音羽」の表示が何らかの意味で自己氏名に該当するとしても、他人の営業と誤認混同させるような使用をして、他人の営業上の利益を害することは許されない。 Fは、自らは日本舞踊の普及活動をしておらず、被告の利益のために名称を使用させており、被告もその事実を知っていたのであるから、被告による右表示の使用は許されない。 |
|
|
争点に対する判断
一 争点1(「音羽流」「音羽」の表示は、原告の営業であることを示す表示として周知性を獲得しているか)1 「音羽流」「音羽」の表示の「営業表示」該当性について(一)証拠(甲第六、第二一、第二二号証、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、初代C、二代目C及び原告は、初代Cが六代目菊五郎の命を受けて創流した日本舞踊音羽流を統率する地位にある家元として、 ①自ら舞踊会、講習会に出演し、出演料等の対価を得る舞踊活動②門弟を指導し、授業料等の対価を得る教育活動③門弟に対し、一定水準以上の者について一定の試験を経て初段から五段までの段位を認め、より水準の高い者には名取として「音羽」の姓を冠した芸名を称することを許し、更に水準の高い者には教授として自らの門弟に音羽流独自の舞踊を「音羽流」の名称を使用して指導する権限を与え、受験料、昇段料、名取料等の対価を得る活動④古典舞踊を簡略化し、親しみやすくした「新舞踊」の活動(これは原告の代になって昭和六一年頃始めたものである。)を行ってきており、これらの活動について、各事業年度ごとに事業計画を立て、これを具体的に実現するための予算を組み、当該年度の支出はこの予算に従って行い、支出の結果については、毎会計年度ごとに決算をし、支出の適否を検討していることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。 不正競争防止法上の「営業」は、経済上の収支計算の上に立って行われる活動をいい、営利を目的とするか否かを問わないと解すべきところ、初代Cから原告に至る音羽流の家元が行っている右認定の活動は、文化・芸術活動というべき側面のあることはいうまでもないが、一面では、経済上の収支計算の上に立って行われている事業活動でもあるから、不正競争防止法2条1項1号所定の「営業」に該当する。その事業活動の主体は家元の地位にある者であり、家元の地位が承継されることにより事業活動も承継されるものと認められる。 (二)「音羽流」の表示は、原告の右の活動を表示するものであるから、同号所定の「営業表示」に該当することが明らかである。 (三)次に、原告の前記活動において各名取の称する「音羽」の表示が「営業表示」といえるかについて検討するに、証拠(甲第六、第二一、第二二号証、証人K、原告本人、被告本人)に弁論の全趣旨を総合すれば、音羽流の舞踊活動においては、家元は常に「C」を称すること、弟子を名取に取り立て、免状を授与し、名取名の使用を許すのは家元の専権に属すること、名取名はすべて「音羽」の姓を冠したものであり、名取に取り立てられた者は、以後自らの音羽流の舞踊活動を行うにつきこの「音羽」の姓を冠した名取名を表示し使用することが許されること、名取への取り立ての際には、「名字内」という盃事が行われるが、これは家の一員となるという意味合いがあることが認められ、そうすると、音羽流の名取名における「音羽」姓は、名取に取り立てられた個人の芸名としての性格を有するだけではなく、同時に、家元「C」によって代表される前記活動「音羽流」に属することを示すものであり、原告を家元とする音羽流一門の「営業表示」としての性格をも有するものというべきである。 2 「音羽流」「音羽」の表示の周知性について(一)証拠(甲第六ないし第二二号証、第二七号証、証人K、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1)初代Cは、戦争中は目立った活動ができなかったが、昭和二〇年代後半、当時関西唯一の日本舞踊の組織であった関西邦舞協会が組織化された時点で、音羽流家元としてその役員となった。 (2)初代Cは、昭和三五年、音羽流家元として、伝統ある日本の著名な流派のほとんどがその構成員となっている全国規模の組織である社団法人日本舞踊協会(関西邦舞協会もこれに発展的に吸収された。)に加盟した。 (3)原告は、昭和四八年、二代目Cから音羽流家元の地位を譲り受けて三代目Cを襲名したが、その際、原告側では挨拶状を各方面に出して三代目襲名を通知し、 各芸能新聞(中部芸能タイムズ、大阪芸能新聞、芸能プレス、婦人芸能新聞)も、 原告の三代目襲名の事実を大きく取り上げて報道した。また、原告は、同年一〇月二八日、大阪の新歌舞伎座において三代目C襲名披露舞踊会を催した。同襲名披露舞踊会には、Fや、日本舞踊西川流の家元G、尾上流の家元Lらが特別出演し、昼夜入替えで日本舞踊関係者をはじめ約三〇〇〇名の客が入った。 (4)以後原告は、主として関西地区を中心に全国で日本舞踊活動を行っており、 海外においても幅広く活動している。 現在、原告を家元とする音羽流は、全国各地に約三〇〇〇名の門弟を擁しており、そのうち、原告の直接の門弟(直門)が約一〇〇名、自らの門弟に指導する資格を有する名取教授が約五〇〇名、一定の技能は習得しているが指導はできない単なる名取が約一五〇〇名である。 また、原告は、音羽流家元として、前記社団法人日本舞踊協会に所属し、同協会関西支部の理事をしている。 (二)右認定事実によれば、「音羽流」「音羽」の表示は、初代Cが昭和三五年に全国規模の組織である社団法人日本舞踊協会に加盟した時点で、日本舞踊関係者の間で音羽流家元の地位にある者の営業表示として周知となり、家元の地位が初代Cから二代目Cを経て原告へと承継されるに伴い、それぞれの営業表示として承継されているものと認められる。 3 被告の主張について 被告は、原告は後には体裁を整えたが、当初は二代目Cが健在であるのに無断で三代目Cを名乗ったものであるとか、二代目Cと原告との間には断絶があると主張するが、右2(一)認定の事実に照らし採用することができない。 また、被告は、舞踊そのものも、初代Cの独特の舞踊である「振り」と「手」を継承しているのは二代目Cまでであり、原告は音羽流を名乗っているとはいえ、その間には法的同一性はなく、新たな流派を創流したものとみるのが相当であると主張するが、家元の地位の承継は当該流派の内部的手続に従ってされれば足りるというべきであり、その効力を舞踊の実質的内容にかからせる理由はないから、右主張は採用することができない。 二 争点2(被告の「清派音羽流」「音羽」の表示は「音羽流」「音羽」の表示と類似し、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の営業上の利益が害されるおそれがあるか)1 前記一認定のとおり日本舞踊関係者の間で「音羽流」の表示が周知性を獲得している以上、これらの者は被告の「清派音羽流」の表示のうち「音羽流」の部分に注目することが明らかであり、これがその要部である。そうすると、被告の「清派音羽流」の表示は、その要部が原告の「音羽流」の表示と同じであるから、これと類似するというべきである。 「音羽」の芸名は、原告の「音羽」の表示と同一である。 2(一)原告と被告は日本舞踊活動という同種の事業をしていることは明らかであるところ、原告は前記一2(一)(4)認定のとおり主として関西地区を中心に活動を行っており、被告は、昭和六二年三月頃、「清派音羽流」を名乗り、河内長野市の自宅及び堺市内に舞踊教室を開いて弟子に日本舞踊を教え、河内長野市内の会場を借りて舞踊会を催すなど、両市を中心に活動を行っている(甲第二、第三、第五、第六号証、乙第一、第二、第七、第一〇号証)から、その活動地域も競合するものである。 したがって、被告が「清派音羽流」の表示を使用すれば、これと原告の「音羽流」の表示との類似性から、被告が原告を家元とする音羽流一門に属する者であるか、又はその承継を受けた分家等、原告との間に業務上、組織上何らかの特殊な関係があるかのように誤認されるおそれがあり、また、被告が芸名として「音羽」を冠した名称を使用すれば、これが原告の「音羽」の表示と同一であることから、原告の主宰する音羽流の一員、関係者と誤認されるおそれがあるものというべきである(乙第一、第二号証も右認定を覆すに足りない。)。 (二)被告は、六代目Bに源を発し、初代Cが作り上げた日本舞踊の一つの形式を完成させた芸能の流れという芸術活動としての音羽流の舞踊の継承を目的としているのみであり、原告のいうような家元制度のもとでの「営業活動」を行っているものではない旨主張するが、証拠(甲第二、第二七号証、証人M、被告本人)によれば、被告においても、舞踊教室を開き、入門する弟子から入会金五〇〇〇円、月謝七〇〇〇円(その後一万円、ただし古参の弟子は二万円)を徴収し、名取や師範に取り立てる場合は名取料五万円、師範料二五万円ないし三〇万円を徴収していることが認められ、前記のとおり会場を借りて舞踊会を催したりもしているのであるから、その活動は、経済上の収支計算の上に立って行われている活動であることも否定できないところである。 (三)また、被告は、その舞踊活動の表示を自らの芸名の一字をとって「清派 音羽流」としているところ、舞踊界では同一流派から派生した流派について、同じ流れを組みつつも、流派としては別派であることを表象する文字を付加して流派名としている場合が多くみられるところである(乙第一一号証の藤間流の例)から、混同は生じていない旨主張する。 しかし、被告のいう「同一流派から派生した流派について、同じ流れを組みつつも、流派としては別派であることを表象する文字を付加して流派名としている場合」というのは、分派が承認されている場合であると認められるから、被告のように、退流した者がそれまで属していた流派と類似する表示を使用して舞踊活動を行う場合には当てはまらない。 3 右2説示のような誤認混同が生じれば、原告が新弟子を失い収益を減少させる等、営業上の利益を害されるおそれがあるというべきである。 三 争点3(被告の「清派音羽流」「音羽」の表示の使用について、不正競争防止法11条1項2号の自己氏名の善意使用に該当する等、違法性阻却事由があるか)1 被告は、六歳の頃から初代Cの指導を受け、原告が三代目Cを名乗る前から「E」を名乗っていることを理由に、「音羽」の名跡については原告が使用する前から使用しているものであり、また、被告にとって「E」は自己の氏名に相当するから、不正競争防止法11条1項2号にいう自己氏名の善意使用(不正目的でない使用)に該当するというべきである旨主張する。 しかし、不正競争防止法11条1項2号の趣旨は、人格権としての氏名権の行使を保護することにあるから、日本舞踊の芸名には当然には適用されず、原告の流派における芸名(名取名)の位置付け、被告が当該芸名(名取名)を使用するに至る経緯等を検討する必要がある。 音羽流の名取名における「音羽」姓が、名取に取り立てられた個人の芸名としての意味を有するだけではなく、同時に、家元「C」によって代表される「音羽流」の活動に属することを示すものであり、原告を家元とする音羽流一門の営業表示としての性格をも有するものであることは前記一1(三)認定のとおりであり、したがって、「音羽」姓を名乗ることを許されるのは音羽流一門にとどまっていることが前提条件であって、「音羽流」を退流した場合には、右名取名における「音羽」姓を使用し続ける根拠に欠けるというべきである。被告(大正一五年四月二〇日生)は、父親が昵懇の間柄であった六代目Bの薦めにより幼少の頃から初代Cの指導を受け、 昭和一六年に名取に取り立てられて「音羽」姓(当時は「N」。昭和二三年に「E」と改名)を名乗ることを許されたものであるが(乙第一、第二号証、被告本人)、昭和六一年五月頃に音羽流を退流し、名取に取り立てられた際に授与された免状も原告に返却しているのであるから(原告本人、被告本人)、被告主張の前記事実をもってしては、本件に不正競争防止法11条1項2号の適用ないし類推適用があるということはできない。 被告は、被告は初代Cから手ほどきを受けてこれこそ音羽流というその独特の「振り」と「手」を継承しているのであり、これに対し、原告は、初代C、二代目Cから手ほどきを受けておらず、現にその踊りは本来の音羽流とは離れているから、そのような原告よりも被告の方が正統な音羽流の継承者であり、したがって、 被告が新流派を創るときに音羽流の流れを組んでいることを標謗することは何ら異とするに足りず、むしろ「音羽」を名乗らない方が不自然である旨主張するが、 「音羽流」「音羽」の表示が営業表示としての性格を有し、右営業を原告が音羽流二代目家元として継承している以上、右主張は採用することができない。 2 しかして、証拠(乙第一二号証、被告本人)によれば、被告は、原告から本件訴訟を提起された後の平成五年秋、Fに会い、本件訴訟のことを話して自分は「音羽の手」(音羽流の踊り)しかできないので難儀している旨窮状を訴えたところ、 同人は、「音羽」のままでやればよいと述べ、被告の希望に従い、被告が「清派音羽流」として活動することを宗家として認可する旨述べたこと、その後、被告が、 Fに認可されたといっても形のあるものがないので困っている旨話したところ、同人は、書付けを与えることを約束し、同年一二月初め、自宅において、「證 E 右の音に日本舞踊流派音羽流(清派)の創流を音羽流宗家として認可します 平成五年癸酉年拾貳月吉日 七代目F」と記し、「F乃印」と刻した角印を押捺した本件書付けを被告に授与したことが認められ、証拠(原告本人)によれば、原告の姉がF(入院中)の妻に会って、本件書付けの件は困る旨話したところ、妻はFの意向として本件書付けを撤回する気はない旨伝えたことが認められるので、被告がFから本件書付けを授与されたことにより、被告が「清派音羽流」「音羽」の表示を使用するについて違法性が阻却されるか否かについて検討する(なお、本件書付けは、直接的には被告が「音羽流(清派)」を創流することを許可するものであるが、「E」宛になっていることでもあり、当然に「E」の名称の使用をも許すものであることが明らかである。)。 (一)証拠(甲第六号証、第八ないし第一〇号証、第一二、第一五、第一七号証、 乙第五、第九、第一三、第一四、第一六号証、証人K、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (1)歌舞伎役者は全員が個々の姓名とは別に屋号を有している。屋号は、江戸時代には苗字が公式には許されなかったため、それに代わるものとして既に使用されていたものであり、明治時代以降歌舞伎役者が苗字を使用するようになっても、その伝統ゆえに一定の意義を有している。 (2)「音羽屋」は、「歌舞伎俳優Bとその一門の屋号」であり(広辞苑第四版三七一頁)、伝統芸能に携わる者の間では周知の表示である。初代Cが音羽流を創流したときの音羽屋の当主ないし主宰者は六代目Bであり、原告が三代目Cを襲名し、被告が本件書付けを取得した時点での音羽屋の当主ないし主宰者はF(六代目Bの養子)である。 音羽流では、音羽屋の一門を宗家と呼んでいる。「宗家」とは、一般的には、 「宗主する家。本家。家元」(広辞苑第四版一四八五頁)という意味を有する。日本舞踊の他の流派、例えば扇流(同じく音羽屋を宗家とする。)、藤間流、若柳流、山村流などにも「家元」とは別に「宗家」が存在する。 (3)もともと、歌舞伎は舞踊をその要素として含んでおり、古くは、舞踊は独立した演目ではなく、芝居の演目の一場面として置かれていながら、芝居とは別種の固有の場として演じられる特殊な形態をとっていたが(その場面を上方では「景事」、江戸では「所作事」といっていた。)、現在では、歌舞伎の舞踊作品を「所作事」と呼んでいる。 六代目Bは、日本舞踊においても卓抜した技能をもって知られていたが、音羽屋一門が継承してきた日本舞踊を一般に広めることに熱心であり、いずれも「尾上」姓を使用していた弟子(歌舞伎役者)三名に、それぞれ音羽流、西川流、尾上流という日本舞踊の流派を創流することを命じた(ただし、西川流については、従来存在した小規模な西川流に初代Gが養子に入ったものである。なお、西川流は名古屋を、尾上流は東京を中心に活動している。)。 当時、「H」と称していた初代Cは、そのうちの一人であり、昭和九年頃、六代目Bから、その屋号「音羽屋」に因んで、流派名を「音羽流」とし、「C」と称することを許されたものである。 (4)昭和三四年一〇月三〇日開催の音羽流舞踊大会(当時の家元は初代C)のプログラム(乙第五号証)には、特別出演者の筆頭にFの名が記載され、同人が同じく音羽屋一門のOとともに特別出演している。 (5)昭和四四年五月二四日開催の初代Cの三回忌追善公演・C舞踊会(当時の家元は二代目C)のプログラム(乙第一四号証)には、特別出演者の筆頭にFの名が記載され、同人が音羽屋一門のP(Fの子で、後の七代目B)とともに特別出演している。 (6)原告が三代目Cを襲名した際の挨拶状(甲第八号証)には、Fを筆頭に、原告、二代目H、西川流家元Gの挨拶が記載され、原告の挨拶として「亡父初代C没後 家元G師の御交情の許にお教えを受けておりましたところ 先生の御推薦の許 F様のお許を得まして 三代目Cを襲名致すはこびと相成りました」、二代目Cの挨拶として「F様 G様 両先生方のおすすめを戴きまして 長男 Qに 三代目Cを襲名させることに相成り」、Gの挨拶として「F師のお許しをいただき ここに新家元が誕生しました」との各記載がある。 三代目C襲名披露舞踊会のプログラム(甲第一〇号証)にも、Fを筆頭に、G、 原告、二代目C改めR・S、尾上流家元L等の挨拶が記載され、Gの挨拶として「尾上宗家F師よりも心よくお許しをいただきましたのでここに新家元を誕生いたさせました」、原告の挨拶として「F様のお許しを得 三代目Cを襲名致すはこびと相成りました」、R・Sの挨拶として「F様 G様 両先生方のおすすめを戴きまして長男Tに 三代目Cを襲名させることに相成りました」、Lの挨拶(祝辞)として「六代目B師の流れをくむ音羽流の益々の御発展を祈り お祝の言葉といたします。」との各記載がある。右プログラム及び同舞踊会の案内(甲第九号証)には、特別出演者の筆頭にFの名が記載され、同人、L、Gを筆頭とする西川流の者多数が特別出演している。 (7)昭和四八年一〇月一日発行の大阪芸能新聞(甲第一二号証)には、原告が「F、Gの推薦で」三代目Cを襲名した旨の記載がある。 (8)昭和五一年五月二九日開催の音羽流舞踊公演のプログラム(甲第一五号証)には、原告の挨拶として「お陰をもちまして此の度、F様、B様、恩師G様各位様の温い御協賛を得まして、音羽流舞踊公演を開催させて頂くはこびとなりました」との記載があり、特別出演者として、F、七代目B、Gの順で紹介されている。 (9)昭和五七年一一月二七日開催の第四回音羽会のプログラム(甲第一七号証)には、原告の挨拶として、「おかげをもちまして此の度、F様、B様、U様各位の温い御協賛を得まして、音羽流舞踊公演を開催させて頂くはこびとなりました」との記載があり、特別出演者として、F、七代目B、Uの順で紹介されている。 (10)平成三年二月頃、音羽流一門のVを中心とする徳島音羽会及び雛菊会の会員が原告を家元とする音羽流を退流して独立し、VがFの認可を得て「菊ノ上流」を創流し、新たに「菊ノ上菊生」を名乗った。その際、原告は、事前にFにVの独立、新流派の創流を認可しないでほしいと申し入れていたが、Fはこれを無視する形となったため、以後、原告とFの関係は疎遠となった。 (二)右(一)認定の事実によれば、原告の「音羽流」「音羽」の表示は、もともと歌舞伎のBとその一門の屋号として著名であった「音羽屋」に由来するものであり、原告がこれを使用することができるのは、初代Cが当時の音羽屋の当主であった六代目Bから、音羽屋一門が継承してきた日本舞踊を広めるために日本舞踊の流派を創流することを命じられ、流派名を「音羽流」とし「C」と称することを許されたからにほかならず、また、音羽流家元の襲名に際しては、宗家である音羽屋当主の許しが重要な意味を有することが明らかである。 原告は、「(1)原告を家元に指名したのは宗家ではなく、宗家は家元の選定手続には何ら関与しておらず、何らかの許可手続がされたわけでもない。原告の挨拶文に「F様のお許を得まして 三代目Cを襲名致すはこびと相成りました」と記載されていても、それは形式上の権威づけのためであり、実際に、許可、認証のような儀式、意思表示がされたわけではない。(2)宗家から家元にその地位を認める免状や書き札が渡されたことはない。逆に、家元から宗家に対し、家元の地位取得の対価、宗家としての活動の対価、その他金銭が支払われたという事実もない。」と主張するが(第三の三【原告の主張】3(二)の(1)及び(2))、音羽流が六代目Bの命により音羽屋の屋号を取って創流されたこと、音羽屋の表示が周知のものであること、歌舞伎と日本舞踊に共通する伝統芸能としての性質を考慮すれば、宗家が家元襲名を許可することは、象徴的なものではあるが、これが単に形式上の権威づけにとどまるものとは考えられず、これなくしては音羽流内外に家元襲名の正当性を示す根拠に乏しくなるものといわなければならない。前掲各証拠によれば、原告の三代目C襲名につきFによる許可の意思表示がなされたことは明らかなところであり、右許可につき儀式や免状、書き札の交付、対価の支払いがないことは、右認定を何ら左右するものではない。 更に、原告の家元襲名披露の舞踊会に、Fのほか、同じく音羽屋に起源をもつ西川流及び尾上流の家元が特別出演していること、音羽流主催の舞踊会にFが何回も特別出演していることからみても、音羽流が音羽屋に起源をもつ意味は決して軽視できず、むしろ、右各事実から、初代C以来、歌舞伎の音羽屋の周知性を意識した上で、音羽流がその流れを汲む流派であることを強調してきたこと、したがって、 「音羽流」「音羽」の表示が日本舞踊関係者の間で周知になり、それが維持されているについても、音羽屋の流れを汲んでいる事実が与かって力があったものであることが推認できる。 以上によれば、原告の「音羽流」「音羽」の表示は、日本舞踊の流派の営業表示であるのみならず、広い意味で音羽屋一門に属することを示す表示でもあるということができ、したがって、音羽屋の流れを汲む日本舞踊の流派、という意味を当然に表象することになる。換言すれば、原告の「音羽流」「音羽」の表示は、音羽屋から完全に独立してこれと無関係に存立しうるものではなく、かえってこれに従属し、初代Cが創流時に六代目Bから名称使用の許可を受け、現在も原告が音羽屋を宗家として戴き広い意味で音羽屋一門に属しているという関係によって初めて正当に存立しえているものというべきである。 (三)しかして、原告は、被告がFから本件書付けを授与されたことは、被告が「音羽流」「音羽」の表示を使用することを正当化する根拠とならず、日本舞踊における「音羽流」「音羽」の名称の使用権、使用許諾権は、全面的に初代Cに帰属し、現在はその継承者の原告に帰属していると主張し、その根拠として、①「宗家」の地位が不明であること、②原告とFとの間には契約関係は存在せず、音羽流においてFの地位は事実上尊重されるものにすぎないこと、③「音羽流」「音羽」の表示の使用は自己の氏名の使用に該当しないことを挙げる。 確かに、音羽屋の当主が日本舞踊音羽流の「宗家」であるという場合の「宗家」の位置付けは、それほど明確ではなく、証拠(証人K、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告が「宗家」との関係が事実上のものであったことの根拠として挙げる前記第三の三【原告の主張】3(二)の(3)ないし(11)の事実が認められる(その(1)及び(2)の事実については、前記(二)説示のとおりである。)。また、「音羽屋」の屋号は、その歴史的経緯から歌舞伎の音羽屋一門に属する者の芸名ないしはこれに準ずるものというべきであり、Fの氏名とは言い難く、被告の「E」の名称が芸名であることはいうまでもない。 しかしながら、前示のとおり、原告が「音羽流」「音羽」の表示を使用することができるのは、初代Cが当時の音羽屋の当主であった六代目Bから、音羽屋一門が継承してきた日本舞踊を広めるために日本舞踊の流派を創流することを命じられ、 流派名を「音羽流」とし「C」と称することを許されたからにほかならないこと、 宗家が家元襲名を許可することは、象徴的なものではあるが、単に形式上の権威づけにとどまるものとは考えられず、これなくしては音羽流内外に家元襲名の正当性を示す根拠に乏しくなること、初代C以来、歌舞伎の音羽屋の周知性を意識した上で、音羽流がその流れを汲む流派であることを強調してきており、したがって、 「音羽流」「音羽」の表示が日本舞踊関係者の間で周知になり、それが維持されているについても音羽屋の流れを汲んでいる事実が与かって力があったこと、原告の「音羽流」「音羽」の表示は、日本舞踊の流派の営業表示であるのみならず、広い意味で音羽屋一門に属することを示す表示でもあるということができ、換言すれば、音羽屋から完全に独立してこれと無関係に存立しうるものではなく、かえってこれに従属し、右のとおり初代Cが創流時に六代目Bから名称使用の許可を受け、 現在も原告が音羽屋を宗家として戴き広い意味で音羽屋一門に属しているという関係によって初めて正当に存立しえているというべきであることに徴すれば、音羽屋の当主が、日本舞踊の流派の創流を許す際にそれが音羽屋の流れを汲むものであることを示すために「音羽流」の表示を許すことは不自然ではなく、その許可をある者に一度与えた以上はもはや他の者に与えることは許されないと解すべき根拠はなく、本件全証拠によるも六代目Bが初代Cに「音羽流」の創流を許した際に今後他の者に「音羽流」「音羽」の表示を許すことはしない旨約したというような事実も認められず、しかも、Fは、被告の創流に際し「清派」の表示を加えて「清派音羽流」として使用することを許可しており、一応原告を家元とする「音羽流」とは別派であることを示しているのであるから、このようにして被告が音羽屋の当主であるFから本件書付けの授与により新たに「清派音羽流」「音羽」の表示の使用を許された後の現在において被告がこれらの表示を使用することは、違法性を阻却されるというべきである。 |
|
|
結論
そうすると、原告の請求は、結局理由がないことになるから、これを棄却することとする。 |
| 裁判官 | 水野武 |
|---|---|
| 裁判官 | 田中俊次 |
| 裁判官 | 本吉弘行 |