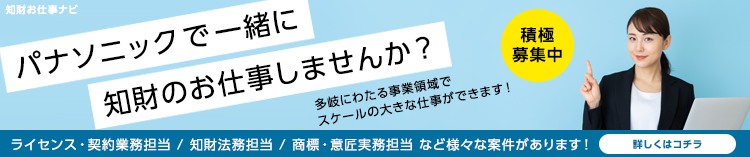| 関連審決 |
審判1996-10996 |
|---|
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成18ネ10080債務不存在確認等請求控訴事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
| 平成17ワ10073損害賠償請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
| 平成18ワ13013不正競争行為差止請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
| 平成16ワ9743損害賠償請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
| 平成17ワ3056損害賠償等請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
| 関連ワード | 広く認識 / 市場占有率 / 特段の事情 / 類似性(類似) / 観念 / 差止請求(差止) / 過失 / 共同不法行為 / 逸失利益 / 因果関係 / 単位数量 / 利益額(利益の額) / 権利濫用(権利の濫用) / 無形損害 / 弁護士費用 / 消滅時効 / 不当利得 / 侵害 / 代理人 / 代表者 / 営業誹謗行為(2条1項14号) / 品質等誤認表示(誤認) / 競争関係 / 営業誹謗 / 虚偽の事実 / 損害賠償 / 損害額 / 推定 / 販売数量 / 営業上の信用 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
17年
(ワ)
2535号
損害賠償請求事件
|
|---|---|
|
原告株式会社フジモト・ダイアグノスティックス 原告藤 本製薬株式会社 原告ら訴訟代理人弁護士山本忠雄 同 内藤秀文 同 安部朋美 同 中橋紅美 同 酒井一 被告日 本臓器製薬株式会社 訴訟代理人弁護士吉利靖雄 同 飯塚卓也 同 小野寺良文 同 古谷誠 |
|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2007/02/15 |
| 権利種別 | 不正競争 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1被告は,原告株式会社フジモト・ダイアグノスティックスに対し,952万円及びこれに対する平成17年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2被告は,原告藤本製薬株式会社に対し,1418万9392円及びこれに対する平成17年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4訴訟費用はこれを100分し,その1を被告の,その余を原告らの各負担とする。 --25この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
第1請求の趣旨1被告は,原告株式会社フジモト・ダイアグノスティックスに対し,15億円及びこれに対する平成17年3月24日(訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2被告は,原告藤本製薬株式会社に対し,15億円及びこれに対する平成17年3月24日(訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3訴訟費用は被告の負担とする。 4仮執行宣言第2事案の概要本件は,原告らが,被告が原告らの取引先等に対し,長年にわたり,原告らの製剤の製造販売は被告の特許権を侵害する,原告らの製剤には品質上の問題がある等と告知・流布し,また原告ら及びその取引先に対して特許権侵害差止, , めの仮処分申立てや訴訟提起等を行い その旨の主張立証活動を行ったことが一体として不正競争防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知・流布に該当し,予備的に不法行為,不当利得を構成すると主張して,同法4条ないし民法709条に基づく損害賠償又は民法703条,704条に基づく不当利得返還を求めた事案である。 1前提事実(証拠等の掲記のないものは当事者間に争いがない )。 (1)当事者等(「」 原告株式会社フジモト・ダイアグノスティックス 以下 原告フジモトDというは 医薬品の製造承認に必要な研究開発と製造設備を所有して ロ 。) , 「ーズモルゲン注 (以下「原告製剤」という )の製造を行っており,原告 」 。 藤本製薬株式会社(以下「原告藤本製薬」という )は,原告製剤の販売を 。 行っているグループ企業である(弁論の全趣旨 。)被告は,医薬品等の製造販売を業とする株式会社である。 (2)被告の特許権ア被告は,次の特許権を有している(この特許権を「被告方法特許権 ,」「」,「」 この特許発明を 被告方法発明この発明に係る方法を 被告発明方法という。。)発明の名称生理活性物質測定法出願昭和62年9月8日(特願昭62-225959)出願公告平成4年3月11日(特公平4-14000)登録平成5年1月19日特許番号第1725747号特許請求の範囲(請求項1)動物血漿,血液凝固第ⅩⅡ因子活性化剤,電解質,被検物質,から成る溶液を混合反応させ,次いで該反応におけるカリクレインの生成を停止させるために,生成したカリクレイン活性には実質的に無影響で活性型血液凝固第ⅩⅡ因子活性のみを特異的に阻害する阻害剤をカリクレイン生成と反応時間の間に実質的に直線的な関係が成立する時間内に加え,生成したカリクレインを定量することを特徴とする被検物質のカリクレイン生成阻害能測定法。 被告方法発明の概要は,訴状添付の被告方法特許権の明細書の記載によれば,次のようなものである。 (ア)カリクレインは,種々の動物の血漿中及び組織内に広汎に存在する蛋白質酵素であって,カリクレイン・キニン系を構成することで知られ, , , ており カリクレイン・キニン系は 種々の酵素系に密接な関連を有し様々な生体抑制機能に関わっている。 (,) , 血漿中に存在する血液凝固第ⅩⅡ因子 ハーゲマン因子 FⅩⅡ はカオリン等の血液凝固第ⅩⅡ因子活性化剤が添加されると,活性化して活性型血液凝固第ⅩⅡ因子(FⅩⅡa)に変化し,この活性型血液凝固第ⅩⅡ因子(FⅩⅡa)は,同じく血漿中に存在するプレカリクレインに作用して,これをカリクレインに変換し,さらに,このカリクレインは血漿中の高分子キニノーゲンに作用して,ブラジキニンを遊離させ,この遊離されたブラジキニンが炎症,痛み及びアラキドン酸カスケードに対する作用を引き起こす。 (イ)被告方法発明における反応は,2段階の反応で構成されており,第1次反応は,血漿にカオリン等の血液凝固第ⅩⅡ因子活性化剤を添加することによって,血液凝固第ⅩⅡ因子(FⅩⅡ)を活性型血液凝固第ⅩⅡ因子(FⅩⅡa)とすることにより,該血漿中のプレカリクレインをカリクレインに変化せしめてカリクレインを生成させる反応であり,第2次反応は,このようにして血漿中に生成したカリクレインの量を定量する反応である。 すなわち,動物血漿,血液凝固第ⅩⅡ因子活性化剤,電解質及び被検物質から成る溶液を混合反応させてカリクレイン生成反応を開始せしめた後,該反応におけるカリクレインの生成を停止させるために,カリクレインの生成と反応時間の間に実質的に直線的な関係が成立する時間内に,言い換えれば,単位時間当たりのカリクレイン生成量が一定の割合で進行している時間内に,活性型血液凝固第ⅩⅡ因子(FⅩⅡa)の活性のみを特異的に阻害してカリクレインの生成を停止する作用を有し,かつ 生成したカリクレインの活性には実質的に無影響である阻害剤 例 , (えばLBTI〔リマ豆由来のトリプシンインヒビター )を添加し(第〕1次反応 ,次いで,第1次反応液を,カリクレインに対する特異的基 )質及び緩衝液から成る第2次反応液と混合反応させる(第2次反応)という,2段階の反応により構成されている。 (ウ)上記第1次反応及び第2次反応は,酵素反応であるから,これらの酵素反応における酵素量は酵素そのものを物質量として測定するものではなく,単位時間当たりに当該酵素によって生成される反応生成物の量の大きさ,すなわち,酵素活性として測定される。 このように,被告方法発明における被検物質のカリクレイン生成阻害能の測定は,第1次反応で生成したカリクレイン活性の大きさを,第2次反応においてカリクレインとその特異的基質の反応によって生成する反応生成物(例えばp-ニトロアニリン)の量を定量することによって行われる。 , (「」 イまた被告は 次の特許権を有していた この特許権を 被告物質特許権いい,これに係る特許を「被告物質特許」といい,これに係る特許発明を「」。, ,「」 被告物質発明というまた特許請求の範囲の各項を便宜請求項という。。)発明の名称新規生理活性物質,その製造方法及び鎮痛,鎮静,抗アレルギー作用を有する医薬出願昭和52年2月17日(特願昭52-16498)出願公告昭和63年8月5日(特公昭63-39572)登録日平成元年4月7日特許番号第1490163号特許請求の範囲【訂正前のもの】第1項次の物理化学的性質:①性状:かつ色無定形の吸湿性粉末②溶解性:水,メタノール,エタノールに可溶③紫外部吸収:UVmax255-275nm④ニンヒドリン反応:陽性⑤本発明物質2mgをとり,過塩素酸1mlを加え,液が無色となるまで加熱し,希硫酸3ml,塩酸アミドール0.4gおよび亜硫酸水素ナトリウム8gに水100mlを加えて溶かした液2ml,モリブデン酸アンモニウム1gに水30mlを加えて溶かした液2mlを加え放置するとき,液は青色を呈し,⑥本発明物質5mgをとり,水を加えて溶かし10mlとし,この液1mlに,オルシン0.2gおよび硫酸第二鉄アンモニウム0.135gにエタノール5mlを加えて溶かしこの液を塩酸83mlに加え,水を加えて100mlとした液3mlを加えて沸騰水浴中で加熱するとき,液は緑色を呈し,⑦本発明物質の水溶液は硝酸銀試薬で沈澱を生じ,そして⑧本発明物質に対する各種蛋白検出反応は陰性である,を有する新規生理活性物質。 第2項次の物理化学的性質: 上記1に記載の物理化学的性質①~⑧ (と同一の記載)を有する物質を有効成分とする鎮痛剤。 第3項次の物理化学的性質: 上記1に記載の物理化学的性質①~⑧ (と同一の記載)を有する物質を有効成分とする鎮静剤。 第4項次の物理化学的性質: 上記1に記載の物理化学的性質①~⑧ (と同一の記載)を有する物質を有効成分とする抗アレルギー剤。 第5項ワクシニアウイルスを接種し,発痘させた動物組織(ひとを除く ,培養細胞,若しくは培養組織を磨砕し,これにフエノ )ール加グリセリン水を加えて抽出し,前記抽出液体を等電点付近のpHに調整し,次いでこれを加熱ろ過して除蛋白を行ない,除蛋白したろ液を弱アルカリ性条件下で加熱した後ろ過し,前記ろ液を酸性条件下で吸着剤と接触せしめ,そして水又は有機溶媒を用いて前記吸着剤から有効成分を溶出する工程からなることを特徴とする,次の物理化学的性質: 上記1に記載の物理化学的性 (質①~⑧と同一の記載)を有する新規生理活性物質の製造方法。 【訂正後のもの】訂正により,訂正前の請求項1及び5は削除され,訂正前の請求項2~4が請求項1~3に繰り上げられた )。 (3)被告製剤の製造承認と販売被告は,昭和28年9月5日,ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚組織抽出液及びそれを有効成分とする注射剤につき,厚生大臣から製造承認を受け,昭和51年9月1日,健康保険法に基づく薬価基準の収載を受け,同年11月1日から,上記抽出液の製造及び上記製剤( ノイロトロピン特号3 「cc 。以下「被告製剤」という )の製造販売を開始した。 」 。 被告は,昭和62年11月20日,厚生大臣に対し,被告製剤の品質検定のための規格試験中にカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験を追加する旨の製造承認事項一部変更申請を行い,平成4年5月11日,製造承認事項一部変更承認を受けた。被告が一部変更承認を受けたカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験は,別表5の「被告確認試験方法」欄記載の方法であり(以下「被告確認試験方法」という,被告方法発明に係る方法であった。 。)なお,被告は,昭和56年6月29日,上記抽出液を有効成分とする錠剤() ,, ノイロトロピン錠 について製造承認申請を行い 昭和62年10月2日製造承認を受け,昭和63年から販売を開始した(甲131 。)(4)原告製剤の製造承認と販売原告フジモトDは,昭和62年1月10日,厚生大臣に対し,被告の抽出液の後発医薬品として,その抽出液の製造承認申請を行い,同年11月13日,同様に厚生大臣に対し,被告製剤の後発医薬品として,原告製剤の製造承認申請を行った。原告フジモトDは,平成元年4月4日,厚生省から,原告製剤の各製造承認申請に,カリクレイン様物質産生阻害活性確認試験を追, 。, 加するよう指導され これを各製造承認申請へ追加した 原告フジモトDは平成4年2月21日 厚生大臣から原告製剤について各製造承認を受けた 以 , (下,これらの製造承認を「原承認」という。この各製造承認についての 。)医薬品製造承認書の「規格及び試験方法」の欄に記載されていた確認試験方法は別表5の「原告当初方法」欄記載のとおりであった(以下,この方法を「原告当初方法」という。原告当初方法は,実質的には被告発明方法と 。)同じであり,被告方法発明の技術的範囲に属するものであった。 原告製剤については,平成4年7月10日,健康保険法に基づく薬価基準への収載が官報に告示され,原告らは,同年10月1日,原告製剤の販売を開始した。 原告フジモトDは,平成4年12月22日,厚生大臣に対し,原告製剤のカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験を別表5の「原告変更方法」欄記載の方法(以下「原告変更方法」という )に変更する旨の各製造承認事項 。 一部変更申請(以下,まとめて「一変申請」という )を行い,平成11年 。 4月13日 厚生大臣から各製造承認事項一部変更承認 以下 まとめて 一 , (,「変承認」という )を受けた。原告変更方法は,被告方法発明の技術的範囲 。 に属しないものである (甲131,乙5及び6の各号) 。 (5)被告の特許権をめぐる訴訟等別表4「係争事件一覧表」のとおり,被告は,原告製剤の製造販売が被告の上記各特許権を侵害するとして,原告ら及びその取引先に対して仮処分申立て,訴訟提起及び刑事告訴を行い,他方原告フジモトDは,被告物質特許は無効であるとして無効審判を請求した(弁論の全趣旨 。これらのうちの)主たるものの経過は,次のとおりである。 ア被告方法特許権関係(ア)第1次訴訟a被告は,平成4年8月20日,原告フジモトDは原告製剤を製造するに当たって確認試験方法として被告方法発明の技術的範囲に属する「」(「」。) 別表5の被告主張方法欄の方法以下被告主張方法というを実施しており,原告製剤の製造販売は被告方法特許権を侵害するとして,原告フジモトDに対し,原告製剤の製造販売の差止め及びその薬価基準収載申請の取下げ等を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起するとともに(同裁判所平成4年(ワ)第7157号 ,同趣旨の仮処)(())(, 分 同裁判所平成4年 ヨ 第2897号 を申し立てた 甲116117 。)これに対して原告フジモトDは,同原告が実施しているのは原告変更方法であり,これは被告方法発明の技術的範囲に属しないとして争ったが,被告はこれを否認し,原告変更方法では後発医薬品が具備すべき確認試験方法の同等性を確保できないから原告フジモトDは被告発明方法を実施しているはずである等と主張して争った(乙1 。な)お,この訴訟の控訴審判決の時点までは,原告フジモトDの原承認に係る製造承認書の「規格及び試験方法」の項にどのような確認試験方法が記載されているのかということも,また原告フジモトDが上記のような一変申請を行っているということも明らかにされなかった(甲131 。)b大阪地方裁判所は,平成7年6月29日,①被告発明方法は,ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚組織抽出液及びこれを有効成分とする製剤の品質規格の検定のためのカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験の方法として現在までに知られている唯一の方法であるとはいえない,②LBTIのような阻害剤を用いなくとも実用に耐え得る生成カリクレイン定量の方法が存在する可能性があるから,LBTIのような阻害剤を用いない原告フジモトD主張の方法が生成カリクレインを定量するための測定法とはなり得ないとまで断定することはできない,③被告が被告製剤の製造承認申請書の「規格及び試験方法」の欄に記載したカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験の方法はLBTIを阻害剤として用いるものであると認められるものの,原告フジモトDが原告製剤の製造承認申請書の「規格及び試験方法」の欄に記載したカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験の方法については,証拠上不明というほかはない,④原告フジモトDが原告製剤の製造承認申請書の「規格及び試験方法」の欄に記載したカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験の方法と,原告フジモトDが現実に業として原告製剤について実施しているカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験の方法とは,必ずしも同じ方法であることを要しないものと認められる,⑤原告フジモトDが原告製剤の品質規格検定のためのカリクレイン様物質産生阻害活性の確認試験の方法として被告発明方法を実施しているとの事実は,全証拠によるも認められない,と判断し,被告の請求を棄却する判決を言い渡すとともに仮処分申立てを却下する決定をした(甲131 。)c被告はこれらに対し控訴及び即時抗告し,大阪高等裁判所(平成7年(ネ)第1743号,同年(ラ)第438号)は,平成9年11月18日,第1審判決を変更し,原告フジモトDは,原告製剤を製造するに際し,品質規格の検定のために,被告主張方法を使用していると認定し,①原告フジモトDが実施する方法は,被告方法発明の技術的範囲に属する,②被告方法発明は,概念的には方法の発明であるが,被告主張方法が原告製剤の製造工程に組み込まれ他の製造作業と不即不離の関係で用いられていることからすれば,実質的に物を生産する方法の発明と同視することができ,被告方法特許権は,被告方法発明を用いて製造された物の販売についても侵害としてその停止を求め得る効力を有すると判断した。その上で,被告の請求のうち,被告主張方法を用いた原告フジモトDの抽出液の製造の差止め,被告主張方法を用いた原告製剤の製造販売及び宣伝広告の差止め,②原告製剤の廃棄,③原告製剤について健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げを求める限度で被告の請求を認容し,その余の請求を棄却する判決を言い渡すとともに,同趣旨の差止め及び薬価基準収載申請取下げのほか原告製剤等の執行官保管を命じる仮処分決定(以下「大阪高裁仮処分決定」という )をした(乙1,3 。 。)d被告は,平成9年11月28日に原告フジモトDの彦根工場において,同年12月2日に原告フジモトDの羽曳野研究所において,原告製剤等の執行官保管を命じる上記仮処分決定を執行した(甲126,134 ),また厚生大臣は,上記仮処分決定に基づき,いったんは平成10年3月27日の厚生省告示第109号により,原告製剤を平成11年4(),, 月1日以降は薬価基準収載から除く旨を告示したが 乙4その後平成11年3月26日の厚生省告示第68号により,原告製剤を同年7月1日以降は薬価基準収載から除く旨に変更し(乙10 ,さらに)次に述べる上記仮処分決定の事情変更に基づく取消決定がされたことにより,同年6月28日の厚生省告示第149号により,原告製剤を薬価基準収載から除くことを撤回した(乙7 。)e大阪高裁仮処分決定については,大阪地方裁判所は,平成11年6月7日,原告フジモトDの申立てに基づき,原告製剤の試験方法について一変承認がされたことから,原告製剤については原告変更方法が実施されていると認められ,同方法は被告方法発明の技術的範囲に属, (,)。 しないとして 事情変更に基づく取消決定をした 甲128 129f原告フジモトDは 控訴審判決を不服として上告し 最高裁判所 平 , ,(成10年(オ)第604号)は,平成11年7月16日,原告フジモトDが被告主張方法を使用しているとの原審の認定判断は正当として是認できるとしたが,被告方法発明は方法の発明であって物を生産する方法の発明ではないから,原告フジモトDが原告製剤の製造工程において,被告発明方法を使用して品質規格の検定のための確認試験をしているとしても,その製造及びその後の販売を被告方法特許権を侵害する行為に当たるということはできないなどとして,原判決中原告フジモトD敗訴部分を破棄し,その部分につき被告の控訴を棄却する旨の判決を言い渡した(乙2 。)(イ)第2次訴訟a被告は,平成11年10月18日,原告フジモトDが原告製剤の品質規格の検定のために行ってきた確認試験の方法は被告方法特許権を侵害するものであるとして,原告らに対し共同不法行為に基づく損害賠償として連帯して17億6311万9960円の支払を求めるとともに,原告フジモトDに対し,提訴日から3年以上前の時期の原告藤本製薬による販売分につき,不当利得の返還として実施料相当額11億9230万円の支払を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成11年(ワ)第10931号,甲127 。)bこれに対し,大阪地方裁判所は,平成14年9月19日,原告フジモトDは,原告製剤の製造販売開始後は原告当初方法による確認試験を実施していたことが認定されるが,一変申請後(平成4年12月22日以後)は,原告当初方法とは異なる原告変更方法を実施していたものと認められるとして,原告フジモトDに対して前者の期間分の実施料相当額である5万0129円の支払を命じ,その余の被告の請求を棄却する判決を言い渡した(甲131 。)cこれに対して被告は控訴(原告らも附帯控訴)したが,大阪高等裁((),()) 判所 平成14年 ネ 第3263号 平成15年 ネ 第179号は,平成15年11月18日,原判決の認定判断を維持し,控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡し(甲132 ,同判)決は確定した。 イ被告物質特許権関係(ア)差止仮処分a被告は,原告製剤の販売は被告物質特許権を侵害するとして,平成6年7月5日に原告製剤を卸販売していた昭和薬品株式会社 以下 昭(「和薬品」という )に対し名古屋地方裁判所に,同じく株式会社バレ 。 オ(以下「バレオ」という )に対し札幌地方裁判所に,さらに同年 。 (「」。) 9月13日には同じく成和産業株式会社 以下 成和産業 というに対し広島地方裁判所に,それぞれ原告製剤の販売の差止めとその執行官保管を求める仮処分を申し立てた(甲119ないし121 。),,,, また被告は 平成7年6月29日 原告らに対し 同様の理由から原告製剤の製造販売及びその執行官保管等を求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てた(甲122 。)bこれら仮処分申立てのうち,名古屋地方裁判所は,平成7年10月31日,原告製剤は被告物質発明(訂正前の請求項1,2及び4)の技術的範囲に属し,昭和薬品の主張に係る特許の無効原因は認められないとして,昭和薬品に対して,原告製剤の販売差止めとその執行官保管を命じる仮処分決定(以下「名古屋地裁仮処分決定」という )。 をした(乙15 。)そこで被告は,同年11月10日及び13日,昭和薬品の配送センター及び支店において,原告製剤の執行官保管を命じる上記仮処分決定を執行した(甲124,125 。)他方,上記以外の仮処分申立てはいずれも却下され,それらに対して被告から即時抗告されたが,被告物質特許権の存続期間満了を見越して,平成9年2月14日に上記名古屋地方裁判所の仮処分事件と併せてすべて取り下げられた(弁論の全趣旨 。)(イ)侵害訴訟被告は,平成7年12月28日に昭和薬品に対して上記仮処分の本案訴訟を名古屋地方裁判所に提起したほか,平成9年1月24日には,原, (, 告らに対し 原告製剤の製造販売が被告物質特許権 訂正前の請求項12,4及び5)を侵害する共同不法行為であるとして,連帯して4983万8000円の損害賠償の支払を求める訴訟を同裁判所に提起した(甲123 。)これら訴訟は後に大阪地方裁判所に移送され,その後,後記のとおり被告物質特許が無効とされたことにより,平成17年1月28日に取り下げられた。 (ウ)無効審判a被告物質発明は,生理活性物質の物質発明(訂正前の請求項1 ,)その用途発明 訂正前の請求項2ないし4 及びその製造方法発明 訂 ( )(正前の請求項5)から成っていたが,原告フジモトDは,平成8年7月5日,特許庁に対し,これら発明は,Aほか「ワクシニアウイルスで感染した家兎皮膚組織中の生物活性物質の研究特に胃酸分泌抑制物質の分離とその性質 (昭和51年10月25日社団法人日本薬学 」会発行「薬学雑誌」96巻10号1247~1254頁,乙26。以下「A文献」という )ほかの公知文献から容易に発明することがで 。 きたこと等を理由にして,被告物質特許の無効審判(平成8年審判第10996号)を請求した。 これに対し特許庁は,平成9年6月18日,被告物質発明は原告フジモトD提出の公知文献から容易に発明することができたものとすることはできない等として,請求を不成立とする審決をした(乙16。 以下「第1次審決」という。。)そこで原告フジモトDが,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起した(同裁判所平成9年(行ケ)第215号)ところ,同裁判所は,平成11年7月15日,被告物質発明の請求項1(訂正前)の生理活性物質とA文献に記載された「抽出物Ⅱ」とは同一の物と認められるとして,審決を取り消す旨の判決をし(乙29。以下「第1次審決取消訴訟判決」という,同判決は確定した。 。)bこれを受けて被告は,平成11年7月29日,特許庁に対して,被告物質特許について,特許請求の範囲の記載のうち,請求項1(物質発明)と請求項5(製造方法発明)を削除する旨の訂正審判の請求をし,特許庁は,平成15年5月30日,同訂正を認める旨の審決をした(乙30 。)c第1次審決取消訴訟判決の確定を受けて,特許庁は,無効審判事件について更に審理した上,同年8月27日,被告物質特許を無効とす(,。「」。)。 るとの審決をした 甲137 乙31 以下 第2次審決 というその理由の要旨は,①第1次審決取消訴訟判決は,訂正前の請求項1記載の発明の生理活性物質は,A文献記載の「抽出物Ⅱ」と同一の物であると認定しているところ,当該認定は,行政事件訴訟法33条1項の規定により拘束力を有する,そして,訂正後の請求項1~3に係る発明の有効成分物質が,訂正前の請求項1に係る発明の生理活性物質と同一の物質であることは明らかであるから,当該有効成分物質は抽出物Ⅱと同一の物質である,②抽出物Ⅱは,MASUICHI TAKINO「ANEW DIRECTION IN THE ASTHMA TREATMENT BASED ON THE THEORY OFTHE MOVEMENT OF TENSION IN PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM (1 」) (,「」。) 952の目次及び43~47頁乙33以下B論文という( 。「」 に記載された生理活性物質 すなわちノイロトロピン 以下 B物質という )と同等の生理活性物質であると認められる,③B物質に鎮 。 痛,鎮静及び抗アレルギー作用があることは,被告物質発明の特許出願前に知られていたから,B物質と同等の生理活性物質である抽出物Ⅱを有効成分とする訂正後の被告物質発明1~3の鎮痛剤,鎮静剤及び抗アレルギー剤は,当業者が容易に発明をすることができたものと認められるというものであった。 dこれに対し被告は,東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起した(同裁判所平成15年(行ケ)第442号)が,同裁判所は,平成16年12月20日,上記審決と同旨の理由により,請求を棄却する旨の判決をし(甲138。以下「第2次審決取消訴訟判決」という,同。)判決は確定した。 2争点(不正競争防止法に基づく損害賠償請求関係), 。 (1)被告は 原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布したか(2)被告に故意又は過失があるか。 (3)被告の行為は違法性を欠くものか。 (4)消滅時効の成否(5)不正競争行為に基づく損害額(不法行為に基づく損害賠償請求関係)(6)被告の行為が不法行為を構成するか。 (7)消滅時効の成否(8)不法行為に基づく損害額(不当利得返還請求関係)(9)被告による不当利得の成否及び利得返還額第3争点に関する当事者の主張1争点(1)(営業誹謗行為の有無)について【原告らの主張】(1)被告は,平成3年から平成17年1月までの間,主に特許権侵害に関する誹謗中傷行為と品質に関する誹謗中傷行為を継続して行ったが,これらの不正競争行為は,取引先の卸売業者や医療従事者間において,被告製剤と同一薬効を持つ競争品たる原告製剤自体の信頼を喪失させあるいは少なくとも希薄化させて,その競争市場への浸透を妨害するという系統的,統一的な目的の下に,各行為が複合的効果を伴うよう計画されて,断続的・継続的に長期にわたり展開されたものである。したがって,以下の不正競争行為は,前記期間中の継続的な不正競争行為として把握すべきである。 (2)特許権侵害に関する営業誹謗行為についてア被告の行為内容(ア)取引先等への告知・流布被告は,原告製剤の製造販売が被告の特許権を侵害するとして,平成4年7月9日に業界紙に「警告 (甲1)を,また同年8月21日には 」「謹告 (甲2)をそれぞれ掲載して,原告製剤の販売開始以前から, 」あたかも原告製剤が被告の特許権を侵害しているかのような事実を流布し,原告製剤の取引先となる主要卸売業者を含む製薬業界関係者全体に対し原告製剤を取り扱わないよう警告した。 また,同年9月からは,原告フジモトDに対して第1次訴訟を提起したということを巧みに利用して,個々の卸売業者に対し,原告製剤が被告の特許権を侵害しているという虚偽の事実を告知し,さらには原告製剤を取り扱った場合には,その取扱会社に対しても訴訟提起をするといった半ば脅迫的な内容の文書を配布し,原告製剤の取扱いを自粛するよう呼びかけた。かかる文書は,少なくとも,平成5年12月,平成6年,, ,, 1月 同年2月 同年4月と複数回にわたって作成されており 被告は文書と口頭を織り交ぜながら,卸売業者の動向を絶えず牽制していた。 中には,被告において長年訪問すらしていなかった卸売業者を突然訪れたり,被告と取引のない卸売業者にまで接触してかかる文書を配布しており(甲20,40,57,68,75,83 ,執拗に原告製剤を取 )り扱わないよう心理的圧力をかけ,その普及を妨害した。 ,, , また 被告は 平成9年11月18日の大阪高裁仮処分決定に基づき被告が原告フジモトDの工場にて原告製剤の在庫品について執行官保管の仮処分の執行を行ったことを奇貨として,平成9年12月,平成10年1月,同年2月には,原告製剤の薬価基準収載削除が近い将来確定す, 。 るとの虚偽の事実を告知・流布し 原告製剤に対する信頼性を毀損したなお,主たる虚偽事実の告知は,被告の営業社員により口頭によりなされたが,主な内容は 「原告製剤を扱うな「扱った会社に対して ,。」,提訴する 」という脅迫的なものと 「被告の勝訴により原告製剤の安 。 ,定供給ができなくなる 」という虚偽のものであった(甲11ないし5 。 4,56,65,75,78,83,93 。)取引先等に対する個々の不正競争行為については,別表1に記載のとおりであるが,これらの特定された不正競争行為をもって,被告の前記全期間にわたる継続的不正競争行為が推認される。 (イ)訴訟における告知別表4「係争事件一覧表」記載の各事件において,被告は,原告製剤が被告の被告方法特許権及び被告物質特許権を侵害するとの主張を繰り返し行ったが,この行為は,①本案訴訟においては,その事件記録や口頭弁論期日,判決内容は公開されているのであるから,訴訟手続を通じて不特定多数人に対して上記の事実を流布したことになり,②原告らの取引先を相手方とした訴訟及び仮処分手続においては,その取引先に対して上記の事実を告知したことになる。 イ被告の告知・流布内容の虚偽性(ア)被告物質特許権に関する虚偽被告物質特許は,これを無効とする審決が確定したとおり,その生理活性物質の存在は以前から知られていたものであり,明らかな無効理由があるにもかかわらず,被告は,同特許があたかも有効なものとして,原告製剤が同特許権を侵害する旨告知・流布しており,この点が虚偽である。 (イ)被告方法特許権に関する虚偽原告フジモトDは,遅くとも平成4年12月22日には既に被告方法発明の技術的範囲に属しない原告変更方法を使用していたのであり,この旨は第2次訴訟の第1審判決及び控訴審判決においても認定されている。したがって,原告フジモトDが実施している確認試験方法は,被告方法発明の技術的範囲に属しないにもかかわらず,被告は,原告らが被告方法特許権を侵害している旨告知・流布しており,この点が虚偽である。 また,被告方法発明は単純方法の発明であり,このような発明に係る特許権に基づいては,原告製剤の製造販売自体を差し止めることはできないにもかかわらず,また薬価基準収載から削除されることもないにもかかわらず,あたかも原告らが特許権侵害をし,それにより原告製剤の製造販売ができなくなる旨告知・流布しており,この点が虚偽である。 ウ以上のとおり,被告が特許権侵害に関して告知・流布した行為は,虚偽のものであり,かつ原告らの営業上の信用を害するものであるから,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為を構成する。 (3)品質に関する営業誹謗行為についてア被告の行為内容被告は,上記各特許権に関する営業誹謗行為と並行して,特に平成6年から平成7年にかけて,原告製剤に以下のような品質上の問題があるとの虚偽の事実を捏造して,卸売業者や医療機関に対し,この虚偽の事実を被告の営業社員が口頭により繰り返し告知することにより,原告ら並びに原告製剤の信用を毀損して,原告らの営業を妨害した。 (ア)農薬,不純物の混入被告は,原告製剤に,サリチル酸等の不純物が混入している,又は農薬ないしは農薬類似物質が混入しているとして,口頭及び書面で卸売業者・病院等の取引先にこれを告知した。 (イ)副作用そして被告は,原告製剤には上記のような品質的に問題があるがゆえに副作用が発生しているなどと虚偽の事実を告知し,副作用情報なる書面を各医療機関に配布し,原告製剤の使用中止を呼びかけた。 確かに,一般論としては,薬物には一定の副作用は必然的に発生するもので,原告製剤も(そして被告製剤も)この例外ではなく,副作用情報も発信している。しかし,副作用発生の具体的実例及び副作用発生の病理やメカニズムを精査・説明することなく,単にその事実だけを殊更に取り上げて不信感を増幅するような言い回しをすれば,その副作用情報を断片的に受けた者は,心配し不安になるのは当然であり,この不安心理を意図的に営業活動に用いることは虚偽の事実の告知と同視されるべき不正競争行為と解すべきものである。 (ウ)取引先等に対する個々の不正競争行為については,別表2に記載のとおりであるが,これらの特定された不正競争行為をもって,被告の前記全期間にわたる継続的不正競争行為が推認される。 イ被告の告知・流布内容の虚偽性(ア)農薬,不純物の混入に関する虚偽原告製剤には農薬は混入していないにもかかわらず,混入していると告知・流布した点において虚偽である。また,2,2’-ジハイドロキシビフェニール,サリチル酸,防腐剤等の混入については,原告製剤への混入自体を虚偽とするものではないが,それは,厚生省の定める基準の範囲内であり,安全性には全く問題がなく,またこれらの物質は被告製剤にも含まれているにもかかわらず,原告製剤にのみかかる物質が混入し,安全性に問題がある旨告知・流布した点において虚偽である。 (イ)副作用に関する虚偽原告製剤を使用している患者に副作用的な症例が生じたこと自体を否定するものではないが,それが原告製剤のみが原因で生じたのか,他の服用薬剤の影響で生じたのかは科学的に判明していない,すなわち副作用の発生原因・メカニズムが全く不明であるにもかかわらず,発生した症例を殊更に取り上げて,あたかもその原因が原告製剤のみにあるかの如く告知・流布した点において虚偽である。また,原告製剤の服用により,ショック症状や肝障害・血管痛等が副作用として生じる可能性があること自体を虚偽とするものではないが,かかる副作用は被告製剤においても同様に発生する可能性があり,また原告製剤は厚生省の認可を受けた品質上問題のないもので,現に厚生省や医療現場において特に副作用が問題となったことはないにもかかわらず,あたかも原告製剤の品質に問題がありそのために副作用が発生して大きな問題になっているかの如く,副作用を殊更に取り上げて告知・流布した点が虚偽である。 ウ以上のとおり,被告が品質に関して告知・流布した行為は,虚偽のものであり,かつ原告らの営業上の信用を害するものであるから,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為を構成する。 【被告の主張】(1)被告が原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布したことは否認する。 なお原告らは,被告による告知行為を一連一体の行為として総体的に評価すべきであると主張する。しかし,不正競争防止法2条1項14号に定める営業誹謗行為は,客観的真実に反することを告知・流布することを要件事実とするものであるところ,個々の行為ごとに告知した内容が異なる上記「一連の行為の総体」なるものについて,その内容を包括的にみて客観的真実に反するか否か判断することはそもそも不可能である。なぜなら,営業誹謗行為における「虚偽の事実」の告知行為に該当するかどうかは,個々の告知行為における告知の具体的な内容,ニュアンスはもとより,告知がなされた具体的な状況,告知者と受け手の関係,受け手の予備知識の有無などを踏まえた,複雑で微妙な判断が必要となることは当然であるからである。このように,不正競争防止法2条1項14号の適用に当たっては,個別の具体的な告知行為の内容について,個別に営業誹謗行為の該当性が判断されなければならず 「一連の行為の総体」なるものが全体として同号の営業誹謗行為とな ,ることはあり得ない。 (2)特許権侵害に関する営業誹謗行為についてア原告ら主張の虚偽性について(ア)被告方法特許権関係について原告製剤は,被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けたものであるが,後発医薬品は先発医薬品と同一の医薬品であることが要求されており,先発医薬品と同一の品質(有効性及び安全性の担保)を維持させる必要上,一般に,製造承認事項中「規格及び試験方法」についても先発医薬品と同一であることを条件に承認されるものである。そして,先発医薬品である被告製剤の製造承認事項中の「規格及び試験方法」には被告発明方法が定められていたのであるから,後発医薬品である原告製剤の製造承認事項にも同一の試験方法を行うことが定められていることは当然であり,実際に原告当初方法は被告発明方法であった。 そこで被告は,以上の判断のもと,原告フジモトDが原告製剤の製造承認を取得した後,被告発明方法を実施していると確信し,第1次訴訟を提起し,仮処分の申立てを行ったわけであるが,同事件について大阪高等裁判所の控訴審判決は,原告フジモトDが原告製剤を製造するに当, , たって被告発明方法を使用していると認定し この認定判断については最高裁判所の上告審判決においても,適法に認定された事実として正当なものと是認されている。 また,上記控訴審判決及び大阪高裁仮処分決定は,原告製剤の製造販売の差止め及び健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ等を命じており,これを受けて厚生大臣は,原告製剤の薬価基準収載を平成11年4月1日以降削除する旨の告示を行った。 このように,原告フジモトDが被告方法特許権を侵害して原告製剤を製造していた事実,及び,その結果厚生大臣により原告製剤の薬価基準。, 収載を削除する旨の告示がなされた事実は客観的真実である もっとも上記告示の後も原告製剤の薬価基準収載が継続されたが,それはもっぱら,原告製剤の製造承認事項一変承認という,全くの事後に生じた事情によるものであって,そのような事後的な事情がなければ原告フジモトDは被告方法特許権を侵害することなしに原告製剤を製造できず,その結果原告製剤の薬価基準収載が削除されたであろうことは明らかである。 以上のとおり,被告方法特許権関係について原告らが虚偽であると主張する点はいずれも虚偽ではない。 (イ)被告物質特許権関係について被告物質特許を無効とする旨の特許庁の審決が後に確定したことは事実であるが,以上に述べたとおり原告フジモトDが被告方法特許権を侵害して原告製剤を製造していたこと,及び厚生省が原告製剤の薬価基準収載を削除する旨の告示を行ったことが真実である以上,結果として原告フジモトDが被告物質特許権を侵害したことがなかったとしても,原告フジモトDが被告の特許権を侵害していたことは事実であり,被告が虚偽の事実を告知したことにならないことは明らかであるから,被告物質特許権関係について原告らが虚偽であると主張する点も虚偽ではない。 イ被告の行為について(ア)原告らが別表1で特定する被告の行為のうち,被告が業界紙に原告ら主張の「警告」等を掲載したこと及び被告製剤の顧客に配布するために文書を作成したこと(別表1の1-1ないし1-10,1-109ないし1-112)は認める。 しかし,そこに記載された内容はいずれも真実である。また,これらの謹告等の文書の文面は,当時被告が依頼していた弁護士の指導を受けて作成されており,その内容は医薬品業界において特許権に関する紛争が生じた際に一般的に掲載される文章とほぼ同様のごく一般的な記載でしかない。 (イ)原告らが別表1で特定する被告の行為のうち,上記以外の,被告の従業員(MR)が医師や医薬品卸売業者等の顧客に対して口頭で原告ら主張のような「虚偽の事実」を告知・流布したことは否認する。 すなわち,被告では支店長会議等の場で訴訟の節目ごとに特許訴訟を担当していた技術法務部より各支店長及び営業所長らに対して訴訟の経過を直接説明しており,また,前記のとおり客観的真実のみが記載された文書を掲載,配布しているが,各MRにもこれら真実のみが記載された文書を配布し,MRに対して真実に基づいた説明を顧客に対して行うよう指示していた。 また,被告では,日本製薬工業協会の定める「医療用医薬品プロモーションコード」あるいは医薬品製造業公正取引協議会の定める「医療用医薬品製造公正競争規約 ,さらに被告独自の「医療用医薬品プロモー 」ションコード」を策定した上(これらのプロモーションコードや規約には,いずれも競業他社あるいはその製品を誹謗中傷してはならない旨が厳格に定められている,営業の現場に対してこれを遵守するよう徹 。)底していた。また,被告では,平成5年から平成9年当時,医薬品業界の自主規制として制定された医薬品情報担当者教育研修要綱に基づき,MRに対する研修教育を,MRとなる際に行う導入教育として6か月で840時間,MRとなった後に毎年行う継続教育として年間100時間以上もの研修を実施しており,上記のプロモーションコードや規約を繰り返し徹底していた。 そして実際に,被告のMRは総じて医薬品営業本部の指示に従った適切な説明を顧客に対して行っていた。 原告らは自社MRからの報告(メモ等)に基づいて被告のMRが別表1記載のような内容を告知したと主張するが,原告ら主張の中には行為の主体や客体すら特定できていない杜撰なものが多数存在するほか,被告以外の他社の社員が告知したとするもの,原告らの証拠(メモ等)に原告ら主張に沿った記載が全くないもの,前記のような客観的真実のみしか記載されていないものなどが多数存在する。その上,原告らの自社MRからの報告(メモ等)は,情報元の医師や医薬品卸売業者の従業員から,被告のMR等の発言の内容とされるものを聞き取った上で,さらにその内容を原告らの社内で使用する報告書にまとめた伝聞証拠にすぎず著しく信用性の乏しいものである。 (ウ)なお,原告らが別表1で特定する被告の各行為についての被告の詳細な認否反論は別表1の「被告の認否・反論」欄記載のとおりである。 (3)品質に関する誹謗中傷行為についてア原告ら主張の虚偽性について(ア)農薬,不純物の混入の点について, ( ) 被告が 原告製剤が入手可能になった当初 平成5年ないし平成6年の複数のロットの製品につきその成分分析を継続的に行ったところ,原告製剤は,被告製剤との比較において,アミノ酸や蛍光物質等の含有量, , に差がみられ また一部のロットではサリチル酸が多く含有されるなど含有組成成分について,被告製剤と明らかに異なる点のあることが判明した。 その中で,特に品質上問題となったのは,毒性が示唆される2,2’-ジハイドロキシビフェニールが原告製剤で多量に検出されたことである。すなわち,被告製剤では検出下限に近い19ないし30ng/mlしか検出されないのに対し,原告製剤では637ないし2009ng/mlも検出された。このように原告製剤に混入していた2,2’-ジハ,.. イドロキシビフェニールの量は 被告製剤の実に21 2倍から1057倍にも及んでいたのである。 この2,2’-ジハイドロキシビフェニールは,主として柑橘類の収穫後の品質保持期間を延ばすためのいわゆるポストハーベスト農薬(柑橘類の外皮に散布される抗菌剤,防腐剤)として使用されるビフェニールや2-ハイドロキシビフェニールと化学構造的に極めて類似しており,毒性が強い物質である。 以上のとおり,原告製剤への不純物の混入について原告らが虚偽であると主張する点は,虚偽ではない。 (イ)副作用の点について原告製剤の使用により被告製剤では発現しなかった副以下のとおり,作用が発生していたことは客観的真実である。 a広島県安芸郡で発生した注射時痛については 「ノイロトロピンで,はこんな事は一度もなかった」と報告されている。 b広島市西区(以下略)の医院で発生した頭痛,手のしびれ,腹部膨満感,はきけといった副作用についての報告では 「ローズ・モルゲ,ン使用開始して2週間で,疑わしい症例いれると4例に副作用が認められたとの事「副作用は初回投与で発現,2回目はローズ・モル 」,ゲンを抜いて投与したところ異常は認められなかったとのこと「初」,回投与にて2~3時間後患者より訴えありソルコーテフ・プリンペラン強ミノ等を投与した。CT検査を行う。どの症例も症状が3~4時間続くのが特徴的」との報告がある。 c広島市西区の医院で発生した頭痛,手のしびれ,腹部膨満感,はきけの副作用の報告では 「 ノイロトロピン特号3cc』の代わりに ,『『ローズモルゲン注』を使用,開始2週間で,4例に副作用を認めたため使用を中止した「他の2例でも『ローズモルゲン注』+『シ 。」グマビタミン』混静注で同様の副作用発現。2回目は『ローズモルゲン注』を抜いて投与した所,異常は認められなかった 」との報告が。 ある。 d堺市の医院で発生した発疹の副作用につき「3月からローズモルゲン注に代えた所,1例に発疹発現,ノイロトロピンに戻した 」との。 報告がある。 e山口県柳井市で発生したそう痒を伴う全身発赤発現と血管痛につき「6月中旬からローズモルゲン注を使用」したところ発現したとの報告がある。 f和歌山市の医院で発生した突発性高血圧症につき「4月よりローズモルゲン注を使用しはじめた所」との報告がある。 イ被告の行為について(ア)原告らが別表2で特定する被告の行為のうち,被告が被告製剤の顧( ) 客に配布する目的で文書を作成したこと 別表2の2-1及び2-50は認める。 しかし,そこに記載された内容はいずれも真実である。 (イ)原告らが別表2で特定する被告の行為のうち,上記以外の,被告の従業員(MR)が医師や医薬品卸売業者等の顧客に対して口頭で原告ら主張のような「虚偽の事実」を告知・流布したことは否認する。 被告は,MRに対して品質に係る情報を提供するに当たって,医薬品営業本部において分析結果のデータや副作用に関する医療現場からの報告はもちろん,原告製剤に含まれた不純物に毒性があることの科学的根拠となった論文についても具体的に指摘した客観的真実のみが記載された資料を作成し,これを配布した上で,各MRに対して医師や医薬品卸売業者等の顧客に対してこれらの資料に基づいて客観的真実のみを伝えるように指示を徹底していた。また,被告では,平素から競業他社や他社製品を誹謗中傷することのないようMRに対して徹底した教育を実施していた。 そして実際にも,被告のMRは総じて上記医薬品営業本部の指示に従った適切な説明を顧客に対して行っていた。 原告らは自社MRからの報告(メモ等)に基づいて被告のMRが別表2記載のような内容を告知したと主張するが それらについては前記(2) ,イ(イ)で指摘したのと同様の点を指摘することができる。 (ウ)なお,原告らが別表2で特定する被告の各行為についての被告の詳細な認否反論は別表2の「被告の認否・反論」欄記載のとおりである。 2争点(2)(営業誹謗行為についての故意・過失)について【原告らの主張】(1)被告は,前記のような営業誹謗行為を行うに当たり,事前に原告らと交渉・議論することを一切せず,突然,業界紙へ警告文を掲載したり,卸売業者へ書面を送付するなどした。かかる被告の行為は,特許権という権利を楯にして,とにかく原告らとの間に係争状態を創出しようと企図したものといわざるを得ず,被告に故意があることは明らかである。また,少なくとも特許権に対する自己の見解を軽率に過信したものであり,過失が認められる。 (2)被告方法特許権に関する被告の故意・過失原告フジモトDが平成4年12月に一変申請をし,原告変更方法を確立・実施していることは,第1次訴訟の第1審のごく初期の段階で開示されていた(平成5年2月26日付け準備書面において開示,平成5年3月16日の口頭弁論期日にて陳述 。にもかかわらず,被告は,被告発明方法以外に確 )認試験方法はないとの考えに固執し,原告変更方法は実施不可能であると主張して,裁判所を誤導したものである。原告フジモトDは,被告に対し,自らの確認試験方法を訴訟のごく初期の段階で開示しているのであるから,被告は,原告らが被告方法特許権を侵害していないことを知っていたものであり,また,必要な事実調査及び法律的検討をすれば,容易に自己の主張が,事実的・法律的根拠のないものであることを知り得たはずである。にもかかわらず,被告は,意図的又は過信により自らの考えに固執し,独自の理論を展開して,長期にわたり原告らを裁判に拘束したものであり,裁判制度の趣旨目的に照らしても著しく相当性を欠くものである。 , 。 よって 被告が前記営業誹謗行為を行うについては故意又は過失があった(3)被告物質特許権に関する被告の故意・過失被告物質発明の有効成分「ノイロトロピン」については,1952年のB論文等で古くから知られており,被告物質発明の特許出願前から,被告自ら鎮痛,鎮静及び抗アレルギー作用の医薬品として長年にわたり市販し続けていた。かつ,同特許出願直前の昭和51年10月には,A文献で,まさに被「」。 告物質発明の有効成分そのものの物性を示す 抽出物Ⅱ が公表されているかかる事情の存する被告物質特許である以上,被告は,その有効性を疑問視するのが当然であり,特に第三者に対しその権利行使をする際には,より慎重な検討・対応を行うべきであった。 なお,1952年のB論文を公表した株式会社大日本臓器研究所は社名変更前の被告のことであり,また昭和51年のA文献にも被告が実験に協力した事実が明記されている。したがって,被告物質発明の特許出願前に被告がこれら文献の存在を知り得なかったことなどあり得ない。被告は,被告物質特許の有効性につき,事実的・法律的根拠のないことを知っていたものであり,また,必要な事実調査及び法律的検討をすれば容易に事実的・法的根拠のないものであることを知り得たものである。にもかかわらず,あえて被告は訴えを提起したものであり,裁判制度の趣旨目的に照らしても著しく相当性を欠くものである。 以上にかんがみると,被告には,前記営業誹謗行為を行うに当たって,故意又は過失があったというべきである。 【被告の主張】被告に故意又は過失があったとの主張は否認する。 (1)被告方法特許権関係に関する被告の故意・過失について原告フジモトDが被告方法特許権を侵害して原告製剤を製造していたことが真実であることは前記のとおりであるが,この特許権侵害に基づいて原告製剤の製造販売等を差し止めることができないと予見することはできなかった。 すなわち,被告方法特許権に基づき原告製剤の製造販売等の差止めが請求できるか否かという法律問題については,被告は,被告方法特許権に係る確認試験方法が,原告製剤の「製造工程に必然的に組み込まれ他の製造作業と不即不離の関係で用いられて」おり 「 方法の使用』即『物の生産』とい ,『う関係が成立している」という実質にかんがみ,それが可能であると判断したものであり,第1次訴訟における大阪高等裁判所の控訴審判決も同趣旨の。,, , 判断をした そして この点は 相手方であった原告フジモトDにおいても上告理由に至るまで実質的な反論を行っていなかったものである。 かかる状況の下において,当時,被告方法特許権によって原告製剤の製造販売等そのものを差し止めることはできないと被告が判断することは困難であり,それが可能であると判断したことについて,被告に過失はなかった。 また,この点の解釈については,大阪高等裁判所の控訴審判決と最高裁判所の上告審判決とで判断が分かれるほどの微妙な法律問題だったのであるから,告知行為当時,被告において差止請求の可否について判断することは極めて困難であったといえ,やはり被告に過失があったとはいえない。 さらに,被告方法特許権の侵害に関する告知行為の大半は,上記控訴審判決の後になされたものであり,同判決での公権的判断に従ってなされたものである。したがって,公権的判断を信じて行った告知について過失は否定されるべきである。 (2)被告物質特許権関係に関する被告の故意・過失についてア被告物質特許権の行使や同特許権に基づく権利侵害警告について,被告に過失があったかどうかを判断するに際しては,①最終的に無効理由が存在すると判断される基礎となった公知技術文献等の資料の入手の有無及びその可能性,②当該資料から当該権利に無効理由が存在すると判断することの困難性について十分に検討されなければならない。 イ被告物質特許権について,その特許出願から特許登録に至るまでに特許庁から通知された拒絶理由は,①昭和62年改正前特許法38条但書の併合要件違反の指摘と,②明瞭でない記載に対する釈明という,ごく形式的なもののみであり,この間,最終的な無効判断の基礎とされたA文献はもちろん,被告物質特許の特許要件の欠如を指摘する先行文献が特許庁から示されることは一切なかった。また,被告物質特許の出願公告がなされた後も一件の異議申立てもなされないまま特許登録に至っている。 , , このように 特許出願から特許登録に至る審査手続は極めて円滑であり被告物質特許には,何らの無効理由の存在を疑わせる事情は存在しなかった。 ウA文献の研究テーマは,その表題からも明らかなとおり 「胃酸分泌抑,」, 「, 制物質の分離とその性質 であり 被告物質特許の対象医薬である 鎮痛鎮静,抗アレルギー作用を有する医薬」とはおよそかけ離れた物質を対象としている。そのため,A文献は,そのテーマ及び対象物質の作用からしても,およそ被告物質特許との関係での無効理由の検討対象からも除外されてしまう論文であった。また,仮に当時被告知的財産部門において同文献の内容を検討し考慮したとしても,そこに採りあげられている物質は,表題のとおり「胃酸分泌抑制物質」であって,被告物質特許が提供する鎮痛剤等の医薬ではない。 そして,別表6のとおり,A文献記載の抽出物Ⅱの物性等も,被告物質特許の鎮痛剤の物性等とは著しく異なっていたのであるから,A文献は,その検討によっても被告物質特許の無効理由とされるなどとはおよそ考えられない文献である。 加えて,後発医薬品メーカーとして被告物質特許を無効にするという点に最も強いインセンティブを有していた利害関係人であったはずの原告らですら,被告物質特許の出願公告後に特許異議申立てを行わなかったことはもとより,その後平成6年以降に権利行使を受けた後ですら,平成8年7月に無効審判請求を申し立てるまで,A文献に基づく無効理由を主張したことはなかった。 このように被告においては,そもそもA文献を被告物質特許の無効理由として検討する実質的可能性がなかったといえるのであるから,被告が被告物質特許を有効と信じてこれを行使したことについて過失は存在しない。 エまた仮にA文献を前提にしたとしても,技術専門官庁である特許庁は,第1次審決において,A文献を精査した上で無効審判請求は成り立たない旨の審決を下している。告知行為がなされた当時,被告がA文献を検討すべき公知文献と位置付けていなかったことは前述のとおりであるが,少なくとも後に無効審判が成り立たないとの審決が得られている事実は,仮に告知当時においてA文献を検討していたとしても権利行使を回避することが困難で,被告に過失はなかった事実を強力に推認させるものである。 オさらに被告物質特許の特許請求の範囲は,東京高等裁判所の第1次審決取消訴訟判決後に訂正され,発明の対象が医薬に限定されたが,その薬効はA文献に全く開示のない薬効であった。しかるに,かかる訂正後の被告物質特許について,特許庁及び東京高等裁判所は,全く製造方法並びに物質の異なるはずのB論文が同種物質の鎮痛作用を開示しているとして,A文献の抽出物Ⅱについても同様の効果を予見できるとして,その進歩性を否定したわけであるが,その判断過程は,前提事実(5)イ(ウ)cのような複雑で技巧的とさえいえる論理を用いている上,特にその判断過程中②の部分においては,A文献に記載された「抽出物Ⅱ」とB論文及び特公昭和25-4206号公報(以下「4206号公報」という )に記載された。 物質とは,別表7及び8のように製法及び物理化学的性質を異にするにもかかわらず両者を実質的に同等の物質であるとしている。そうすると,このような複雑かつ技巧的な論理で判断がなされたこと自体が,被告物質特許の進歩性の判断が極めて困難であることを示しているといえる。 そして何より,上記一連の無効審判請求手続は,平成8年7月5日の審判請求時から東京高等裁判所の判決が確定した平成17年1月4日まで,足かけ10年もの審理期間を要しており(その間に3件の審決(訂正審決を含む )と2件の判決がなされている,この一事をもってして 。 。)も,被告物質特許の無効理由について判断することがいかに困難であり,被告の予見可能性がなかったかがわかる。 以上のとおり,被告において,被告物質特許権を権利行使した平成6,7年当時,仮にA文献を踏まえて無効理由の有無を判断したとしても,被告物質特許が進歩性を欠いて無効になると予見することは,極めて困難であり,被告に過失はない。 3争点(3)(違法性の欠如)について【被告の主張】(1)特許権侵害訴訟の提起は,特許権者が,事実的・法律的根拠を欠くことを知りながら,又は,特許権者として,特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば,事実的・法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が特許権侵害訴訟という裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限って違法となるものと解すべきである(最高裁判所昭和63年1月26日判決 。そして,特許権者が競業者の取引先に対 )する訴え提起の前提としてなす警告も,それ自体が競業者の営業上の信用を害する行為でもあることからすれば,訴え提起と同様に,特許権者が,事実的・法律的根拠を欠くことを知りながら,又は,特許権者として,特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば,事実的・法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて警告をなした場合には,競業者の営業上の信用を害する虚偽事実の告知又は流布として違法となると解すべきであるものの,そうでない場合には,このような警告行為は,特許権者による特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたものというべきであり,正当行為として,違法性を阻却されるものと解すべきである。 (2)本件について検討するに,争点(2)に関する被告の主張のとおり,特許権者である被告が,被告方法特許権及び被告物質特許権の行使につき,事実的・法律的根拠を欠くことを知っていたことはなく,また,特許権者として,特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば,事実的・法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて警告をしたこともない。 さらに,被告は,被告の警告にもかかわらず原告製剤の取扱いを中止しなかった卸売業者に対して,被告物質特許権に基づき原告製剤の販売中止を求める仮処分申立てを実際に行っているのであり(前提事実(5)イ(ア)a ,)被告の警告状の送付及び取扱停止の要請が,これら法的手続を前提としたものであり,その目的がもっぱら被告の特許権の正当な権利行使にあったことは明らかである。 以上に照らせば,被告の医薬品卸売業者に対する警告状の送付や口頭での原告製剤の取扱中止要請は,被告の有する特許権の正当な権利行使の一環としてなされたものであることが明らかであり,正当な権利行使として違法性がない。 【原告らの主張】(1)特許権者による虚偽事実の告知・流布が,正当な権利行使の一環としてなされたかどうかは,当該警告文書の形式・文面のみならず,当該警告に至るまでの競業者との交渉の経緯,警告文書等の配布時期・期間,配布先の数・範囲,警告文書等の配布先である取引先の業種・事業内容,事業規模,競業者との関係・取引態様,当該侵害被疑製品への関与の態様,特許侵害争訟への対応能力,警告文書等の配布への当該取引先の対応,その後の特許権者及び当該取引先の行動等の,諸般の事情を総合して判断すべきである。 (2)この点被告は,平成3年12月から平成17年1月まで,業界紙等に警告文等を掲載する際にも,卸売業者へ文書を送付する際にも,訴訟を提起する際にも,事前に原告らに対し協議や交渉を持ちかけたことは一切なく,常に突然に行為に及んでいた。被告の営業誹謗行為は,平成3年12月から平成17年1月まで,長期,大量,広範囲に行われ,その対象も,卸売業者から個人の診療所の医師にまで及んでいた。さらに,被告は,原告らと協議・, , 交渉する場を設けることすらなく 原告製剤の単なる流通に関わるにすぎず特許権侵害の有無等を自ら判断することは困難な卸売業者を相手に,いきなり仮処分を申し立てた。かかる被告の行為は,明らかに社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容・態様であり,正当な権利行使の範囲をはるかに超えているものである。 したがって,被告の不正競争行為(営業誹謗行為)は,正当な権利行使の一環といえるものでは到底なく,違法性が阻却されることはあり得ない。 4争点(4)(消滅時効)について【被告の主張】(1)不正競争行為に基づく損害賠償請求権は 「損害及び加害者を知った時」 ,から3年を経過した時点をもって,時効により消滅する(民法724条 。)同条の「損害及び加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味すると解されており(最高裁判所昭和48年11月16日判決 ,)また,加害行為の違法性の認識の程度については,営業誹謗行為に基づく損害賠償請求権の場合には,加害行為の違法性を確定的に知ることを要するものではなく,被害者にその意思があれば加害者に対し損害賠償等が請求できる程度に違法である蓋然性を認識すればよいものとされている。そして,損害の認識の程度についても,被害者が不法行為に基づく損害の発生を知った以上,当時その損害との関連において当然その発生を予見することが可能で, , あったものについては すべて被害者においてその認識があったものとして民法724条所定の消滅時効は前記損害の発生を知った時から進行を始めると解されている(最高裁判所昭和43年6月28日判決 。)したがって,本件でも,原告らが,その主張に係る被告の特許権に関する営業誹謗行為の違法性を確定的に認識することは不要であり,権利行使をしようと思えばそれが可能な程度に被告の行為が違法であるとの蓋然性及び損害を認識した時点から消滅時効期間は進行する。 (2)特許権侵害に関する営業誹謗行為の関係について本件において,原告らが虚偽の事実であると主張する特許権に関する不正競争行為は,別表9の「被告の主張」欄記載のとおり,①被告方法特許権のみに関するもの,②被告方法特許権及び被告物質特許権の双方に関するものに分類可能である。 ア被告方法特許権のみに関する営業誹謗行為(①)に基づく請求について特許権侵害に関する営業誹謗行為については,原告らは,平成4年以来一貫して被告のいかなる特許権をも侵害していないとの立場を貫いており,その旨を医師,医薬品卸売業者等の顧客に対して表明し続けていた。 そして,原告らは,裁判手続においても,被告方法特許権については平成5年2月5日の時点で,原告フジモトDが使用している方法は被告方法発明の技術的範囲に含まれない(すなわち同特許権を侵害しない)と主張していた。この事実からすれば,原告らが被告の各行為を認識した時点,あるいは遅くとも上記のとおり各裁判手続の中で被告方法特許権を侵害しないと主張した時点において,原告らは被告による上記告知・流布行為が虚偽の営業誹謗行為であるという蓋然性を当然に認識しており,不正競争防止法に基づく損害賠償請求をすることも十分可能だったのであるから,上記の時点をもって消滅時効の起算点とすべきである。 また,仮に上記の時点が消滅時効の起算点とならないとしても,被告方法特許権については,平成11年7月16日の第1次訴訟の最高裁判決によって,以後被告の同特許権によって原告製剤の製造販売が差し止められたり,薬価基準収載の削除を余儀なくされる可能性は消滅したのであり,これ以後は原告らが本件請求を行うことに何らの障害はなかった。したがって,遅くとも平成11年7月16日の翌日である同月17日が消滅時効の起算点となり,平成14年7月16日の経過をもって消滅時効が完成した。 これに対し原告らは,被告が,前記最高裁判決の確定後に,被告方法特許権の侵害に基づく損害賠償請求訴訟(第2次訴訟)を行ったことをもって消滅時効が進行しないなどと主張するが,被告方法特許権の侵害に基づき被告がなした損害賠償請求訴訟の提起が,本件訴訟に係る請求の消滅時効の中断事由に該当しないことは明白である。 イ被告方法特許権及び被告物質特許権の双方に関する営業誹謗行為(②)に関する請求についてこれらの請求については,被告方法特許権のみならず,被告物質特許権についても特許権侵害の告知・流布が虚偽であることの蓋然性を認識した時点から消滅時効が進行するものと考えられる。 原告らは,①被告が昭和薬品に対して被告物質特許権の侵害に基づく原告製剤の販売差止めを求めた仮処分手続において,原告ら自身が実質的に対応する中で,平成6年8月16日には,既に被告物質特許の無効を主張しており,②平成7年3月28日には,同手続の中で原告製剤は被告物質発明の技術的範囲に属さない旨主張している。さらに,③平成8年7月5日には,被告物質特許の無効審判請求を行っている。そして,④平成11年7月15日,上記無効審判請求について東京高等裁判所が,同審判請求は成り立たないとした特許庁の審決を取り消す旨の第1次審決取消訴訟判決を言い渡し,同判決はそのまま確定し,当該判断は特許庁を拘束することとなった。 したがって,上記の各時点,いかに遅くとも平成11年7月15日の第1次審決取消訴訟判決の時点までには,原告らは,被告物質特許権についての本件請求をすることは十分に可能であったから,これよりも遅い前記アの時点が消滅時効の起算日となり,別表1のすべての行為に基づく損害, 。 賠償請求権は 平成14年7月16日の経過をもって消滅時効が完成した(3)品質に関する営業誹謗行為の関係についてこれについては,原告らが被告の行為を認識した時点で,損害及び加害者を知ったことは明らかであるから,原告らがこれらの行為をそれぞれ認識した時点が消滅時効の起算点となる。 しかるところ,別表2記載の主張に係る行為のうち,最も直近のものですら平成7年4月5日であるから,本訴が提起された平成17年3月16日の時点においては,同表記載の主張に係る行為を理由とする請求すべてにつき消滅時効が完成している。 (4)原告らは,被告による告知行為のすべてが一連の継続的行為であることを前提に,消滅時効の起算点を原告らと被告との間のすべての特許権侵害紛争が終結した平成17年1月28日の翌日であると主張する。 しかしまず,争点(1)に関する被告の主張のとおり,被告による行為のすべてを一連の継続的行為であると把握することは失当である。 また,仮に被告の行為が継続的不正競争行為だとしても,それによって発生したとされる原告製剤の販売減少なる損害は,それら原因行為が行われる, , 都度に日々刻々と発生したはずであり 日々消滅時効期間が起算されるからやはり原告らの主張は失当である。 (5)被告は,平成17年11月14日の第4回弁論準備手続期日において,前記消滅時効を援用するとの意思表示をした。 【原告らの主張】消滅時効の完成に関する被告の主張は否認する。 (1)本件で原告らが被告の不正競争行為として主張しているのは,被告製剤の市場における優位性確保を図るという営業目的達成のために実施された互いに密接に関連した一連の行為の総体であり,それらが全体として継続的不正競争行為を構成する旨主張しているものである。それら行為を個々別個のものとして捉えるべきものではない。 そして,かかる行為が終了したのは,原告らと被告との間のすべての紛争・係争状態が終了した平成17年1月28日である。よって,このときに被告による不正競争行為が終了し,原告らは,被告による一連の行為の違法性及び損害の発生を知ったものである。したがって,本件損害賠償請求権の消滅時効の起算点は平成17年1月28日の翌日であり,本件請求権の消滅時効は完成していない。 もっとも,被告の主張に沿って,消滅時効の起算点を個々に考えたとしても,以下のとおり,いずれも消滅時効は完成していない。 (2)被告方法特許権関係について被告方法特許権に関する被告の営業誹謗行為は,原告らが同特許権を侵害していることを前提に「特許権侵害をしているから原告製剤を差し止められる,薬価基準収載からも削除される 」という内容を告知したというもので 。 ある。そして,薬価基準収載削除の点については平成11年6月7日の大阪地方裁判所による事情変更による保全命令取消決定により解決されたものの,特許権侵害の有無の点については,第2次訴訟まで解決されなかったものであり,それまでは,原告らが特許権侵害不存在を理由に,被告の行為は不正競争行為であるとして損害賠償請求権を行使することは極めて困難であった。当該請求権が行使できるようになったのは,第2次訴訟において,平成4年12月22日以降の原告らの権利侵害が否定された時点以降である。 したがって,被告方法特許権関係での営業誹謗行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は,第2次訴訟の控訴審判決が確定した平成16年4月23日の翌日である。よって,当該請求権の消滅時効は完成していない。 (3)被告物質特許権関係について被告物質特許権については,平成16年12月20日に同特許の無効が確定した時に,原告らは被告の行為の違法性を知ったものであり,この翌日が消滅時効の起算点である。 確かに,被告物質特許について,原告らは,同特許が問題となった訴訟手続等でその無効を主張し続けていたが,本件の場合,仮処分事件とはいえ,平成7年10月31日に名古屋地方裁判所で同特許が有効であることを前提とした仮処分決定がされた。かかる裁判所の判断が示されている状態において,原告らが被告に対し 「被告物質特許は無効であり,有効であることを ,前提としてなされた被告の行為は虚偽事実の告知・流布である 」と主張し。 て損害賠償請求権を行使することなど不可能である。原告らは,被告物質特許の無効が確定した時点で初めて権利行使ができるようになったものである。 したがって,被告物質特許権関係での営業誹謗行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は完成していない。 (4)品質関係について品質に関する不正競争行為については,新しい薬剤が軌道に乗るか否か販促活動において最も重要な初期の段階に,原告製剤に決定的ダメージを与える手段として,次々と訴訟等を提起するのと並行して補助的営業活動として行われた行為であり,上記特許権に関する不正競争行為と密接不可分に関係しており個別に捉えることのできない行為である。 したがって,消滅時効の起算点を単独で捉えることはできない。 5争点(5)(不正競争行為に基づく損害額)について【原告らの主張】(1)逸失利益原告らは,被告の不正競争行為により,原告製剤につき本来得られるはずであった利益を現実には得ることができなかった。 ア原告製剤は,被告製剤の後発医薬品ではあるものの,ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚組織抽出液製剤市場においては,平成4年の原告製剤, , の発売開始から平成11年まで 事実上原告製剤と被告製剤以外存在せずまた,両医薬品は同効能・同機能・同剤形であり,かつ,平成4年の発売時から平成8年3月まで同薬価であった。したがって,両医薬品は,どちらかが増えればどちらかが減るという市場を奪い合う競合関係にあった。 原告製剤は,当初の段階では順調に市場占有率を拡大していたが,特に平成7年11月の名古屋地裁仮処分決定に基づく執行官保管の仮処分の執行後は,順調な一般の医療用医薬品のたどるライフサイクルに戻ることは。, 。 できなかった その要因は 被告の継続的不正競争行為によるものであるそして,以後一度も回復することなく,本来なら医薬品として当然たどるべき右肩上がりの成長期及びピーク期を経ることもなく売上げが減少した。 本件では,不正競争行為前の原告らの営業状況,売上高・利益の推移から,違反行為がないと仮定した場合に想定される売上量やマーケットシェア(市場占有率)を推測し,その想定マーケットシェアから売上高・利益と,違反行為後の原告らの現実の売上高・利益とを比較することによって逸失利益を算定するべきであり,この算定方法が違反行為の前後の営業状況等を比較するものであって,前後基準といわれるものである。 かかる原告らの主張と同様の分析が,マーケティング分野の専門家によってもなされている。すなわち,その鑑定結果(甲133。以下「C見解書」という )によると,原告製剤と被告製剤は,どちらかが増えればど 。 ちらかが減るという極めて強いシェアの奪い合いがある競合関係にあること,原告製剤は,一般の医療用医薬品がたどるライフサイクルを経ず,ある時期を境に一気に衰退していること,すなわち,被告による前記仮処分の執行後の平成7年11月から平成8年2月に,原告製品の販売数量に急速な落ち込みがあり,それ以降健全な競争状態では考えられない大きなシェアの波動があることなどが分析されている。そして,同鑑定によれば,原告らの逸失利益は,最低でも約31億0500万円,最大では約67億3000万円に上り,中間値として約47億8500万円が適当であるとされている。 イ仮にそうでないとしても,次のとおり主張する。 原告らにおいては,原告製剤につき,当初の売上目標を達成することができず 結果的に約1億3000万本の売上げが減少することになった 甲 , (144 。被告製剤1本当たりの利益額が56.84円を上回るものであ ), (), ることは 被告自身が認めていることであるところ 甲12740頁市場において原告製剤と被告製剤以外存在せず,薬価も同額であったことにかんがみても,原告製剤1本当たりの利益額は被告製剤と同額であるといえる。したがって,原告らの逸失利益は,73億8920万円(130,000,000×56.84=7,389,200,000)を下らないものである。 確かに,目標が達成できなかった約73億円という額すべてが,被告による不正競争行為と相当因果関係にある損害額とまでは必ずしもいえないかも知れない。しかし,原告らが,全国規模の販売体制を整え,原告製剤を次世代の原告らの主力製品として社をあげて拡販に取り組んでいたこと,前記仮処分の執行以前の平成6年から平成7年は売上げを倍増させ,ほぼ目標数量を達成していたこと等にかんがみると,かかる目標未達成部分の少なくとも半分は,被告による不正競争行為によって生じた逸失利益といえるものである。 よって,原告らの損害額は30億円を下らないものである。この額は,上記アで述べた市場におけるシェア分析によって算定された額ともほぼ一致しており,極めて妥当な数字である。 (2)無形損害原告らは,被告の長期間にわたる多数の虚偽事実の告知・流布により,製薬企業としての信用を著しく毀損された。 よって,原告らは,営業活動全般について信用毀損による無形損害を被ったものであり,その損害額は10億円を下らない。 【被告の主張】(1)逸失利益についてア原告らの主張アについて(ア)仮に原告ら主張に係る包括的な行為群によって原告らに逸失利益の損害が生じていたのであれば,少なくとも,原告らが具体的に主張している個別行為が集中している時期に相前後して原告製剤の数量シェアが減少しているといった事実関係が窺われるはずである。ところが,原告ら主張に係る個々個別の行為が集中している平成6年から平成7年10月までの時期と,原告らが,原告製剤の数量シェアが減少したことを根拠に 不健全な競合状況 なるものが存在したと主張されている時期 平 「」 (成7年11月以降)は全く一致しない。 したがって,原告らの主張する逸失利益なるものは発生していないと言わざるを得ない。 (イ)原告らが依拠するC見解書(甲133)では,原告製剤と被告製剤が同効能・同機能・同剤形・同薬価であることを根拠に,原告製剤のあるべき数量シェアが最低でも35%に到達したはずであると分析しているが,以下のとおりその分析は不合理である。 aそのような具体的な数字が導かれる根拠は全く示されていない。 b一般に,我が国における平成5年度から平成14年度における後発医薬品のシェアは,後発医薬品に対する不安や先発医薬品との差異から,数量ベースでせいぜい10~12%程度にすぎない。単に被告製剤と同等であるということを根拠に,原告製剤が一般的な後発医薬品と比較して極端に高い数量シェアを獲得できたとするC見解書の試算は極めて不合理である。 c後発医薬品の数量シェアを試算する際には,当然,先発医薬品メーカーの営業力と後発医薬品メーカーの営業力の差異も考慮されなければならないが,被告には,常に原告らの約1.8倍から約3.2倍の人数のMRがおり,支店・営業所も原告らより整備されていた。しかるにC見解書は,数量シェアの増減に直結する販売体制を何ら考慮しておらず,不合理である。 dそもそも原告らには被告の数分の1程度の人数のMRしかいなかったのであるが,原告らは,平成10年12月にハンガリーのキノイン社からの導入品であるパーキンソン病治療剤「エフピー錠」を上市したのを契機に,その営業力を原告製剤からエフピー錠にシフトさせたから,C見解書が分析しているような,原告製剤の数量シェアが平成11年まで上昇したとは到底考えられないし,その後,35~45%という高い数量シェアを維持したと考えることも不可能である。 e原告製剤の数量シェアを試算する際には,平成9年9月に被告製剤の2次後発医薬品である「ナブトピン注」が,平成11年12月に3次後発医薬品として「ノルポート注」がそれぞれ発売されたことも考慮されなければならないが,C見解書の分析は,この点を全く考慮していない。 (ウ)C見解書では 「相関分析」の手法により,原告製剤と被告製剤の ,間に強い競合関係があったことを分析の根拠としているが,このような競合関係の有無・程度は,被告の行為と原告製剤の販売数量との関係と, , いう 本来証明すべき命題と直接関係する要素を分析したものではなく意味がない。その他,C見解書の相関分析に対しては,数理統計学の専門家より,方法論としても,その使用法においても誤りであるとの指摘がなされている。 (エ)C見解書は,プロダクトライフサイクルの成長曲線が原告製剤にも妥当するとの前提に立って,原告製剤と被告製剤との間に,何らかの不健全な競争があった可能性が高いと分析する。 しかし,理想的なプロダクトライフサイクルの成長曲線は,すべての製品に当てはまるわけではなく,むしろ,ほとんどの製品が成長期にすら至らず,導入期の段階で販売中止となってしまうのである。また,プロダクトライフサイクルの考え方は,製品の売上げと利益の変遷を4つの段階で説明し,それぞれの段階ごとのマーケティング戦略を明らかにするモデルのことであり,2つの製剤間に不健全な競合関係があったかどうかを調べる手法ではなく,C見解書はその使用法でも誤っている。 (オ)C見解書は,原告製剤の償却前粗利益率を50%,60%,70%と想定しているが,逸失利益の算定は,原告製剤1本当たりの実際の利益率に基づいて行われるべきであるのは当然であり,この点でもC見解書の分析には理由がない。 イ原告らの主張イについて(ア)原告らが立てた原告製剤の売上目標は,原告らの製造販売する胃炎・消化性潰瘍治療剤である「カイロック」の売上実績を参照して,年ごとの伸び率を算出して予測したというものである。 しかし,原告製剤がカイロックと同じような売上推移をたどるはずだったという根拠はどこにもない。 また,この売上予測が達成されたとすると,原告製剤は,平成10年度から平成14年度で約47%から50%程度のシェアをとれたことになるが,原告製剤がそのような高い数量シェアを獲得できるまでに売上げを伸ばしたという予測はあまりにも現実離れしている。さらに,被告が昭和63年7月に発売した「ノイロトロピン錠」の影響により,被告製剤を含めた注射剤市場全体が縮小傾向にある中で,原告製剤だけが売上げを伸ばすことができたと考えるのも不合理である。 (イ)また,原告らは,何らの資料を提出せずに,原告製剤1本当たりの利益額が,被告製剤のそれと同額の56.84円であるとするが,会社の利益率はそれぞれ別々であるし,被告製剤と原告製剤では製造量が異なるので,量産効果により被告製剤のほうが製造コストが小さくなり,その結果,単位数量当たりの利益額が大きくなることは明らかであるから,原告製剤1本当たりの利益額は全く証明されていない。 (ウ)以上より,原告らの主張イも不合理である。 (2)無形損害について虚偽事実の告知・流布による無形損害が認められるには,当該告知によって原告らの信用が毀損されたことの具体的事実と,それによって原告らに実際に生じた損害額の主張立証がなされなければならないことは当然である。 しかしながら,原告らは抽象的な主張をするのみで,具体的に信用が毀損されたことなどにつき一切主張立証をしていない。 6争点(6)(不法行為の成否)について【原告らの主張】(1)争点(1)において不正競争行為として主張した営業誹謗行為が不法行為を, , 構成することは 争点(1)ないし(3)に関する原告らの主張のとおりであるがこのほか,被告が被告方法特許権及び被告物質特許権の侵害を主張して種々の訴訟を提起・追行し,仮処分を申し立て,刑事告訴を行ったことは,上記営業誹謗行為とともに,以下のとおり,一連の包括的・継続的な不法行為を構成する。 すなわち,被告による訴えの提起等は,被告が有する特許権を行使すると。, , いう外形をとっている しかし 特許権者の競争相手方に対する権利行使はその法的手続を執ったという事実のみで,顧客・購入者においてある種の買い控えの現象が生ずるものである。これを単なる反射的効果とのみ評価するのは誤りであり,権利行使の相手方にとって営業上の損害の発生が不可避であるので,特許権に基づく権利行使としての訴訟行為であっても,その行為の背後に営業的利用を第一義としている場合はもちろんのこと,仮にそれを第二義的若しくは補助的動機としている場合でも,特許自体が無効であったり,権利範囲に抵触しない等の理由で敗訴した場合には,不法行為に該当すると構成するべきものである。 本件の場合は,被告による訴えの提起等は,権利行使の形式をとってはいるが,市場における被告製剤の独占販売を維持継続するための経営戦略として,原告製剤について,その供給が不安定で違法なものと顧客に観念させるために係争状態を創出・維持すること自体が第一義的なもので,仮にそうでないとしても,少なくとも第二義的には営業的利用を意図していたものである。したがって,別表4「係争事件一覧表」に記載されたうちの被告による, , 訴えの提起・追行・不服申立て 仮処分の申立て・追行・執行・不服申立て刑事告訴は,個々の訴訟等自体が不当訴訟であるのみならず,被告が前記のような虚偽の内容の告知・流布を行ったことも併せて,一体として継続的不法行為を構成する。 (2)また数々の訴訟や仮処分を個々的に見ても,それら訴えの提起や仮処分の申立て及び執行は,何ら確たる証拠もないにもかかわらず,安易・薄弱な推測・推理に基づいてなされたもので,かかる被告の訴えの提起等は,市場における優位的地位の確保を目的にしており,裁判制度の趣旨目的に照らして,著しく相当性を欠くものであり,不法行為を構成する(以下,事件の符号は別表4「係争事件一覧表」の番号である 【ただし,丸付数字を<>に 。 置き換えた。。】)なお,個々の事件についての詳細は,別表3のとおりである。 ア不正競争防止法に基づく差止請求<1>は,平成3年12月に提起された仮処分命令申立事件で,<4>-2はその抗告審である。原告製剤が未だ市場に出る前の段階で,厚生省の製造承認を差し止めようと計画されたもので,被告の目的が被告製剤が有している独占的販売シェアを確保することであることを仮処分命令申立書の中で被告は明らかにしており,当初から不法行為の故意の存在を示すものである。 イ被告方法特許権に基づく差止請求(第1次訴訟), , <2>及び<3>とこれらの上訴審である<9>-2 <10>-2及び<23>-1は原告フジモトDの使用する確認試験方法は,被告方法特許権を侵害するものでないこと,及び,仮に侵害する場合であっても,本来原告製剤の製造販売行為の差止めや薬価基準収載申請の取下げを請求する権利はないないにもかかわらず,裁判所を誤導するために,原告フジモトDに対してされた訴訟提起及び仮処分申立てである。 ウ被告方法特許権に基づく損害賠償請求(第2次訴訟)<27>及び<30>-2は,被告方法特許権の侵害を理由に被告が原告らに対して提起した約30億円の損害賠償請求訴訟及びその上訴審である。これらは,第1次訴訟の最高裁判決の精神から逸脱した極めて不当訴訟性の強いものである。まさにその結果の如何ではなく,原告製剤をめぐり,原告らと被告との間に係争状態があること自体を市場に知らしむべくそこに目的を求めた不当訴訟というべきものである。 エ被告物質特許権に基づく差止請求<5>,<6>,<7>及び<8>とこれらの上訴審である<12>,<13>-2,<15>-2,<16>-2及び<17>は,被告物質特許権に基づく訴訟及び仮処分命令申立事件である。これらの請求の根拠とされた被告物質特許は,後に無効となるものであった。また,原告製剤の卸売業者に対して申し立てられた<5>,<6>及び<7>の事件は,明らかな営業妨害を意図する露骨な不当訴訟である。原告らは,これら取引先に懇請して,訴訟上の防御自体を事実上引き受けてこれら不当訴訟に立ち向かうこととなった。特に,標的にされたこれらの会社は,当時,株式公開手続や会社合併手続等の過程であり,被告はそのことを知った上で,あえて無効な特許を根拠に訴えを起こしたものである。被告のこれらの訴訟行為は,相手方を困惑させることを殊更に意図した極めて悪質なものである。その結果,原告らの営業的損害は計り知れないものであり,最も重要なマーケティングの時期に原告らは原告製剤の市場浸透を果たすことが十分にはできなかった。 オ仮処分の執行(ア)名古屋地裁仮処分決定の執行<11>-2は,被告が,平成7年11月10日及び同月13日に,無効な被告物質特許権に基づいて得た名古屋地裁仮処分決定に基づいて,昭和薬品の小牧配送センター及び同本社の原告製剤に対して行った執行官保管仮処分の執行である。 (イ)大阪高裁仮処分決定の執行<21>-3は,被告が,平成9年11月28日に,原告フジモトDは被告方法発明を実施しておらず,また本来被告方法特許権によっては原告製剤の製造販売自体の差止請求権がないにもかかわらず,大阪高裁仮処分決定に基づいて,被告が原告フジモトDの彦根工場の原告製剤に対して執行官保管の仮処分を執行したものである。 カ刑事告訴<22>-1は,被告が,平成10年4月24日,原告フジモトD及びその。 , 代表者に対して行った刑事告訴である これについては不起訴となったが原告フジモトDの存続をすら破壊することを意図した露骨な不法行為である。 【被告の主張】(1)原告らが争点(1)において不正競争行為として主張した営業誹謗行為が不法行為を構成しないことは,争点(1)ないし(3)に関する被告の主張のとおりである。 。 (2)また原告らが主張する被告による訴えの提起等も不法行為を構成しないア不正競争防止法に基づく差止請求について不正競争防止法に基づく被告製剤の周知商標である「ノイロトこれは,ロピン」を使用した原告製剤の有効成分表示「ノイロトロピン単位」の使用差止め等を求めた仮処分申立てであり,同表示を原告フジモトDが無断使用し,原告製剤と被告製剤との間で品質誤認が生じるおそれがあったた, 。 め 被告が原告フジモトDに対してその使用差止め等を求めたものであるその結果,原告フジモトDがその名称の使用を中止した上,将来にわたって使用しない旨表明したために却下されたにすぎない。 イ被告方法特許権に基づく訴訟等及び被告物質特許権に基づく訴訟等について民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,その訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という )が事実的・。 法律的根拠を欠くものである上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる(最高裁判所昭和63年1月26日判決 。)この要件に照らすと,争点(2)(故意・過失の有無)及び(3)(正当な権利行使)に関する被告の主張のとおり,被告方法特許権に基づく訴訟等及び被告物質特許権に基づく訴訟等は,不法行為を構成しない。 ウ仮処分の執行について争点(2)(故意・過失の有無)に関する被告の主張のとおり,被告は,被告物質特許が有効であると信じたことについて過失がなく,また被告方法特許権に基づいて原告製剤の製造販売等の差止めを請求し得ると信じることについて過失がなかったから,名古屋地裁仮処分決定及び大阪高裁仮処分決定を執行したことは不法行為を構成しない。 なお,仮処分決定が異議若しくは上訴手続において取り消された場合,あるいは,本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され,その判決が確定した場合には特別の事情のない限り過失の存在が推認されるというのが最高裁判例(最高裁判所昭和43年12月24日判決)の立場であるが,本件においては,①前記仮処分決定は昭和薬品を債務者としたものであって原告らを債務者としたものではないこと,②前記仮処分決定は債権者と債務者の双方審尋において債務者側の十分な主張・立証を踏まえて発令されたものであること,③最高裁判例が前提としている,仮処分決定の取消しや本案訴訟における債権者の敗訴判決の確定といった事実が存在しないことから,過失の存在は推認されない。 エ刑事告訴について特許権侵害の罪での刑事告訴については,大阪高等裁判所によって原告フジモトDが被告方法特許権を侵害している事実が認定され,原告製剤の製造販売の差止め等を命ずる判決及び仮処分決定がなされたにもかかわらず,原告らが引き続き原告製剤の製造販売を継続し続けた結果,上記大阪高裁判決及び仮処分決定の趣旨にある所期の民事上の救済が得られなかった。そのため被告は,前記民事上の救済を実効性あらしめるべく特許権侵害罪で刑事告訴したものであり,同刑事告訴に違法性がないことは明らかである。 , ,「」 オその他 各訴訟等に対する被告の主張は 別表3の 被告の認否・反論欄のとおりである。 7争点(7)(消滅時効)について【被告の主張】争点(4)(消滅時効)に関する被告の主張と同旨である。 また,仮処分の執行に基づく損害賠償請求権についても同様の理由から消滅時効が成立した。被告は,この消滅時効を平成18年7月14日の第10回弁論準備手続期日において援用した。 【原告らの主張】争点(4)(消滅時効)に関する原告らの主張と同旨である。 8争点(8)(不法行為に基づく損害額)について【原告らの主張】(1)被告の一連の継続的不法行為によって原告らが受けた損害は 争点(5) 不,(正競争行為に基づく損害額)に関する原告ら主張のもの(逸失利益及び無形損害)のほか,一連の訴訟関連費用がある。 すなわち,原告らは,平成3年12月から平成17年1月までの長期間にわたり,被告が提起した複数の訴訟に対応せざるを得ず,そのために弁護士・弁理士その他専門家に対する多額の訴訟関連費用(着手金,報酬,日当,交通費,書面作成費等)が発生した。その額は,2億円を下らない。したがって,原告らは,被告の一連の継続的不法行為により,少なくとも上記費用相当の損害を被った。 (2)また原告らは,被告による違法な仮処分の執行により,次のとおりの損害を被った。 ア名古屋地裁仮処分決定の執行に基づく損害(ア)直接損害被告は,同仮処分決定に基づき,原告製剤につき,①平成7年11月10日に昭和薬品の小牧配送センターにおいて50アンプル・23箱及び200アンプル・116箱を,②同月13日に昭和薬品の名古屋北支店において200アンプル・2箱及び200アンプル・1箱の,計2万4950本の執行官保管の仮処分の執行をした。そのため,原告らは,本来販売されるはずであったこれらの原告製剤を販売することができなくなり,結局,執行解除後,当該原告製剤は原告らへ返品され廃棄された。なお,原告らと卸売業者との間では,原告製剤につき,実際に卸売業者から医療機関へ売却された後に,卸売業者から原告らにその分の代。, , 金が支払われることになっていた そのため 上記仮処分の執行により昭和薬品のもとにあった原告製剤は医療機関に販売することができず,原告らは当該原告製剤分の代金を回収することができなくなった。よって,原告らが上記仮処分の執行の直接の損害を被ったものである。そして,その額は,631万2350円(平成7年当時の薬価253円/本×24,950本=6,312,350円)である。 (イ)昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害, , 昭和薬品は 従前の取引関係から原告らの重要・有力卸売業者であり原告製剤の販売についても,大きな売上げが期待できる重点卸売業者の一つであったが,上記仮処分の執行により,原告製剤に関する原告らと昭和薬品との取引は,被告の不当執行以後平成9年2月に被告物質特許権の期限が満了するまでの間中止された。また,同月に取引が再開されて以降も,不当執行以前のような売上げの成長は見られず,頭打ち状態となった。これに基づく損害額は以下のとおりである。 a平成7年度(平成7年11月~平成8年3月)の損害不当執行直前の売上実績からすると,不当執行がなければ,原告は昭和薬品に対して平成7年11月以降も少なくとも月平均12万本は売り上げていたものであり,平成7年度の本来の売上数量は,実績の約80万本より55万本(平成7年11月:7万本,平成7年12月~平成8年3月:12万本/月×4か月=48万本計55万本)は多かったはずである。 したがって,平成7年度は,被告の不当執行により,原告らは,少なくとも55万本の売上減少に伴う逸失利益の損害を被ったものである。 b平成8年度,9年度の損害このように,原告らは,本来であれば平成7年度は少なくとも135万本(実績の80万本+売上減の55万本)を売り上げていたと推定されるものであり,平成6年度と比較して,約30万本の売上増であったはずである。そして,原告製剤が,製品としての成長期にあったことにかんがみると,平成8年度には,前年度に比べ少なくとも30万本の売上増を,平成9年度にもさらに前年対比で30万本の売上増を達成できていたと考えられる。したがって,平成8年度は165万本(平成7年度の売上げ135万本+30万本)の売上げが,平成9年度は195万本(平成8年度の売上げ165万本+30万本)の。,, 売上げが極めて高い確率で見込まれたものである しかし 実際には平成8年度は12万本の売上げで,少なくとも153万本の売上減少に伴う逸失利益の損害を,平成9年度は95万本の売上げで,少なくとも100万本の売上減少に伴う逸失利益の損害を被ったものである。 cよって,被告の不当執行により,前記期間の間,原告らが昭和薬品に対する売上減少となった数量は,少なくとも,総計308万本(平成7年度の55万本+平成8年度の153万本+平成9年度の100万本)に相当する。当該逸失利益の額は,諸費用等を控除した原告製剤1本当たりの利益額は56.84円を上回るものであるから,1億7506万7200円を下らないこととなり(308万本×56.84円/本 ,これが損害額となる。 )(ウ)他社との取引への影響により受けた損害被告の不当執行は,昭和薬品との取引のみならず,他の卸売業者との, 。, 取引にも大きな心理的影響を与え 購買意欲を一挙に減少させた 特に昭和薬品と時を同じくして販売差止め等の仮処分を申し立てられていた札幌のバレオ,広島の成和産業においては,この影響が明白に表れ,両社の原告製剤に対する販促活動は停滞した。その損害額は次のとおりである。 a平成7年度(平成8年1月~3月)の損害被告の不当執行による他の卸売業者へのマイナスの影響が,現実的な数字として顕著に表れてきたのは,平成8年1月ころからである。 平成7年4月~12月の原告製剤の売上数量は,月平均約92万本, ,, であるところ 平成8年1月~3月の実績数量は 1月は約54万本2月は61万本,3月は66万本と,平成7年4月~12月の月平均売上数に比べ,それぞれ38万本,31万本,26万本の計95万本の売上減少となっている。なお,この数字には,上記昭和薬品の平成8年1月~3月の売上減少分36万本も含まれるので,それを控除すると,他の卸売業者への売上減少分は,約59万本(95万本-36万本)となる。そして,原告製剤1本当たりの利益額は56.84円を上回るから,原告らの被った売上減少に伴う逸失利益の損害額は,3353万5600円(59万本×56.84円/本)を上回るものである。 b平成8年度の損害被告の不当執行により他の卸売業者へ与えた影響は,少なくとも翌年度の平成8年度においても継続していたと考えるのが相当であり,平成8年度における原告らの逸失利益の相当部分がこの不当執行を原因としているものといえる。 平成7年度の売上実績は,1008万7000本であるところ,上記のとおり,平成8年1月~3月において売上げが約95万本減少しているので,本来であれば,平成7年度の売上数量は,約1100万本であり,平成6年度の売上実績603万8170本に比べ約500万本売上げを増加させたことになる。そして,原告製剤が製品としての成長期にあることにかんがみると,平成8年度も平成7年度に比べ同程度の売上増加が見込まれたと考えるのが相当であり,平成8年度の売上げは,約1600万本(1100万本+500万本)となるはずであった。 しかし,実際には,平成8年度の売上げは,1363万6990本であり,約236万本売上げが減少している。なお,この数字には,上記昭和薬品の平成8年度の売上減少分153万本が含まれるので,それを控除すると,他の卸売業者の売上減少分は,約83万本(236万本-153万本)となる。もっとも,かかる売上減少において,被告の不当執行のみが原因しているとまでは断定できないが,少なくともその50%は,被告の不当執行による影響と考えるのが妥当である。よって,原告製剤の利益額は1本当たり56.84円を上回るものであるから,平成8年度における原告らが被った他の卸売業者との間の売上減少に伴う逸失利益の損害額は,2358万8600円(83万本×56.84円/本×0.5)を下らないものである。 c以上のとおり,原告らは,被告の不当執行により発生した昭和薬品以外の卸売業者との取引における売上減少により,平成8年1月から平成9年3月に限定しただけでも5712万4200円(33,535,600円+23,588,600円)を上回る損害を被ったものである。 (エ)無形損害原告らは,被告の不当執行により,昭和8年の創業より長年にかけて。, 築き上げてきた製薬企業としての名誉・信用を著しく毀損された また原告らは,その信用を回復するために,本来であれば新規開拓に従事すべき全国のMRや,工場に勤務する生産部の人員までをも動員して,全国の得意先や医療機関へ説明に回らざるを得なかった。その労力・出費は計り知れない。 かかる名誉・信用毀損に関する無形損害の額は,1億円を下らない。 (オ)まとめ以上のとおり,被告の不当執行に限定して原告らの損害額を算定した場合,原告らの損害は,3億3850万3750円(6,312,350円+175,067,200円+57,124,200円+1億円)を上回るものである。 イ大阪高裁仮処分決定の執行に基づく損害被告は,同仮処分決定に基づき,平成9年11月28日に,原告フジモトDの彦根工場において,原告製剤4万6650本の執行官保管の仮処分を執行した。そのため,原告らは,本来販売されるはずであったこれらの原告製剤を,被告の不法行為により販売することができなくなり,その分の損害を被った。そして,その額は,937万6650円(平成9年当時の薬価201円/本×46,650本=9,376,650円)である。 【被告の主張】原告ら主張の損害額は否認する。 , , (1)原告ら主張の損害のうち 逸失利益及び無形損害に関する被告の主張は争点(4)(不正競争行為に基づく損害額)に関する被告の主張のとおりである。 また,訴訟関係費用の点については,原告らが被告との訴訟によって負担した費用を被告が賠償しなければならないのは,被告が原告らを相手方として行った訴訟手続等の法的措置がいわゆる不当訴訟などの不法行為に該当する場合のみであるが,争点(6)(不法行為の成否)に関する被告の主張のとおり,被告が講じた法的措置で,いわゆる不当訴訟などとして不法行為に該当するものは皆無であるから,訴訟関係費用に関する原告らの主張も失当である。 (2)仮処分の執行に基づく損害に関する主張は次のとおりである。 ア名古屋地裁仮処分決定の執行に基づく損害について(ア)直接損害について原告らは,損害額を算定する際に原告製剤の薬価を基準としている。 しかし,そもそも薬価とは,保険請求の基準とされる医療用医薬品の公, 。 定価格のことであり 製薬企業が卸売業者に販売する際の価格ではない原告らが被った損害はせいぜい,執行官保管を受けた原告製剤を後に昭和薬品から買い戻した(返品に応じた)金額にとどまり,それは原告製剤の昭和薬品への販売価格にとどまる。そして,平成7年当時の原告藤本製薬の卸売業者への販売価格は,薬価の63.68%に当たる161円/本と計算されるので,最大でもこれを基準とすべきである。 (イ)昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害について昭和薬品に対する仮処分の執行がなされた平成7年11月から被告物質特許権の存続期間が満了した平成9年2月までの間(以下,この期間を「仮処分の執行期間」という,原告製剤について原告らと昭和薬 。)品との取引は中止された。しかしながら,昭和薬品が原告製剤を販売できなくなった分,代替手段として原告らのグループ企業である藤本医薬販売株式会社(以下「藤本医薬販売」という )やその他の小規模卸売 。 業者を通じて,昭和薬品の顧客に対して原告製剤を販売し(以下,かかる販売形態を「直販 ,その売上高を「直販数量」という,昭和薬品 」 。)の販売減少分に見合う売上げを確保していた。 この事実は,①仮処分の執行期間中において,昭和薬品の販売減少分に見合う数量だけ直販数量が増加していること,②原告ら自身も直販によって昭和薬品分の売上げを維持していたことを自認していること,③当時の被告の内部資料にも,直販が行われていた事実が記録されていたこと,④仮処分の執行期間が終了すると昭和薬品の売上げがすぐに従前の水準に回復しており,このような事態は原告製剤の顧客を被告製剤が奪ったのであれば考え難いこと,⑤仮処分の執行期間中,昭和薬品の元顧客で,被告製剤を新たに採用した医療機関はほぼ皆無であったこと,⑥仮処分の執行期間中,注射剤市場全体は急速に縮小していたにもかかわらず,原告製剤は順調に販売数量を増加させていること,⑦仮処分の執行直後に原告製剤の販売がいったん減少したように見えるのは,季節変動及び薬価改定前の買い控えによるものにすぎないことから明らかである。 したがって,昭和薬品が原告製剤の取扱いを中止したことによって原告らが逸失利益損害を被った事実はない。 また,原告らが主張する原告製剤1本当たりの利益額の主張も根拠がない。 (ウ)他社との取引への影響により受けた損害について昭和薬品に対する仮処分の執行を原因として,バレオや成和産業といった昭和薬品以外の卸売業者分の原告製剤の売上げが減少し,逸失利益損害なるものが発生したことはない。 すなわち,そもそも,原告製剤全体の売上げは仮処分の執行後も順調に推移しており,原告らが主張するように原告製剤の売上げが減少したことはない。このことは,①仮処分の執行後の平成7年12月に原告製剤の売上げは増加したこと,②仮処分の執行期間中,注射剤市場全体は急速に縮小していたにもかかわらず,原告製剤の販売数量は増加していること,③月別の数量シェアで見ても,仮処分の執行期間中の16か月間の原告製剤のシェアは,仮処分の執行前の12か月間のそれよりも上昇していること,④仮処分の執行によって被告製剤の売上げが増加したことはないこと,⑤バレオや成和産業といった卸売業者は,特定の医薬品について差止命令を受ければその取扱いを中止すれば足りるだけのことであり,他の卸売業者が販売差止めの仮処分命令を受けたのみでは,未だ自社が販売差止めを命ぜられていない状況にもかかわらず当該医薬品の取扱いを中止する理由はなく,またこれら卸売業者は,当時,被告が申し立てた仮処分手続において原告製剤は侵害品ではないと主張して争っていた上,その弁護士費用は原告らが負担していたのであり,昭和薬品に対する仮処分の執行期間中にそれら仮処分申立てについては却下決定がされたのであるから,仮処分の執行が原告製剤の取扱いを萎縮させたこともないことから明らかである。 また,平成8年1月以降の原告製剤の販売数量の変動も,仮処分の執行以外の原因に基づくものである。このことは,①医薬品の販売数量は月ごとに大きく変動すること,②平成8年1月の売上減少は平成7年12月の高い売上げの反動と見るべきこと,③毎年12月は高い売上げとなる反面,翌年1~3月は売上げが減少するというように,季節によって売上げが増減する(季節変動)こと,④平成8年4月には,ほぼ確実に原告製剤の薬価が大幅に切り下げられることが予想されていたから,その直前の平成8年1月~3月の薬価改定前には,薬価切り下げを見越して買い控えが生じることもあることから明らかである。 また,原告らが主張する原告製剤1本当たりの利益額の主張も根拠がない。 (エ)無形損害についておよそ無形損害が認められるためには,被告の行為によって原告らの信用が毀損されたことの具体的事実と,それにより原告らに実際に生じた損害額が明らかにされなければならないが,具体的に原告らの信用が毀損されたことは一切明らかにされていない。 通常,信用毀損の有無の判断においては,取引が中止されたかどうかが重要であるところ,上記のとおり,仮処分の執行を受けた昭和薬品の顧客も原告製剤を購入し続けたと考えられるばかりか,昭和薬品と同様に被告物質特許権に関して仮処分事件の当事者であったバレオや成和産業も一貫して原告製剤を取り扱い続けていたのであるから,原告らの信用は全く毀損されていない。 よって,昭和薬品に対する仮処分の執行により原告らに信用毀損の無形損害が生じたとの主張にも理由がない。 9争点(9)(不当利得の成否及び利得返還額)について【原告らの主張】被告は,前記不正競争行為・不法行為により,後発医薬品たる原告製剤の市場への進出を妨害して原告らに損失を与え,事実上先発医薬品である被告製剤の独占市場を形成して,争点(5)(不正競争行為に基づく損害額)及び争点(8)(不法行為に基づく損害額)で主張した原告らの損害額相当の利得を得たものである。 したがって,原告らは,被告に対し,不当利得に基づき,利得金30億円の支払を求める。 【被告の主張】そもそも被告の行為は不正競争行為・不法行為を構成しないものであるが,仮にこの点を措くとしても,被告が被告製剤の販売によって得た利益は,被告が正当な権原によって被告製剤を販売した結果として得られたものであるから,その利益あるいは原告らの利益の減少分なるものが「法律上の原因のない利得」とされる余地はない。すなわち,被告は,本来であれば販売が許されないような製品(特許権等により原告らが独占権を有しているような製品)を販売したわけではなく,販売することが法的に許された医薬品を販売して利益を得ているのである。したがって,被告が得た利益あるいは原告らの利益の減少分は「法律上の原因のない利得」などではなく,不当利得返還請求制度適用の前提に欠けている。 そして,一般に特許権等の知的財産権を侵害した場合には,実施料等権利者が受けるべき対価に相当する金額に限って不当利得返還請求が権利者に認められることがあるが,これは侵害者が本来権利者に支払うべき対価の支払を免れた点で法律上の原因に基づかない利得を得ているという考え方を前提とするものである。これに対し,本件で問題となっている営業誹謗行為の場合には,上記のような権利者が受けるべき対価を観念する余地がない。したがって,上記対価相当額の不当利得の存在も観念できず,本件ではこのような意味の不当利得も生じる余地はない。 第4当裁判所の判断1不正競争防止法に基づく請求について(1)争点(4)(消滅時効)について事案にかんがみ,まず抗弁に係る争点(4)について判断する。 ア不正競争防止法に基づく損害賠償請求権の消滅時効については,民法724条が適用されるが,同条が消滅時効の起算点を「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」としたのは,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者(又はその法定代理人)による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて,損害賠償請求権の行使を合理的に期待し得る時点を消滅時効の起算点としたものである。したがって 「損害及び加害者を,知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれを知った時を意味する(最高裁判所昭和48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照)が,これは,加害者に対して損害賠償請求権を行使することを合理的に期待し得る程度に,加害者の行為が違法であること(営業誹謗による不正競争行為の場合には,加害者の告知・流布行為が被害者の営業上の信用を害する虚偽のものであること)を認識することが必要であるとの趣旨をも包含するものと解するのが相当である。 イところで原告らは,その主張に係る被告の営業誹謗行為は,被告製剤の市場における優位性確保を図るという営業目的達成のために実施された一連の継続的行為の総体であるから,そのうちの最終の行為が終了した時点で原告らは一連の行為の違法性と損害の発生を知ったものであるとして,同時点(原告らの主張では原告らと被告との間のすべての係争状態が終了した平成17年1月28日の翌日)を消滅時効の起算点とすべきであると主張する。 しかし,原告らが主張する被告の各告知・流布行為は,それらが被告の営業目的達成のためになされた一連のものであるとしても,それぞれ時,場所,相手方及び態様を異にする別個の行為である。そして,それらの行為は,全体を合わせて初めて違法性を有するに至るというものではなく,その内容が虚偽である場合には,それぞれ個別に不正競争行為(営業誹謗行為)を構成するものである。そしてまた,それらの行為による売上げの減少や信用の毀損等の損害も,それらの行為がなされるごとに個別に発生するものであり,それらの各損害が積み重なって全体の損害に至るものなのであって,公害による身体の疾患・障害のような,個別の加害行為による個別の損害ということが観念し得ず,一連の加害行為の影響が積み重なって単一かつ不可分の損害が生じるというものではない。これらの点からすると,原告らの被告に対する損害賠償請求権は,被告の各行為ごとに個別に成立するのであって,その消滅時効も,各行為について原告らが「損害及び加害者を知った時」から個別に進行するものと解するのが相当である。 ウ特許権侵害に関する営業誹謗行為の関係について(ア)以下,被告の各行為について,原告らがどの時点で「損害及び加害者を知った」と認められるかを検討するが,本件で原告らが虚偽である, , と主張する点が 被告方法特許権と被告物質特許権とで異なることから被告の各告知・流布行為が,いずれの特許権の侵害を内容とするものかを分類しておくことが便宜である。そして,その分類結果は,別表9の「裁判所の認定」欄記載のとおりである(なお別表1中の1-25については,いずれの関係でも原告らが虚偽であると主張する内容が告知されたとは認められない。また原告らは,別表1で特定した以外にも被告による営業誹謗行為は継続的になされていたと主張する趣旨にも見受けられるが,別表1以外に営業誹謗行為がなされたことを認めるに足りる証拠はない。。)a同欄に「1A」と記載のあるものは,原告らの主張自体が,被告方法特許権のみに関連するとしているものである。 b同欄に「1B」と記載のあるものは,原告らの主張では被告方法特許権と被告物質特許権の双方に関するものとされているが,原告らの主張の根拠となる各証拠(別表1の「甲号証」欄記載の各書証)の記, 。 載によれば 被告方法特許権のみに関連すると認められるものであるすなわち,1-15,1-24及び1-92では,被告の従業員は被告の原告らに対する裁判の帰趨のみに言及しているところ,これらの行為の時点で被告が原告らに対して提起していた裁判は,被告方法特許権に基づくもののみであったから,これらの行為は被告方法特許権に関する内容のみを告知したものと認めるのが相当である。 また,1-22では,被告が同時期に福岡薬品に送付した内容証明郵便(甲101)の内容に照らして,被告が大森薬品に送付した内容証明郵便も被告方法特許権に関する内容のみであったと推認される。 c同欄に「2A」と記載のあるものは,被告方法特許権と被告物質特, 。 許権の双方に関連することにつき 当事者間に争いがないものであるd同欄に「2B」と記載のあるものは,原告らの主張の根拠となる各証拠(別表1の「甲号証」欄記載の各書証)の記載によれば,被告方法特許権と被告物質特許権の双方に関連すると認められるものである。 これらは,上記甲号証によって認められる被告による告知内容が,単に被告が提起していた裁判の帰趨に関するものだけでなく,原告らが被告の特許権を侵害している旨をも一般的に告知する内容となっていることから,そのような告知に接した者は,原告らが被告の有するいずれかの特許権を侵害していると理解するものと考えられる。そうだとすると,各行為の時点において提起されている裁判が被告方法特許権に基づくもののみであったとしても,なお各告知行為は,被告方法特許権と被告物質特許権の双方に関連すると認めるのが相当である。 eなお,原告らは,①被告は原告らに対して被告方法特許権や被告物質特許権の侵害を理由とする訴訟を提起し,公開法廷で審理され,訴訟記録が自由な閲覧に供されるその訴訟手続の中で,原告らがそれら被告の特許権を侵害する旨主張立証したこと,②被告が昭和薬品等の第三者を相手に原告製剤の販売の差止め等を求める仮処分を申し立て,その中で原告製剤の販売が被告物質特許権を侵害すると主張立証したことが営業誹謗行為に該当すると主張する。しかし,これら行為が外形的に不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に該当するとしても,後に2(3)で述べるのと同様の理由で違法性を有しないというべきであるから,これら行為については以下の検討の対象としない。 (イ)被告方法特許権のみに関連する行為(前記1A及び1B)の消滅時効についてaこの関係の行為について原告らが虚偽であると主張する点は,①原告フジモトDが実施している方法は被告方法発明の技術的範囲に属しない原告変更方法であるにもかかわらず,原告フジモトDが被告方法特許権を侵害していると告知した点,②被告方法発明は単純方法の発明であり,かかる発明に係る特許権に基づいては,原告製剤の製造販売自体を差し止めることはできないにもかかわらず,また薬価基準収載から削除されることもないにもかかわらず,あたかも原告らが特許権侵害をし,それにより原告製剤の製造販売ができなくなる旨告知・流布した点である。 ところで,上記①の点(原告フジモトDが被告方法特許権を侵害していること)については,原告らの主張によれば,原告フジモトDは遅くとも平成4年12月22日より後は,原告変更方法を実施して原告製剤を製造していたというのであるが,原告変更方法がLBTI等の阻害剤を第1次反応中に添加することをしていない点で,被告方法発明の技術的範囲に属しないことは明らかなところであり,この点については特段困難な法的評価を要するものではない。そうすると,実際に原告変更方法を社内で実施していたという原告らとしては,上記①のような被告の告知行為を認識すれば,直ちにそれが虚偽の事実を告知する違法な営業誹謗行為であり,それによって売上減少や信用毀損等の損害が生じることを認識することができたと認めるのが相当であるから,その時点において上記行為に係る損害賠償請求権を行使することを合理的に期待し得るものというべきである。 もっとも,これら被告の告知行為が行われた時点では,被告による第1次訴訟が既に提起されており,またそれが解決した後も第2次訴訟が提起されたことから,原告らとしてはそれら訴訟に対する応訴に精力を注いでいたものと思われる。しかし,それらの侵害訴訟において原告らが勝訴判決を得なければ,上記被告の行為が違法であることが確定しないわけでもなく,そのことを本件のような損害賠償請求訴訟で主張することができないというわけでもない。また,原告らが真に社内で原告変更方法を実施しているのであれば,被告の告知内容が虚偽であることを直ちに認識するはずであるし,またそのことを訴訟上立証するための証拠もすべて原告ら自身の手元に存するのであるから,それらの侵害訴訟において勝訴判決を得なければ,原告らが,被告の行為が違法であることを認識し,またその違法性を訴訟上立証することが困難であるというわけではない。さらに原告らと被告とは対等な立場の企業同士なのであるから,訴訟の提起を事実上困難ならしめる事情も特に窺われない。これらの諸点からすると,上記のような侵害訴訟が係属していたからといって,原告らにおいて,被告に対する本件損害賠償請求が事実上可能な状況の下になかったということはできない。 また,上記②の点(原告製剤の製造販売等ができなくなること)については,既に①の点で被告の告知・流布行為の虚偽性を認識した以上,②の点についての法解釈如何にかかわらず,②の点の虚偽性についても認識したものと認められるから,やはり上記①のような被告の告知・流布行為を認識した時点で損害賠償請求権を行使することを合理的に期待し得るものというべきである。 以上によれば,被告方法特許権のみに関連する行為についての消滅時効の起算点は,原告らが被告の各行為を認識するに至った時とするのが相当である。 bそうすると,別表1のうち被告方法特許権のみに関連する行為(前記1A及び1B)は,同別表の「甲号証」欄記載の各書証からして,いずれも同別表中の「不正競争行為(不法行為)時」欄記載のころに原告らも認識するに至ったものと認められるところ,その最も遅い時期のもので平成11年1月13日ころであるから(別表1の1-90 ,これらの被告の行為に基づく損害賠償請求権は,遅くともそれ )から3年が経過した平成14年1月13日の経過によりすべて消滅時効が完成し,被告が本件訴訟でそれを援用したことによって消滅したものというべきである。 (ウ)被告方法特許権と被告物質特許権の双方に関連する行為(前記2A及び2B)の消滅時効についてa別表1の「甲号証」欄記載の各書証によれば,これらの被告の行為は,いずれも特段特許権を特定することなく,原告らが被告の特許権を侵害している旨を告知するものと認められるが,このような場合には,原告らが被告方法特許権と被告物質特許権のいずれかでも侵害していれば,被告が告知した内容は虚偽とはいえない(なお,弁論の全趣旨によれば,原告らがこれら以外の被告の特許権を侵害することはなかったと認められる。したがって,これらの行為については, 。)被告の行為が原告らの営業上の信用を害する虚偽のものであることを原告らが認識したといえるためには,そのうちの被告方法特許権に関する告知内容が虚偽であると認識するだけでは足りず,被告物質特許権に関する告知内容をも虚偽であると認識したことが必要となる。 そして,原告らが,被告方法特許権に関する被告の告知内容が虚偽であると認識した時点は,前記のとおり原告らがそれら被告の行為を認識した時点であると認めるべきことは先に上記(イ)で説示したところと同様である。 そこで次に,原告らが,被告物質特許権に関する被告の告知内容が虚偽であると認識した時点について検討するが,本件で被告の告知内容が虚偽であるとして原告らが主張する点は,被告物質特許が無効であるにもかかわらず原告らが同特許権を侵害していると告知したという点であるから,結局,原告らが,被告に対する損害賠償請求権を行使することが合理的に期待し得る程度に被告物質特許が無効であることを認識したのはどの時点かということを検討することが必要である。 b後掲証拠によれば,原告フジモトDが請求した無効審判手続において被告物質特許が無効とされた理由は,概ね次のとおりのものであったと認められる。 (a)この無効審判請求において請求人である原告フジモトDが主張した無効理由の要旨は,訂正前の請求項5の発明の方法によってワクシニアウイルスを接種し,発痘させた動物組織,培養細胞若しくは培養組織より抽出した訂正前の請求項1の発明の生理活性物質は,A文献に記載された「抽出物Ⅱ」と同一の製法から得られる同一物質であるところ 上記のように抽出された生理活性物質はノ , ,「イロトロピン」として,鎮痛作用,抗アレルギー作用等が公知文献に記載されて知られていたから,訂正前の被告物質発明はいずれも進歩性を欠くというものであった(乙16 。)(b)A文献では,ワクシニアウイルスで感染した家兎皮膚組織中からウイルスを死滅後調製した抽出物Ⅰがラット胃酸分泌抑制作用及び食用ガエル心臓機能促進活性を示し,抽出物Ⅱが家兎赤血球の加熱溶血抑制,多核白血球の遊走抑制活性等を示したことが報告されている(乙26 。)そして,A文献に記載された「抽出物Ⅱ」と被告方法発明の生理活性物質とは,同じくワクシニアウイルスで感染した動物組織中からウイルスを死滅後調製した抽出物であったが,別表6記載のような差異があった(本件訴状添付の被告物質特許権の明細書及び乙26 。)(c)そこで,特許庁の第1次審決は,この差異に着目し,①両者の製法は,被告方法発明では,抽出材料にフェノール加グリセリン水を加え,次いでホモゲナイザーで摩砕するのに対して,抽出物Ⅱでは,同じ抽出材料にグリセリンを含まない単なるフェノール水中に2日間放置した後ホモジナイズするという点で相違しており(別表8 ,この相違が同一物質が得られる程度の微差であるとは直ちに )認められない,②両者の物理化学的性質は,訂正前の請求項1の発() 明ではオルシノール反応が陽性とされている 物理化学的性質の⑥のに対し,抽出物Ⅱでは陰性とされている(別表6の「物理化学的性質」⑥)として,両者は異なる物質であるとした上,被告方法発() , 明の生理活性物質 訂正前の請求項1 に進歩性が認められる以上その用途発明である訂正前の請求項2ないし4の発明にも進歩性が認められ,またその製造方法である訂正前の請求項5の発明にも進歩性が認められるとした(乙16 。)(d)これに対し,東京高等裁判所の第1次審決取消訴訟判決は,まず,A文献に記載された抽出物Ⅱの抽出条件に従って調製されたワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚組織抽出物につき物理化学的性質を試験したところ,被告方法発明の生理活性物質の①ないし⑧記載の性質とすべて一致したことが認められ,その信用性を疑わせる証拠はないとして,抽出物Ⅱと被告方法発明の生理活性物質とは同一の物と認められるとした。 その上で,両者の差異については,次のとおり判断し,抽出物Ⅱと被告方法発明の生理活性物質の製法等の相違点は,両者が同一の物であるとする結論に影響を与えない旨判断し,第1次審決を取り消した(乙29 。)α第1次審決が指摘したグリセリンの添加や抽出のための処理時間の相違については,特許請求の範囲においても発明の詳細な説明においてもグリセリン添加量についての限定や説明がないこと,被告物質発明におけるグリセリンの添加は,細胞の膨潤による抽出効率の増加やフェノールの添加による着色防止を目的としてされるものであり,グリセリンの添加によって活性成分の抽出特性が質的に変化するとは考えられず,その量は常識的な範囲で適宜定められ,水を主体とする抽出溶媒の本質に影響するほどのものではないこと,被告物質特許の明細書では抽出のための処理時間も記載されていないこと,抽出のための処理時間の相違により抽出物の成分が相違することを認めるに足りる的確な証拠がないことからすると,いずれの相違も,両者の出発粗抽出物の相違をもたらすほどのものとは認められない。 β最終抽出物に含まれる乾固物の収量が訂正前の請求項1の発明のものと抽出物Ⅱとでは異なる(別表6の「収量」欄)が,被告物質発明の明細書の実施例の間でも収量が異なっており,同一の製法においても溶媒の変更等により収量が数倍以上異なることがあるから,この点を根拠として両者が異なるとはいえない。 γ抽出物Ⅱには一部のアレルギーについて抗アレルギー作用がないとの記載がある(別表6の「抗アレルギー」欄)が,被告物質発明で行われた種類のアレルギーに対する抗アレルギー作用の試験は行われていないから,抽出物Ⅱが抗アレルギー作用を示さないとまで認定することはできない。 σ第1次審決が指摘したオルシノール反応の相違については,A文献では抽出物Ⅱの分画の一部についてオルシノール反応が陰性との結果が示されているだけであり,抽出物Ⅱの全分画について同反応が陰性と記載されているわけではない。 (e)被告物質発明を生理活性物質の用途発明のみに減縮する訂正請求の確定後にされた第2次審決では,抽出物Ⅱと同一の公知の物とされた被告方法発明の生理活性物質に,その用途発明のような薬効があることを見出した点に進歩性が認められるか否かが問題となったが,前提事実記載のとおり,被告物質発明の生理活性物質とA文献の抽出物Ⅱとは同一物であるところ,同抽出物ⅡとB論文(及び同論文と同等の方法により同一の生理活性物質を製造している4206号公報[乙34 )に記載された生理活性物質(B物質)とは ]同等の生理活性物質であり,B物質に鎮痛,鎮静,抗アレルギー作用があることは被告物質特許の出願前に知られていたから,上記用途発明も進歩性を欠くというものであった。この第2次審決の判断及びこれと同旨の判断をした東京高等裁判所の第2次審決取消訴訟判決の判断のうち,同抽出物ⅡとB論文に記載された生理活性物質(B物質)とが同等の生理活性物質であるとの判断の概要は,次のとおりである(甲137及び138,乙31 。)αA文献とB論文・4206号公報の各製造方法は,同一の原料を用いたものと認められるが,別表8記載のとおり,数点にわたる相違がある。 混合工程について,抽出物Ⅱでは,フェノール水を用いるものとされているのに対し,B物質では,生理的食塩水又は石炭酸加グリセリン水を用いるものとされているが,この点が最終抽出物に生理活性物質としての違いをもたらすほどの相違ではないことは当事者間に争いがない。 粗抽出工程について,A文献では,ワーリングブレンダーを用いてホモジナイズするものとされているのに対し,B論文・4206号公報では,凍結融解処理を繰り返すものとされている。しかし,いずれの方法も粗抽出方法として慣用されるものであると認められる上,磨砕も,凍結融解も,機械的に細胞を損傷することによって細胞内の諸物質を抽出しやすくするものである点で,本質的に同等の粗抽出処理であると理解され,現に被告を特許権者とする「神経疾患治療剤」の発明についての特許(特許第2539665号,出願日:昭和63年6月20日)に係る特許公報(以下「9665号公報」という )では,実施例1について, 。 抽出物Ⅱのものと同一の原料から,ほとんど同一といってよいほど酷似した製造方法により,神経疾患治療剤の有効成分となる生理活性物質を抽出する方法が記載されており,このように粗抽出処理として 「ホモゲナイザーで磨砕」するという上記実施例1 ,の処理のみならず 「凍結融解」の「処理により細胞組織を破壊 ,して抽出を容易にすることができる」とされているから,そこでは,両者を同等の粗抽出処理であると位置付けている(なお,A文献は,9665号公報に係る特許の出願日より10年以上前に実施されたものではあるが,その間に,粗抽出処理に関する当業者の理解に変化があったことを認めるに足りる証拠はない。。)もっとも,粗抽出工程の方法の相違に基づいて,抽出される細胞内の諸物質にある程度の差異が生じることは確かであるが,粗抽出方法の上記差異は,抽出物Ⅱの粗抽出物に,B物質中の有効成分物質が含まれなくなるようなものではない。 ,,. タンパク質除去工程については A文献では ろ過液をpH92に調整して,30分沸騰してろ過する工程があるのに対し,B論文・4206号公報には存在しない。また,B論文・4206号公報では,クロロホルム処理及びアスベスト処理の工程があるのに対し,A文献には存在しない。しかし,前者については,これらはいずれも不要なタンパク質除去のためのものであると認められるところ,前記9665号公報においては,多種多様なタンパク質除去のための処理方法が記載され,適宜に選択可能な同等の処理方法であると位置付けられていることからすれば,タンパク質除去工程の上記差異は,最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点とは認められない。また,後者については,B論文による製造方法と,相互に同等の方法により,実質的に同一の生理活性物質,すなわちB物質を製造するものであることにつき当事者間に争いのない4206号公報の製造方法においては,クロロホルム処理及びアスベスト処理の工程は存在しないから,当該工程の有無に関する差異が,最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点でないことは明らかである。 吸着溶出工程については,A文献では活性炭を用いているのに対し,B論文・4206号公報ではカオリンを用いている。しかし,吸着剤として活性炭及びカオリンのいずれを用いても実質的に同一の有効成分を持った生理活性物質が抽出されることについては,当事者間に争いがない。 濃縮等工程につき,B論文・4206号公報には,塩類を除くために透析する工程があるのに対し,A文献には存在しない。しかし,B論文・4206号公報の製造方法における透析工程は,塩類を除くためのものであるから,透析前の液においても,透析後の液においても,B物質の有効成分自体は含まれているはずで,, ,() あり 仮に これを行わないこととしても 若干の夾雑物 塩類が含まれることになるだけであって,B物質の有効成分に差異はもたらされないことが明らかである。 沈殿工程について,B論文には,ろ液の10倍量のアセトンやアルコールのような水可溶性有機溶媒と混合して沈殿させる工程があるのに対し,A文献には存在しない。しかし,4206号公報の製造方法においては,上記沈殿工程は存在しないから,当該工程の有無に関する差異が,最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点でないことは明らかである。 以上のとおり,A文献の製造方法とB論文・4206号公報の製造方法の相違点は,いずれも,最終的に製造される生理活性物質に相違をもたらすような実質的な相違点であるとは認められない。加えて,A文献の執筆者において,抽出物Ⅱの製造方法が,B論文の製造方法に「準じ」るものであると考えていたことは,A文献の記載から明らかであることをも考え併せれば,A文献に接した当業者においては,そこに記載された抽出物Ⅱの製造方法は,公知のB物質の製造方法と実質的に同等のものであると理解するものと認められる。そして,そうとすれば,A文献に接した当業者は,他に特段の事情が認められない限り,B物質の製造方法と実質的に同等の製造方法から得られた生理活性物質である抽出物Ⅱ自体も,B物質と実質的に同等の物質であると理解するものというべきである。 β抽出物ⅡとB物質とは,被告物質発明に係る生理活性物質の物理化学的性質として特定された事項において,何点か相違点があるとの実験報告がある(別表7 。)性状,特に色の点について,B物質が「白色無定形の粉末」であるのに対し,抽出物Ⅱは「褐色の吸湿性の粉末」である。しかし,色に関する表現は,物質の採取量や観察者の主観によって異なることはよく知られているところである。また,抽出物ⅡやB物質のような生体由来の抽出物の場合,夾雑物の混入等により性, 。, 状に差異の生じ得ることは 当業者に自明の事項である そして抽出物Ⅱの製造方法とB物質の製造方法との間には,いくつかの差異があるのであるから,後者に含まれない夾雑物が前者に含まれ,これが上記色に関する差異をもたらしたとしても,何ら不自然なことではないというべきである。そうすると,抽出物ⅡとB,,, , 物質との間に 表現上 実際上 色に関する差異があるとしてもそのことから直ちに,抽出物Ⅱの有効成分物質とB物質の有効成分物質との間に物性の違いが存在するということはできない。 アルコール,アセトンに対する溶解性の点について,B論文では,B物質は「アルコール,アセトン若しくはエーテルに溶けないが,水には可溶である」と記載されているが,A文献の製造方法に従って抽出物Ⅱを製造し,その性質を実験した実験報告書では,抽出物Ⅱは「水1ml,メタノール1ml及びエタノール5mlに溶解した」とされている。しかし,溶解性の試験条件や基準によって,ある物質の「溶けない「可溶である」等の溶解 」,性に関する評価が変わることは明らかであるところ,抽出物Ⅱの溶解性は,上記実験報告書の結果に従うと,溶質1gを溶かすために溶媒量約4200mlが必要であるということになるから,当該溶解が,仮に,日本薬局方の定める溶解条件に従ったものであるとすれば,同基準上 「極めて溶けにくい」と評価されるも ,のであって,こうした物質について 「極めて溶けにくい」ので ,あるから 「溶けない」と評価することも,また,溶解しないこ ,とはないのであるから「可溶である」と評価することも,いずれも可能であるというべきである。他方,B論文は,B物質について 「アルコール,アセトン若しくはエーテルに溶けない」と記 ,, 。, 載するが その試験条件や判定基準が明らかでない そうするとB論文において,少なくとも,エチルアルコールに対する溶解性につき 抽出物Ⅱについてのものと同程度の溶解現象に対し溶 , ,「」 , けない との評価がされた可能性は否定することができないから結局,上記のような実験報告書とB論文との表現上の違いを根拠に,抽出物ⅡとB物質とが,アルコール,アセトンに対する溶解性という物性において相違するとまでは認められないというべきである。 同じくアルコール,アセトンに対する溶解性の点について,B論文においては,B物質につき 「このように処理した濾液を, ,濾液の10倍量のアセトンやアルコールのような水可溶性有機溶媒と混合する。そうすると有効成分は沈殿し容器の底に沈む」とされているが,被告が,被告物質発明の実施品である「新ノイロトロピン原液」について上記と同じ混合をした実験報告書では,いずれの溶媒の添加に対しても沈殿は生じなかった旨報告されている。しかし,同じ溶質を溶解した水溶液に,同じ有機溶媒を同じ割合で添加したとしても,基となる水溶液における溶質の濃度が異なれば,溶質の沈殿挙動は相違すること(通常,溶質の濃度がより大きいほど,より沈殿しやすいこと)が一般的であると認められる。そうすると,仮に 「新ノイロトロピン原液」が被告 ,物質発明の実施品であるとしても,B論文におけるB物質の濃度が不明である以上 「新ノイロトロピン原液」の濃度よりも,B ,論文における有機溶媒添加前のろ液における溶質の濃度が濃いことにより,溶質の沈殿挙動が左右された可能性を排除することはできない。 ,,, ニンヒドリン反応の点について B論文においては B物質は「如何なる蛋白質反応およびニンヒドリン反応に対しても,本品の水溶液は陰性を示す」とされているのに対し,A文献の製造方法によって抽出物Ⅱを製造し,その物理化学的性質を試験した実験報告書では,抽出物Ⅱは「ニンヒドリン反応に陽性」とされている。しかし,ニンヒドリン反応の有無に関する相違は,抽出物Ⅱ中にはニンヒドリン反応陽性物質が存在するが,B物質中には。, そのような物質が存在しないことを意味するにすぎない そして抽出物ⅡやB物質のような生体由来の抽出物の場合,夾雑物の混入等により性状に差異の生じ得ることは,当業者に自明の事項で, , あるところ 抽出物Ⅱの製造方法とB物質の製造方法との間にはいくつかの差異があることは前示のとおりであり,後者に含まれないニンヒドリン反応陽性の夾雑物が前者に含まれているとしても,何ら不自然なことではない。 透析性の相違について,B論文ではB物質は非透析性の物質であると記載されているのに対し,その有効成分が抽出物Ⅱである「」, と被告が主張する 新ノイロトロピン原液 について実験すると透析性があったと報告されている。しかし,単に,透析性の有無(透析されるか否か)だけを論じても無意味であり,透析に用い() , た透析膜 半透膜 の性状その他の透析条件が確定されなければ真に,対象とされる物質の間に物性の相違があるか否かは不明である。そして,B文献における透析条件は不明であるから,上記結果からB物質と抽出物Ⅱとが透析性の有無という物性において異なるということまではできない。 以上のとおり,抽出物ⅡとB物質とは物性において相違するとはいえないから,他に特段の事情の認められない本件において,A文献に接した当業者は,B文献の製造方法と実質的に同等の製造方法から得られた生理活性物質である抽出物Ⅱ自体も,B物質と実質的に同等の物質であると理解するものというべきである。 cところで,特許に無効理由が存する場合であっても,いったん登録された以上,その登録を無効とする審決が確定しない限り,当然その効力を失うものではなく,通常裁判所において特許の当否やその効力の有無を判断することはできないというのが,従前の判例であり(大審院明治37年9月15日判決・刑録10輯1679頁,同大正6年4月23日判決・民録23輯654頁等 ,ただ特許の内容の一部に )公知部分があるときにはこれを除外して当該発明の権利範囲を限定して解釈することができるとされるにとどまっていた(最高裁判所昭和39年8月4日第三小法廷判決・民集18巻7号1319頁参照 。)そして,これらの判例に従う限り,特許権侵害訴訟において特許が無効であるものと扱うことができず,同訴訟を審理する裁判所が無効理由の有無を判断することはできないこととなるが,そのような場合だけなく,本件のように,被告が原告らの行為が特許権を侵害する旨を第三者に告知・流布した場合に,当該特許権に係る特許が特許法29条2項違反を理由として無効理由を有するために同告知・流布行為が虚偽の営業誹謗行為に該当するとして,原告らが被告に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合においても,同事件の審理においては,特許が無効であるものと扱うことができず,同事件を審理する裁判所が無効理由の有無を判断することはできないこととなる。 そうすると,上記大審院判例が通用している状況下では,たとえ原告らが被告物質特許に無効理由があることを認識していたとしても,まず同特許に対する無効審判を請求し,その無効審決が確定するのを待って本件のような損害賠償請求訴訟を提起するという行動に出たのは無理からぬところがあり,換言すれば,同無効審決の確定前に本件損害賠償請求訴訟を提起することは合理的に期待し得るところではなかったというべきである。 もっとも,上記の大審院判例は,最高裁判所平成12年4月11日第三小法廷判決(民集54巻4号1368頁)によって明示的に変更され,同判決は,特許に無効理由が存在することが明らかであるときは,その特許権に基づく差止め又は損害賠償等の請求は,特段の事情がない限り,権利の濫用に当たり許されない旨を判示したから,同判決以後は,原告らが本件損害賠償請求訴訟を提起することも期待し得たように見える。 しかしまず,この判決は,特許権侵害訴訟における特許権者側の権利行使が権利の濫用として扱われることを示したにとどまり,本件のような虚偽の営業誹謗に基づく損害賠償請求においてまで,その射程が及ぶものであるのか否かは必ずしも明らかでない。 またその点を措くとしても,上記最高裁判決では,特許に無効理由が存在することが「明らか」であることを要件としていることから,原告らに本件損害賠償請求訴訟を提起することを合理的に期待し得たといえるためには,原告らが,被告物質特許に無効理由が存在することが明らかであると認識していたことが必要である。しかるところ,上記最高裁判決がなされた時点では,被告物質発明にかかる生理活性物質がA文献に記載された抽出物Ⅱと同一物質であるとの第1次審決取消訴訟判決は確定していたものの,その用途発明である訂正後発明( ) , 訂正前の請求項2ないし4 が無効理由を有するか否かについては①第2次審決及び第2次審決取消訴訟判決で引用文献とされたB論文は,第1次審決取消訴訟の判決確定後に再開された無効審判手続において被告側から(原告フジモトD側からではない)乙第5号証として提出されたものであるから(甲137 ,原告らは,これを引用文献 )「」, として被告物質特許が無効理由を有することが 明らか であるとは少なくとも第2次審決がされた平成15年8月27日までは認識していなかったと考えられること,②またA文献に記載された抽出物ⅡとB論文に記載されたB物質(ノイロトロピン)とは,前記のとおり,その製造方法に若干の相違があるほか,その物理化学的性質にも相違点があるとの実験報告書が存したのであるから,原告らにおいて,両者が同一であることが上記第2次無効審決前においても「明らか」であるとまでの認識を有していたと認めるのは困難であることからして,早くとも第2次審決がされた平成15年8月27日以前には,原告らが本件損害賠償請求訴訟を提起することを合理的に期待することはできなかったというべきである。 (なお原告らは,被告が昭和薬品に対して申し立てた仮処分事件において,事実上昭和薬品に代わって手続を追行する過程で,平成7年3月28日付けの主張書面において,原告製剤は被告物質発明の定める物理化学的性質を満たさず,同発明の技術的範囲に属しない旨の主張をしたことがある(乙24 。しかし,この点の真偽は結局未確定の )ままとなっており,本件でも虚偽と認めるに足りる証拠はないから,原告らがこの点で被告の告知・流布内容が虚偽であると認識することができたとはいえない )。 dそして,本件訴訟はそれから3年を経過する前の平成17年3月16日に提起されているから,結局,被告方法特許権と被告物質特許権の双方に関連する行為(別表9の2A及び2B)については,消滅時効は完成していないというべきである。 エ品質に関する営業誹謗行為の関係について原告らが被告による品質に関する営業誹謗行為として主張するのは,農薬,不純物の混入に関する告知・流布行為と副作用に関する告知・流布行為であるが,いずれについても,その内容が実際に事実と反するというのであれば,原告らとしては,上記のような被告の告知・流布行為を認識すれば,直ちにそれが虚偽の事実を告知・流布する違法な営業誹謗行為であり,それによって売上減少や信用毀損等の損害が生じることを認識することができたと認めるのが相当であり,その時点において損害賠償請求権を行使することを合理的に期待し得るものというべきである。 したがって,品質に関する営業誹謗行為に基づく消滅時効の起算点は,原告らが被告の各行為を認識した時であるところ,別表2によれば,同行為に該当するとして原告らが主張する被告の行為は,最も時期の遅いものでも平成7年4月5日であるから,遅くともそれから3年が経過した平成10年4月5日には,被告の上記行為によるすべての損害賠償請求権について消滅時効が完成し,被告がこれを援用したことにより,消滅したものというべきである。 オ小括以上より,原告らの不正競争防止法に基づく損害賠償請求については,特許権侵害に関する営業誹謗行為のうち被告方法特許権のみに関連する行為(別表9の1A及び1B)に基づくもの,及び品質に関する営業誹謗行為に基づくものは,その余について判断するまでもなく理由がない。 そこで次に,特許権侵害に関する営業誹謗行為のうち被告方法特許権及び被告物質特許権の双方に関連する行為(別表9の2A及び2B)に基づくものについて,請求原因上の争点(争点(1)ないし(3)及び(5))を検討する。 (2)争点(1)(営業誹謗行為の存否)についてア行為の存否及び内容について(ア)別表1の1-1及び1-2,1-109ないし1-112欄について被告がこれらの謹告文や警告文を薬事日報や薬事ニュースといった業界紙に掲載したことは当事者間に争いがない。 これらの文章では,被告がワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤について多数の特許権を有しており,その製造販売は被告の特許権を侵害する旨が記載されているから,これにより被告は,原告らが被告の特許権を侵害して原告製剤を製造しており,原告製剤の製造販売は被告の特許権を侵害する行為である旨を告知・流布したものと認められる。 (イ)別表1の1-3ないし1-7欄について被告がこれらの文章を被告製剤の顧客に配布するために作成したことは被告も認めるところであり,この点にこれら文書を原告らが入手していることを考え併せれば,被告は,これら文書を医薬品卸売業者に配布したものと推認される。 これらの文章では,被告がワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤について多数の特許権を有しており,その製造販売は被告の特許権を侵害する旨が記載されているから,これにより被告は,原告らが被告の特許権を侵害して原告製剤を製造しており,原告製剤の製造販売は被告の特許権を侵害する行為である旨を告知・流布したものと認められる。 (ウ)別表1の1-12欄について, , 同欄記載の証拠によれば 昭和薬品のD部長から原告従業員に対して同欄記載のころ,同欄記載のとおりの内容の架電がされたことが認められるところ,そこにおいて被告から昭和薬品に送付された文書とは,別表1の1-3ないし1-7欄記載の被告の各文書配布の時期からして,別表1の1-5欄に係る文書であると推認される。 そして,この文書では,被告がワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤について多数の特許権を有しており,その製造販売は被告の特許権を侵害する旨が記載されているから,これにより被告は,原告らが被告の特許権を侵害して原告製剤を製造しており,原告製剤の製造販売は被告の特許権を侵害する行為である旨を告知・流布したものと認められる。 (エ)別表1の1-17,1-18,1-20,1-27,1-29ないし1-32及び1-98欄について同欄記載の甲号証によれば,行為者欄記載の被告の関係者が,相手方欄記載の者に対し,行為時欄記載のころ,甲号証の記載欄のとおりの内容を告知したことが認められ,これにより被告は,原告製剤の製造販売は被告の特許権を侵害する行為であり,原告製剤は薬価基準収載から削除されるなど販売できなくなる旨を告知・流布したものと認められる。 これに対し,被告は,同欄記載の認否・反論のとおり主張する。しかし,原告ら提出のメモや報告書(上記各甲号証)は,当時において原告らの担当者が報告用に作成したメモであり,特に訴訟等を意識したことも窺えない上,被告は平成6年ころに立て続けに前記謹告文等を業界紙に掲載し,また前記文書を医薬品業界に配布しており,しかも掲載した前記謹告文等においては,被告の特許権を侵害することなくワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤を製造販売することは不可能であると明言しているのであるから,従業員が同様の趣旨を医薬品卸売業者等に告知したとしても何ら不思議ではない。以上によれば,上記各甲号証の記載が伝聞に基づくものであることや,相手方や内容が抽象的なものがあることを考慮しても,なお上各甲号証の記載内容は信用できるものと認められる。 (オ)別表1の1-26,1-28欄について同欄記載の甲号証によれば,被告の従業員が,相手方欄記載の者に対し,行為時欄記載のころ,甲号証の記載欄のとおりの内容を告知したことが認められる。しかし,この内容は,原告らと被告との間で特許権侵害訴訟が係属していることや,そこで被告が勝訴した場合には原告製剤が製造販売できなくなることを告知しているにすぎないから,原告ら主張の虚偽事実,すなわち原告製剤の製造販売が被告の特許権を侵害する旨を告知したものとは認められない。 (カ)別表1の1-33欄について同欄記載の甲号証には,被告の代理人弁護士が,相手方欄記載の者に対し,行為時欄記載のころ,甲号証の記載欄のとおりの内容を告知したことが記載されている。しかし,そこで言及されている「卸の裁判」とは,被告が昭和薬品等を相手に申し立てた仮処分のことを意味するもの,, , と思われるところ その担当弁護士が 当該事件と関係がない者に対し迂闊に判断の見通しを断定的に語るとは考え難いところがある。また,告知を受けた「シオノギの総務の者」も,弁護士は自分の面子からも負けるとはいえないのかも知れないと感じたというのであるから,結局において,原告製剤が被告の特許権を侵害する旨を告知したものとは認められないというべきである。 (キ)別表1の1-96欄について同欄記載の証拠によれば,小田島弘前営業所の担当者から原告従業員に対して,同欄記載のころ,甲号証の記載欄のとおりの情報が寄せられたことが認められるところ,そこにおいて被告から同営業所に送付された文書とは,別表1の1-3ないし1-7欄の被告の各文書配布の時期からして,別表1の1-7欄に係る文書であると推認される。 そして,この文書では,被告がワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤について多数の特許権を有しており,その製造販売は被告の特許権を侵害する旨が記載されているから,これにより被告は,原告らが被告の特許権を侵害して原告製剤を製造しており,原告製剤の製造販売は被告の特許権を侵害する行為である旨を告知・流布したものと認められる。 (ク)以上のとおり,被告方法特許権及び被告物質特許権の双方に関連する行為(別表9の2A及び2B)のうち,被告が,原告らが被告の特許権を侵害しており,原告製剤の製造販売が被告の特許権を侵害する行為である旨を告知・流布したものと認められるのは,別表1の1-1ないし1-7,1-12,1-17,1-18,1-20,1-27,1-29ないし1-32,1-96,1-98,1-109ないし1-112欄の行為であり(以下,これらを「本件告知・流布行為」という,。)その他の行為は原告らが主張する虚偽の事実を告知・流布したものとは認められない。 イ告知・流布内容の虚偽性について(ア)被告方法特許権の侵害の点についてa前提事実記載のとおり,被告が原告らに対して被告方法特許権の侵害を理由として提起した訴訟について,その第1次訴訟においては,原告フジモトDは被告方法発明の技術的範囲に属する被告主張方法の確認検査方法を用いて原告製剤を製造し,被告方法特許権を侵害しているとの認定判断が確定し,その第2次訴訟においては,原告フジモトDは平成4年12月22日以前は被告方法発明の技術的範囲に属する原告当初方法の確認検査方法を用いていたが,同日以後は原告変更方法を用いており,被告方法特許権を侵害していないとの認定判断が確定した。 bところで,証拠(乙1)によれば,第1次訴訟では,①原告フジモトDは,自己の実施する確認試験方法は原告変更方法であると主張していたものの,原告製剤の原承認に係る製造承認書に記載された確認試験方法がどのようなものであるかは明らかにされておらず,また原告フジモトDによる一変申請の事実も明らかにされておらず,さらには原告フジモトDがその主張する確認試験方法を開発した経過に関する内部資料も提出されなかったこと,②そのため,原告製剤が被告製剤の後発医薬品であることから,原告製剤の確認試験方法は被告製剤の確認試験方法と同等又はそれ以上のものであることが求められることを前提に,原告フジモトDの製造承認書に記載された確認試験方法がどのようなものか,原告フジモトDが実施していると主張する確認試験方法(これは原告変更方法であった )が被告発明方法と同等又 。 はそれ以上といえるか否か,また被告方法発明以外にカリクレイン様物質産生阻害活性の定量的測定方法が存在するかという観点から,原告フジモトDが被告発明方法を使用していると推認し得るか否かが争。, , われたことが認められる そして これに対する控訴審判決の概要は次のとおりである(この認定判断は上告審判決においても正当とされた。。)(a)薬事法上,後発医薬品には先発医薬品との間に医薬品としての「同一性」がなければならないが,後発医薬品と先発医薬品との同一性を調査する項目の一つがいわゆる「規格及び試験方法」である(この中に「確認試験」が含まれる。後発医薬品につき製造承 。)認を受けるためには,その「規格及び試験方法」が先発医薬品のそれと同一内容のものである必要はなく,同等又はそれ以上の精度のものであることが証明できるのであれば,異なる試験方法を採用しても差し支えない。また,後発医薬品の製造に当たっては,製造承認において承認された「規格及び試験方法」のうちの確認試験の方法と現に業として実施する確認試験の方法とが必ずしも同じ方法であることを要しないが,この場合であっても,同等以上の試験方法であることが要求される。 (b)先発医薬品である被告製剤の確認試験方法は,別表5の「被告確認試験方法」欄記載のとおりであり,被告発明方法であるが,その技術的特徴は,次の点にある。 α被検物質溶液にヒト血漿とカオリンを混和してカリクレイン様活性を惹起しカリクレイン様活性が時間経過とともに直線的に増加する一定時間内にLBTIを添加することによってそれ以後のカリクレイン様物質の産生を停止させる点(第1次反応)(), βこの反応液と合成基質溶液とを混和反応させて 第2次反応反応液の吸光度を測定し,この吸光度と同様にして得た対照液についての吸光度との吸光度差を被検薬剤のカリクレイン阻害活性能の測定値とする点(c)この被告確認試験方法と比較すると,原告変更方法では,第1に特異的阻害剤であるLBTIを添加していない点で異なる。 特異的阻害剤は,カリクレインを生成させる第1次反応を停止させるために添加されるものであり,この添加がない場合には,生成したカリクレイン量を定量する第2次反応の反応時間中もカリクレインの生成反応が継続することになり,第1次反応におけるカリクレイン生成量を正確に測定することができないから,原告変更方法では,被告確認試験方法と同等以上の精度でカリクレイン様物質産生阻害活性の定量測定が可能であるとすることはできない。 原告フジモトDは,LBTIを添加せずともカリクレイン様物質産生阻害活性の確認ができるとして実験結果を提出するが,それらは原告変更方法とは異なる方法であったり,被告確認試験方法との間に測定値において小さからぬ差が生じていて,採用できない。 (d)被告確認試験方法と原告変更方法の相違点の第2は,原告変更方法では,被検物質非添加群を設定していない点である。 被検物質非添加群の測定値は,カリクレイン生成反応が阻害されていない状態での基準値たる測定値であり,この測定値と被検物質添加群の測定値との差がすなわち阻害能であるから,カリクレイン様物質産生阻害活性の定量的測定のためには,被検物質非添加群の測定が不可欠である。 原告フジモトDは,原告変更方法においては,被検物質非添加の. , 状態で第2次反応後の吸光度が0 4前後の一定の値になるように測定ごとに血漿の希釈倍率を決定しており,これが被検物質非添加群の測定にほかならないと主張するが,その証拠として提出された実験報告書等では,被検物質非添加群の測定をした旨が示されていなかったり,原告変更方法と異なる方法が実施されていたりするなどしており,原告フジモトDが被検物質非添加群の測定を行っているとは認められない。 (e)被告確認試験方法と原告変更方法の相違点の第3は,原告変更方法では,被検物質を添加した場合の吸光度をカリジノゲナーゼ標準液の吸光度と比較している点である。 しかし,原告変更方法では,血漿からのカリクレイン生成反応という,測定ごとの変動が避けられない測定系を用いながら,その比較対照基準として,血漿を用いないカリジノゲナーゼ標準液を使用しているため,血漿を用いたときのカリクレイン生成反応における試験ごとの測定値の誤差変動を償却できない。そうである以上は,被検物質添加群の吸光度測定値とカリジノゲナーゼ標準液の吸光度測定値を比較してみても,それは定量性の点から見て技術的には意味のないものである。 (f)以上より,原告変更方法は,被告確認試験方法と同等以上の精度でカリクレイン様物質産生阻害活性の定量測定が可能であるとすることはできないから,そのような方法を製薬企業である原告フジモトDが実施しているとは容易に認め難い。そして,被告発明方法によらないカリクレイン様物質産生阻害活性の定量方法が存在することを認めるに足りる証拠はないこと,原告製剤の製造承認の過程では,厚生省の担当官は,原告フジモトDに対し,被告確認試験方法と同等以上の確認試験の方法を設定するよう指示・指導し,原告フジモトDもこれに対応したという経緯を考え併せると,原告製剤は,被告主張方法(すなわち被告発明方法)を用いて製造されていると認めるのが相当である。 c他方,証拠(甲127,131)によれば,第2次訴訟では,第1次訴訟での主要な証拠が改めて提出されたほか,①原告製剤の確認試験方法は,平成4年2月21日の原承認に係る製造承認書では被告発明方法と実質的に同一の原告当初方法とされていたが,原告フジモトDは同年12月22日に確認試験方法を原告変更方法に変更する旨の一変申請を行い,平成11年4月13日にその一変承認を受けたことが明らかになっており,また,当時原告藤本製薬の研究部に所属していたEの実験ノート等が提出されるなどして,原告フジモトDが原告変更方法を開発した時期や経過を立証するための内部資料が証拠として提出されたこと,②そのため,審理においては,上記一変承認前にも原告フジモトDが原告変更方法を実施していたか否かが争われ,具, , 体的には 原告変更方法が被告発明方法と同等といえるか否かのほかEの実験ノートの記載及び同人の陳述の信用性や一変承認の合理性が問題となったことが認められる。そして,そして,これに対する第1審判決の概要は,次のとおりである(この認定判断は控訴審判決においても基本的に維持された。。)(a)「医薬品製造指針」等によると,医薬品の製造承認に係る「確認試験」は,当該医薬品が目的物であるか否かを確認するために必要な試験とされており,他方「定量法」は,医薬品の有効成分の含量,力価などを物理的,化学的又は生物学的方法によって測定する試験法とされている。そうすると,確認試験においては,対象物が目的物であるかどうかを判別するための特定の反応等の有無が明らかにされれば足り,測定数値が問題とされる場合も,標準物質の測定値と比較して,基準となる一定の測定値以上(又は以下)の数値を示すかどうかが問題とされるものと解され,定量法において試料中に存在する分析対象物の量を正確に測定することとは異なるものと解される。そして,被告製剤においても,また原告製剤においても,カリクレイン様物質産生阻害活性に関する試験は,そのような確認試験として位置付けられていることが認められる。 (b)確かに原告変更方法では,被告発明方法と異なり阻害剤としてのLBTIが添加されておらず,第1次反応により産生されたカリクレインの量を測定するに当たっては,阻害剤を添加して第1次反応を停止させたほうが,そうでない場合よりも正確な測定値を求めることができる。 しかし,原告変更方法は,第1次反応により産生されたカリクレインの絶対量を直接測定するものではなく,カリジノゲナーゼ標準試料の吸光度を基準として被検物質試料の吸光度との大小を比べて(いずれもブランクの吸光度が差し引かれている。以下,原告変更方法について述べる場合同じ,後者が前者よりも低いときにカ 。)リクレイン様物質産生阻害活性があると判定するものである。そして,阻害剤を用いず,したがって第1次反応の継続時間が長くなるとすれば,カリクレイン様物質が多く産出され,吸光度が大きくなり,カリクレイン活性が大きく測定されることとなる。しかるに,仮に被検物質の吸光度が実際より大きく測定されたとしても,標準溶液の吸光度よりも小さいと判定されれば,その被検物質の真の吸, , 光度は 標準溶液の吸光度よりも優に小さいことは間違いないから被検物質の吸光度が標準溶液の吸光度よりも小さいこと,言い換えれば,被検物質のカリクレイン様物質産生阻害活性が所定の値よりも大きいことを,確実に検査することができる。 このように,原告変更方法は,被検物質を添加した溶液の吸光度が標準溶液の吸光度よりも小さい場合に,被検物質のカリクレイン様物質産生阻害活性があると判定するものであるから,標準溶液の吸光度の値を適切に設定すれば,阻害剤を用いなくても,被検物質のカリクレイン様物質産生阻害活性が一定値以上あることを正確に判定し得るといえる。 (c)そして,原告変更方法においては,被検物質を添加しない試料の第2次反応後の吸光度が約0.4を示すように測定ごとにヒト血漿の希釈倍率の決定を行っており,他方,カリジノゲナーゼ標準試料の吸光度は0.3前後である。そこで,カリジノゲナーゼ標準試料の吸光度と被検物質試料の吸光度を比較して,カリクレイン様物質産生阻害活性があると判定される場合は,常に,被検物質試料の吸光度は,カリジノゲナーゼ標準試料の吸光度である0.3前後以下,すなわち,被検物質非添加試料の吸光度である0.4以下であることになる。そうすると,被検物質非添加試料の第2次反応後の吸光度が約0.4を示すようにヒト血漿の希釈倍率の決定を行うという操作は,被検物質を添加しない場合の吸光度の設定ということができ,そこで設定された0.4という吸光度は,カリクレイン様物質産生阻害活性があると判定されるためには常に被検物質試料の吸光度がそれより低くなければならないという意味で,被検物質試料の吸光度と対照されているということができる。そうすると,原告変更方法において,被検物質非存在下の測定がされていないとはいえないし,原告変更方法によって,カリクレイン様物質産生阻害活性の有無は判定できるものというべきである。 (d)また,原告変更方法では,減圧乾固及びエタノール抽出処理によってカリクレイン様物質産生阻害活性が失活するとの問題が指摘されている。 しかし,そのような報告がされている実験報告書は,それらにおける減圧乾固及びエタノール抽出処理の条件が原告変更方法と異なるか,あるいは同一か否か不明である上,原告変更方法を実施した実験報告書等によれば,原告変更方法によってカリクレイン様物質産生阻害活性が失活しないものと認められる。 (e)したがって,原告変更方法は,確認試験方法として原告当初方法と少なくとも同等であると認められる。 (f)原告製剤の原承認に係る製造承認書には確認試験方法として原告当初方法が記載されており,それは実質的に被告主張方法と同じであり,被告方法発明の技術的範囲に属するものである。したがって,原告フジモトDは,一変承認を得るまでの間は,確認試験として被告発明方法を使用していたことが事実上推定される。 しかし,Eの実験ノートは,信用し得るものといえるが,それによれば,同人は,昭和55年より後,一変申請前,LBTIの添加によってカリクレイン産生反応がかえって活性化するという実験結果を得ていたものと認められる。他方,原告フジモトDは,その提出に係る製品標準書及び標準作業書を有していたことは認められる, , が これらの書面がその記載どおりに平成4年8月1日に作成され同年9月19日から原告変更方法が実施されたということは認めることができない。そして,原告フジモトDは,平成4年8月20日ころ,第1次訴訟の訴状の送達を受け,原承認に係る製造承認書に記載した原告当初方法を使用すると被告方法特許権を侵害することになることを知ったこと,その後,原告当初方法を用いずに確認試,,, 験を行う方法を真剣に検討したこと 同原告は 平成4年7月ころ又は第1次訴訟の訴状の送達を受けた後,Eに相談し,同人が,以前に行った実験でLBTIに問題点があった旨を述べ,LBTIを使用しない確認試験方法の検討がされ,実験が行われたことが推認され,一変申請を行った平成4年12月22日までには,これらの実験を終え,原告変更方法をもって原告当初方法に代え得ることについて,実験データ等の相当程度の裏付けを得ていたものと推認される。そして,第1次訴訟の係属中であったから,このように相当程度の裏付けを得た後は,原告変更方法を実施していたものと推認される。 d以上の両判示を検討する。 (a)まず,原告変更方法が被告確認試験方法と比較して,後発医薬品として具備すべき同等性を備えているか否かを検討するに当たり,第1次訴訟の判決においては,原告製剤の確認試験方法は,先発医薬品である被告製剤のそれと,定量面まで含めて同等でなければならないことを前提としているが,第2次訴訟の判決が引用する「医薬品製造指針」等の記載からすると,確認試験においては,対象物が目的物であるかどうかを判別するための特定の反応等の有無が明らかにされれば足り,厳密な定量性は求められないとする第2次訴訟の判断がより正当であると考えられる。 そして,その前提に立って見れば,原告変更方法は,その定量性においては被告の確認試験方法に劣ると考えられるものの,確認試験方法として求められるところに関する限りは,第2次訴訟の判決が述べるとおり,原告当初方法と同等であるというべきであり,ひ。, いては被告確認試験方法とも同等であるというべきである そしてこのことは,実際に原告変更方法に対して一変承認がされたことによっても裏付けられている。 (b)また,一変承認前に実際に原告フジモトDが原告変更方法を行っていたか否か,同原告が原告変更方法をいつごろどのような経緯で開発していったのかという点についても,第1次訴訟では全く検討されていないが,第2次訴訟では,第1次訴訟では提出されなかった原告フジモトDによる原告変更方法の開発経過を示す証拠が相当数提出され,その開発経過が相当程度解明されるに至っているのであって,その判断は,第1次訴訟の判断と比べて,より豊富な証拠に基づく,より精度の高い判断に至っていると考えられる。 (c)以上からすれば,第2次訴訟において判断されたとおり,原告フジモトDは,一変申請がされた平成4年12月22日以降は,原告変更方法を実施していたものと認めるのが相当であり,本件告知・流布行為がなされた時点では,原告らは被告方法特許権を侵害していなかったものと認められる。したがって,上記の日以後に,原告らが被告方法特許権を侵害している旨を告知・流布する行為は,虚偽の事実を告知・流布することになるというべきである。 eまた,特許法2条3項は,発明を物の発明,方法の発明及び物を生産する方法の発明の3種類に分類しており,それぞれについて特許権者が専有する実施行為の内容を異にして規定しているが,被告方法発明は,被検物質のカリクレイン生成阻害能の測定法の発明であって,この方法を実施したことによって物が生産されるわけではないから,上記分類中の方法の発明に該当する。そうすると,被告方法特許権の侵害行為とされるのは,業として被告発明方法を使用する行為であって(同法2条3項2号 ,被告方法発明の測定法を使用して原告製剤 )の確認試験を行う場合であっても,原告製剤の製造販売行為は被告方法特許権を侵害する行為とはいえない。これは,第1次訴訟上告審判決の判示するところである。したがって,原告製剤の製造販売が被告方法特許権を侵害する旨を告知することも虚偽の事実を告知・流布することになるというべきである。 (イ)被告物質特許権の侵害の点について被告物質特許については,これを無効とする審決が確定し,遡及的に無効となったことは前提事実記載のとおりである。したがって,原告らは,被告物質特許権を侵害していなかったと認められ,原告らが被告物質特許権を侵害している旨を告知・流布する行為は,虚偽の事実を告知・流布することになる。 (ウ)被告の告知・流布行為の虚偽性について先に上記アで認定した本件告知・流布行為はいずれも,被告の特許権を特定することなく,原告らが被告の特許権を侵害しており,原告製剤を製造販売する行為は被告の特許権を侵害する旨を告知・流布するものと認められるが,そのような内容に接した医薬品関係者は,被告がいかなる特許権をどのくらい保有しているかを知っているわけではないのが通常であろうから,上記告知・流布に係る内容としては,原告らが,被告が有する特許権のいずれかを侵害しており,原告製剤の製造販売は被告の特許権のいずれかを侵害するという趣旨に理解するものと推認される。そうすると,被告の告知・流布した内容が「虚偽の事実」であるというためには,原告らが,被告が保有するいずれの特許権をも侵害していないことが認められる必要がある。 しかるところ,先に上記アで認定した本件告知・流布行為のうち,別表1の1-1ないし1-3欄の各行為は,いずれも原告フジモトDが確認試験方法を原告変更方法に変更する以前の時期になされたものであり,その時点では未だ原告製剤の販売は開始されていなかったものの,原告フジモトDが原告製剤を製造するとすれば原告当初方法以外に採り得る確認試験方法がなかったのであるから,上記各行為のうち,原告らが被告方法特許権を侵害するとの点については虚偽の事実とはいえない。しかし,原告製剤の製造販売が被告方法特許権を侵害するとの点については,前記のとおり虚偽の事実であるといえる。 また,先に上記アで認定した本件告知・流布行為のうち,別表1の1-1ないし1-3欄以外のものについては,それら各行為がなされた時点では,前記のとおり被告方法特許権も被告物質特許権も侵害しておらず,また被告が有する他の特許権を侵害しているということもなかったと認められる(弁論の全趣旨)から,それらの行為は虚偽の事実を告知・流布するものであったといえる。 ウ以上によれば,本件告知・流布行為は,いずれも原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものであり,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為を構成するものというべきである。 (3)争点(2)(故意・過失の有無)についてア前記のとおり,先に上記(2)アで認定した本件告知・流布行為はいずれも,原告らが,被告の有する特許権のいずれかを侵害しており,原告製剤の製造販売は被告の特許権のいずれかを侵害するという趣旨を告知するものであると考えられる。したがって,被告がそれら告知・流布行為を行うに当たり,いずれかの特許権の侵害の関係で,原告らがその特許権を侵害しており,原告製剤の製造販売がその特許権を侵害すると判断したことについて過失が認められなければ,行為全体としても過失は認められないものというべきである。 そして,一般に特許権者が,競業者の製品について,その製造販売行為が自社の特許権を侵害する旨を競業者の取引先等に対して告知・流布し,その取扱いについて警告する行為は,特許権の行使としての性質を有するものではあるとはいえ,法的手続によらずに,もっぱら自己の認識判断に基づいて自力救済的に行われる権利行使であり,常にその認識判断が誤っている危険をはらむものである一方,一度そのような行為がなされた場合には,当該競業者の製品の取扱いが控えられるなど,競業者に重大な損害をもたらすおそれが高いものである。このことからすると,告知・流布した者の過失の有無については,後に述べる違法な仮処分の執行の場合のように過失が推定されるとまで解し得るか否かはともかく,少なくとも高度の注意義務が課せられるものと解するのが相当である。 イ被告方法特許権関係での故意・過失について(ア)本件告知・流布行為のうち,別表1の1-4ないし1-7,1-12,1-17,1-18,1-20,1-27,1-29ないし1-32,1-96,1-98,1-109及び1-110欄の行為についてaこれらの行為は,いずれも平成5年12月から平成7年9月の間になされたものであり,被告方法特許権の侵害との関係では,第1次訴訟(平成4年8月20日提訴)の第1審係属中の時期に当たる。そして被告は,原告フジモトDが実施している確認試験方法を現認しておらず,また侵害の有無が訴訟上争われ,裁判所による公権的判断が未だ出されていないにもかかわらず,原告らが被告方法特許権を侵害することを内容とする告知・流布を行ったものではある。これらの点からすると,被告にはこの点において少なくとも過失があったといってよいようにも思われる。 bしかし,これについては,次の諸点を指摘することができる。 (a)被告は,原告フジモトDが実施している確認試験方法を現認していないとはいえ,原告製剤は被告製剤の後発医薬品であり,その製造承認における確認試験方法は被告製剤におけるそれと同等以上の精度が要求されるものであり,また製薬事業者は,原則として製造承認書記載の確認試験方法を実施するものであることは,当時から明らかなことであった。 (b)原告製剤の製造承認の審査が行われていた時期は,前提事実記載のとおり,被告が,被告製剤の確認試験中に被告発明方法によるカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験を追加する旨の製造承認事項一部変更申請を行い,その審査が行われていた時期と重複していたものであるが,被告の従業員であるF作成の平成4年8月28日付け報告書(乙9)によれば,原告製剤の製造承認審査の過程では,厚生省の担当官は,上記Fに対し,①昭和63年10月及び同年12月ころに,原告製剤の審査においても,被告製剤の製造承認事項一部変更承認申請の審査結果を考慮する必要があるので,その審査状況についても逐次知らせてほしいと依頼したこと,②平成3年11月26日には,被告製剤の製造承認事項一部変更承認申請については実質審査が終了しており,後発医薬品の審査にもその点を含めて検討していると述べたこと,③平成4年2月21日には,承認審査に当たっては最新の科学レベルのものを要求する,被告製剤の一部変更承認申請の規格・試験法は一応の評価を終えており,これらの内容で承認されることは容易に想定できる,後発医薬品の承, , 認時点では 先発医薬品の評価済みの規格及び試験方法と比較すると述べたこと,④同年3月12日には,上記Fが 「後発医薬品の,規格・試験法にKPI(カリクレイン様物質産生阻害活性)の確認試験が入っているか 」と尋ねたのに対し,先発医薬品の評価済み 。 のものを参考にしている,KPIの試験方法の内容までは覚えていないが,公表論文(被告発明方法が記載されたGほか「血漿カリク」『』 レイン様物質産生阻害能を評価するin vitro測定法基礎と臨床第20巻第17号所収)に基づいた方法であったと思う,と述べたことが認められる。これによれば,被告は,当時から,原告製剤の製造承認審査においても,被告製剤の製造承認事項一部変更申請に係るカリクレイン様物質産生阻害活性確認試験に基づいた方法が設定されたことを,厚生省担当官の発言によって認識していたということができる。 (c)第1次訴訟における原告フジモトDの訴訟態度は,自らが実施している方法として原告変更方法の主張をするものの,製造承認書に記載された確認試験方法がどのようなものであるかは明らかにしないというものであり,また,当時既に行っていた一変申請の事実や原告変更方法の開発経過についても積極的に明らかにすることがなかった。 (d)当時,被告発明方法以外に,被検物質のカリクレイン様物質産生阻害活性を測定する方法として公知のものがなかったことは,第1次訴訟の控訴審判決で認定されており,この認定を左右するに足りる証拠はない。 (e)原告変更方法が被告確認試験方法と同等以上であるか否かについては,原告変更方法は,カリクレイン様物質産生阻害活性の定量性において被告確認試験方法よりも劣ることは第2次訴訟の判断によっても認められており,このような定量性も加味して考えれば,原告変更方法は被告確認試験方法と同等以上とはいえない性質のものである。 (f)侵害性に関する被告の主張は,第1次訴訟の控訴審判決で容れられ,結局,第1次訴訟における最終的な認定判断として確定するに至った。この認定判断は,第2次訴訟において覆されたが,第2次訴訟においては,第1次訴訟と異なり,原告フジモトDの原承認に係る製造承認書の記載と一変申請の事実が明らかにされ,さらにその一変承認もされており,かつ原告変更方法の開発経過を示す種々の証拠も提出されたことを踏まえて判断されたものである。 c以上の諸点からすると,第1次訴訟の時点において,被告が,原告フジモトDの訴訟態度も踏まえた上で,原告製剤の原承認に係る製造承認書における確認試験方法の記載がどのようになっているかが侵害性の有無を決するポイントであると判断したことは合理的な根拠があったといえる。そして,被告は,厚生省の担当官から,原告製剤の確認試験方法も被告の確認試験方法に基づいたものであると説明されていたのであるから,被検物質のカリクレイン様物質産生阻害活性を測定する方法として当時は他に知られたものがなく,また原告フジモトDが主張する原告変更方法は定量性において被告の確認試験方法に劣るものであることを考え併せると,被告が,原告製剤の原承認に係る製造承認書の確認試験方法として被告発明方法が記載されていると判断したことも無理からぬものといえ,そうである以上,原告フジモトDはその方法を実施して被告方法特許権を侵害していると判断したことも合理的な理由に基づくものであったというべきであり,このことは,同旨の判断が結局第1次訴訟の確定判断となったことからも裏付けられるといえる。もっとも,この判断は第2次訴訟において覆るに至り,また客観的には誤った判断であったと認められることも前記のとおりであるが,それは上記のような事情の相違によるものであり,これによって当時の被告の判断が無理からぬものであったとの認定が左右されるものではない。 したがって,被告が,前記各行為の時点において,原告らが被告の特許権を侵害していると判断したことには,被告方法特許権の関係では,高度の合理的根拠があったというべきであるから,結果的にその, 。 判断は誤っていたとはいえ 被告に故意・過失があったとはいえないdもっとも,被告方法特許権の関係で,被告が,原告製剤の製造販売が被告の特許権を侵害すると判断したことついては,故意・過失の有無を別途検討する必要がある。 前記のとおり,被告方法発明は単純方法の発明であるから,被告方法発明の測定法を使用して原告製剤の確認試験を行う場合であっても,原告製剤の製造販売行為は被告方法特許権を侵害する行為とはいえない。これは,第1次訴訟上告審判決の判示するところである。 他方,原告フジモトDが被告発明方法を使用して原告製剤を製造しているとする場合には,原告製剤の確認試験の実施は,原告製剤の製造工程に必然的に組み込まれていることから,これを物を生産する方法の発明と同視できると解して,原告製剤の製造販売も被告方法特許, , 権の侵害となると解するのが 第1次訴訟における被告の主張であり第1次訴訟控訴審判決の判示するところである。 これらの見解の当否については,第1次訴訟上告審判決によって前者の見解が正当なものと確定したわけであるが,後者の見解も一つの見解であり,少なくとも第1次訴訟控訴審判決の採用するところとな, 。 ったのであるから 全く不合理なものであったということはできないしかしながら,前者の見解は,特許法を最も素直に適用した場合の帰結であるということができる上,この論点については従前は特に定説と見られるものもなかったことからすると,少なくとも裁判所による公権的な判断が示される前の時点では,前者の見解を採用せず,後者の見解を採用するだけの合理的な根拠はなかったというべきである。 したがって,原告製剤の製造販売が被告の特許権を侵害するとの内容を告知・流布した点については,被告方法特許権との関係では,被告に少なくとも過失があったというべきである。 (イ)別表1の1-111欄の行為についてこの行為は,第1次訴訟の第1審判決後・控訴審判決前にされたものであるが,上記(ア)で述べたことからすると,第1審判決で被告の請求を棄却する判決がされていることを考慮しても,被告が,原告らが被告方法特許権を侵害していると判断したことには過失があるとはいえない。しかし,被告が,原告製剤の製造販売が被告方法特許権を侵害すると判断したことには,上記(ア)dと同様に少なくとも過失があるというべきである。 (ウ)別表1の1-1ないし1-3欄の行為について前記のとおりこれらの行為は,被告方法特許権の関係で,原告らが被告の特許権を侵害する旨を告知・流布する点では虚偽でないが,原告製剤の製造販売が被告の特許権を侵害する旨を告知・流布する点では虚偽であるというものである。そうすると,先に上記(ア)dで述べたことからして,被告には少なくとも過失があったものというべきである。 (エ)別表1の1-112欄の行為についてこの行為は,第1次訴訟の控訴審判決後・上告審判決前にされたものであり,判決の確定前とはいえ,控訴審裁判所による公権的判断が示された後のことであるから,その判断を信頼して,その判断内容に沿った内容を告知・流布することに故意・過失があるとはいえない。 したがってこれらの行為については,被告物質特許権関係での故意・過失を判断するまでもなく,不正競争防止法4条の故意・過失は認められない。 ウ被告物質特許権関係での故意・過失について(別表1の1-1ないし1-7,1-12,1-17,1-18,1-20,1-27,1-29ないし1-32,1-96,1-98,1-109ないし1-111欄の行為について)(ア)前記のとおり,被告物質特許は,A文献とB論文(及び4206号公報)を基本的な公知文献として,無効とされたものである。 (イ)ところで,被告の本件告知・流布行為がされたのは,平成4年7月から平成9年5月の間であって,この時点では,原告フジモトDによる無効審判請求はされていなかったし,弁論の全趣旨によれば,A文献及びB論文に基づく無効理由の主張がされたこともなかったと認められる(原告らは,被告が昭和薬品に対して申し立てた仮処分事件において,事実上昭和薬品に代わって手続を追行する過程で,平成6年8月16日付けの主張書面において,被告物質特許には無効理由があると主張したが,これはA文献及びB論文に基づく進歩性欠如の主張ではなく,またその主張は仮処分決定によっても受け入れられなかった[乙15,23。]。)また,弁論の全趣旨によれば,被告物質特許が特許査定されるについては,特許庁から公知文献を示して特許性の欠如が指摘されることもなかったと認められる。 このように被告は,上記行為の時点では,他者からA文献やB論文に基づく被告物質特許の無効の可能性を指摘されたことがない状況であったといえる。 (ウ)他方,被告がA文献及びB論文の存在及び内容を認識していたか否かについては,次のように考えられる。 aB論文(乙33)は,1952年に「Institute for Medical Research,Dainippon Zoki Kenkyusho Co.,Ltd」から発行されたものであるが,この「Dainippon Zoki Kenkyusho Co.,Ltd」は,4206号公報(乙34)の出願人欄に記載された「株式会社大日本臓器研究所」のことであり,弁論の全趣旨によれば,商号変更前の被告であることが認められる。 したがって,B論文は被告が自ら発行したものであり,その存在及び内容を熟知していたものと推認される。そしてそのことは,4206号公報についても同様である。 bA文献(乙26)は,社団法人日本薬学会発行の「薬学雑誌」96( ) , 巻第10号 昭和51年10月25日刊行 に掲載されたものであり「ワクシニアウイルスで感染した家兎皮膚組織中の生物活性物質の研究特に胃酸分泌抑制物質の分離とその性質」と題するものである。 A文献では,その末尾に「実験材料の一部を提供された日本臓器製薬株式会社に厚く感謝する」と記載されている。これからすると,被告は,実験自体にこそ関わっていないものの,実験材料の提供に関与していたことが認められる。 またA文献が掲載された「薬学雑誌」は,社団法人日本薬学会が発行するものであり,このように学会が自ら発行するほどの雑誌については,製薬企業の間で広く入手されていたものと推認される(ちなみに乙26の表紙には,原告藤本製薬が発行から8日後の昭和51年11月2日に図書として購入したことを示す押印がある。。)さらに被告は,ワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤の「創製者」であり,その「製造方法や医薬用途等に関して多数の特許権を有して」おり(甲1 ,同製剤を昭和25年以降,製造販売して )きている。 以上からすると,被告は,A文献が掲載された「薬学雑誌」を刊行当時に入手していたものと推認されるが,それにとどまらず,被告がワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤について研究開発を続けてきていたことやA教授らに実験材料を提供したことからすると 「ワクシニアウイルスで感染した家兎皮膚組織中の生物活性物質 ,の研究」という,自己が創製した特殊な製剤分野そのものを研究した論文については,その内容も十分に認識していたものと推認するのが相当である。 (エ)以上に基づき検討する。 まず,A文献では,B論文の方法に準じて抽出物Ⅱを得たと記載されているから,A文献を十分に認識していた被告としては,そうして得られた抽出物Ⅱが,B論文によって得られたB物質と同等の物質である可能性があることは容易に考えられるところであり,また両文献の製造方法を具体的に見ても,第2次審決取消訴訟判決が判示したように同等のものと認められるから,なおさらそのようにいえる(同判決の判示によれば,A文献とB論文の製造方法の間には,形式的には別表8のような相違点があるが,被告物質特許の出願当時の当業者の技術常識からすると,いずれも最終抽出物中の生理活性物質に実質的に相違をもたらすようなものとは認められないというのであるから,そのような製造方法の形式的な相違にかかわらず,被告は上記のような認識を有することができたと考えられる。そうすると,B論文を熟知していた被告が,A 。)文献に接し,その内容を検討したときには,A文献ではサブタイトルが「胃酸分泌抑制物質の分離とその性質」とされているものの,そこでの抽出物ⅡはB論文及び4206号公報のB物質と同等であり,したがってB物質の作用として従前から知られていた薬効を抽出物Ⅱも有する可能性があることについて想到することは,十分可能であったというべきである。 そして,A文献の抽出物Ⅱの製造方法と被告物質発明の生理活性物質, , の製造方法とは 抽出時間やグリセリン添加の有無の点に相違はあるが第1次審決取消訴訟判決が判示したようにいずれも抽出物の成分の相違に影響するものではないことからすると,両者が同一の物である可能性があることについても,想到することは十分可能であったというべきである。 これらのことからすると,前記告知・流布行為の時点では,A文献及びB論文を理由とする無効理由の主張に被告が未だ接していなかったとしても,ワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤の当業者である被告としては,他者からの無効理由の指摘がなくとも,被告物質特許の有効性について疑問を抱いてしかるべき事情があったというべきであって,この点について過失があるというべきである。 もっとも,A文献・B論文・被告物質発明における各製造方法が前記のとおり同等のものであったとしても,第1次及び第2次審決取消訴訟判決が認定するとおり,そのような製造方法によって抽出された抽出物の物理化学的性質は,それぞれ異なる点があるとの各文献の記載や後の実験報告がある。しかし,いずれにおける抽出物も,同じ材料から同等と考えられる製造方法で抽出したものであるから,抽出された物の性質は同じになるはずのものであり,そうである以上,各文献の記載の理解や実験報告の信頼性について疑問を抱いてしかるべきである。したがって,上記事実によっては,前記認定判断は左右されない。 また被告は,被告がA文献の抽出物Ⅱと被告物質発明の生理活性物質とが異なる物であると判断したことについては,特許庁の第1次審決もそのような判断をしたほどなのであるから,合理的な根拠に基づくもの。,,, であったと主張する しかし 特許庁の第1次審決は A文献における抽出物Ⅱに関する「オルシノール反応陰性」との記載について,抽出物Ⅱの分画の一部についての結果が示されているだけであるのに,抽出物Ⅱの全分画についての結果であるかのような認定をしており,明らかに不合理な判断を含むものであったといえるから,第1次審決の存在をもって被告に過失があるとの上記認定判断を覆すほどの合理的な根拠があったとはいえない。 以上よりすれば,被告は,被告物質特許に無効理由がないと判断したことについて,少なくとも過失があったものというべきである。 エ故意・過失のまとめ以上によれば,別表1の1-112欄の行為を除き,本件告知・流布行為を行うについて,被告には,被告方法特許権関係でも被告物質特許権関係でも過失があったといえるから,行為全体としても過失があったというべきである。 (4)争点(3)(違法性の欠如)についてア先に述べたとおり,特許権者が,競業者の製品について,その製造販売行為が自社の特許権を侵害する旨を競業者の取引先等に対して告知・流布し,その取扱いについて警告する行為は,特許権の行使としての性質を有するものではあるとはいえ,法的手続によらずに,もっぱら自己の認識判断に基づいて自力救済的に行われる権利行使であり,常にその認識判断が誤っている危険をはらむものである一方,一度そのような行為がなされた場合には,競業者の製品の取扱いが控えられるなど,競業者に重大な損害をもたらすおそれが高いものである。このことからすると,その告知・流布内容が虚偽である場合には,特許権者の主観的な意図,目的にかかわら, , ず 当該告知・流布行為は一般に違法性を有すると解するのが相当でありそれが特許権の行使であることの一事をもって違法性を欠く正当な行為とされるべきものではない。このことは,特許権者が,差止仮処分を得てこれを執行したが,後に本案訴訟等においてその被保全権利が存しないことが確定したことにより仮処分決定が当初から不当なものであったことが確定した場合に,その執行に出た行為が,法的手続に則った特許権の行使であるにもかかわらず,一般に違法な行為と評価すべきこととの均衡からしても裏付けられるところである。 もっとも,特許権者が,競業者の取引先を相手方として,その取引先が競業者の製品を販売する行為が自社の特許権を侵害するものであるとして,仮処分を申し立てたり,特許権侵害訴訟を提起したりすることは,たとえそれによって取引先に競業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知することになり,またその認識判断に過失が認められるとしても,裁判を受ける権利を保障する観点からして,特許権者が,事実的・法律的根拠,,,, を欠くことを知りながら 又は 特許権者として 特許権侵害訴訟の提起あるいは,仮処分の申立てをするために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば,事実的・法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて訴訟等を提起し,あるいは,仮処分を申し立てた場合に限って違法になると解するべきである(最高裁判所昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照 。そして,特許権者が競業 )者の取引先に対して訴訟を提起することを考える場合であっても,いたずらに訴訟を提起するのではなく,これに先立って,当該取引先に対し特許権を侵害しているとの警告等を行い,事前の話合いによる解決の道を探求することは,訴訟手続に要する当事者及び国家の負担を回避する見地からむしろ奨励されるべき行為である。そうすると,そのような警告等が,当該警告等に至る経緯,当該警告等の態様(内容,文面,規模,状況等 ,)当該警告後の経緯等に照らして,当該取引先に対する訴訟提起の前提としての事前の真摯な紛争解決探求行為と認められるものである場合には,訴訟提起に準じるものとして,同様に違法性を有しないと解するのが相当である。 イこれを別表1の1-112欄以外の本件告知・流布行為について見ると,まず,謹告文等の業界紙への掲載(別表1の1-1及び1-2,1-109ないし1-111欄)は,医薬品関係者に対して,その者の原告製剤の取扱いの有無にかかわらず,網羅的に特許権侵害の事実を告知するものであり,訴訟提起の前提としての事前の真摯な紛争解決探求行為とは到底認めることができない。 次に医薬品卸売業者に対する文書の送付行為(別表1の1-3ないし1-7,1-12,1-96欄)についても,医薬品関係者に対して,その者の原告製剤の取扱いの有無にかかわらず,網羅的に特許権侵害の事実を告知したものであり,上記と同様,訴訟提起の前提としての事前の真摯な紛争解決探求行為と認めることはできない。 さらに,被告の従業員による口頭での告知行為(別表1-17,1-1,,,,, ) 8 1-20 1-27 1-29 1-30 1-31及び1-98欄についても,同欄に記載された告知状況及び告知内容からして,訴訟提起の前提としての事前の真摯な紛争解決探求行為と認めることはできない。 ウ以上によれば,被告の本件告知・流布行為(別表1の1-112欄を除く)は,いずれも違法性を欠くということはできない。 (5)争点(5)(不正競争行為に基づく損害額)についてア逸失利益について(ア)原告らは,被告による営業誹謗行為に基づく損害額を証するものとして,○○大学大学院経済研究科教授のC作成の「ワクシニアウィルス接種家兎炎症皮膚抽出液製剤マーケットにおけるローズモルゲンとノイロトロピンの競合分析及び逸失利益の算出について と題する見解書 C」(見解書)を提出している(甲133 。)このC見解書では,原告製剤と被告製剤の販売額についてIMSのデータ(甲139)を基礎として,概ね,次のように述べている。 a被告製剤と原告製剤の間には,強い競合関係があり,極めて強いシェアの奪い合いが存在していた。 b自由競争市場において市場に導入された商品は,一般に導入期,成長期,成熟期,衰退期というプロセスから成るライフサイクルをたど,,, , り 医薬品の場合には 導入期が1年程度 成長期が3~10年程度成熟期が7年以上,その後衰退期という流れをとるところ,被告製剤ではこのような医薬品の一般的なライフサイクルをたどっているが,原告製剤では,別表10のような販売額の推移からすると,平成6年の導入期を経て,平成7年度から販売量・販売額が急増していくはずだが,平成8年度の売上げをピークに減少傾向にあり,成長期も成熟期も経ておらず,本来ならば成長期を迎えるべき段階で,不健全な競合状況があったといわざるを得ない。 c医薬品の場合には,本来の競合関係における両製品のシェアの奪い合いは,ある一定の値に漸減的に収束していくものであり,原告製剤と被告製剤の2製品においても,別表11のとおり,平成7年10月までは漸減的にシェアの変動がみられるが,同年11月から平成8年2月までの急速な落ち込みやそれ以降のシェアの大きな変動は,健全な競争状態では考えられない動きであり,何らかの不健全な競争があった可能性が高い。 dもし自由競争の下で健全な競合状況が存在していたならば,原告製剤は平成7年度から平成14年度までの8年間にわたって成長期を維持したと推定され,その最大シェアは最低35%,最大45%と推定される。そして,平成7年10月までを健全な競合状況と見て,この時期までの原告製剤のシェア増加率からその成長速度を推計し,上記期間中の逸失売上額を算定すると,最大シェアを35%とした場合での売上損失額(薬価の85%とする実勢価格ベース)は62億円余となり,粗利率を50%とすると逸失利益額は31億円余となる。 (イ)また原告らは,原告らが当時作成した原告製剤の販売計画と実績との相違をもって,被告による営業誹謗行為に基づく販売減少を示すものと主張している。 (ウ)以上について検討するに,別表1及び9によれば,まず本件告知・, , 流布行為が行われた時期は そのほとんどが平成6年中に集中しており平成7年のものも多くは同年3月ころまでのものにとどまっている。また,本件告知・流布行為ではないが,原告らが本件で被告による営業誹謗行為であると主張する行為の全体を見ても,同様の時期的な傾向を見て取ることができる。 このような行為時期からすると,上記C見解書によれば,平成7年10月ころまでは健全な競合状況であったと考えられるとされているけれども,被告の行為の影響はより早期に現れてしかるべきである(なお,C意見書では,平成7年11月の名古屋地裁仮処分決定の執行の影響に触れているが,それは後記の同仮処分の執行に基づく損害賠償の問題であって,ここでの問題とは異なる。。)また,原告らグループの常務執行役員であるHの陳述書(甲144)によれば,別表12のとおり,原告らが原告製剤について立てた販売計画は,平成7年度まではほぼ達成されているが,平成8年度からは実績が計画を大きく下回っていることが認められる。しかし,上記のような被告の行為の時期からすると,その影響が生じたのであれば,既に平成7年度中に実績が計画を大きく下回ってしかるべきである。 さらに,そもそもC見解書が前提とする医薬品のライフサイクルが,原告製剤にも妥当するものであるかどうかは不明であり,I「図解自分のポジショニングの見つけ方 (乙42の1。著者は,株式会社リク 」ルートリサーチにて種々の分野の調査の営業,企画,実査,分析に携わった経験を有する )では 「商品の寿命の考え方としては 『プロダク 。, ,トライフサイクル(PLC 』があるが,商品の寿命は可変的であるた )め,現実には適用しにくく,理論的な理解にとどまっている場合が多い 」とされ,また同人のホームページ(乙42の2)では 「市場に 。 ,投入される数多くの製品の中で,この図のようにライフサイクルを描くものは,実際にはほとんどなく,成長期にすら至らず,導入期の段階で販売中止となってしまうものが大半である 」とされている。。 さらに,本件で損害賠償の対象となる被告の行為は,原告らが主張する営業誹謗行為のうちの一部にすぎない上,当時被告は原告らに対して特許権侵害訴訟を提起して争っており,この事実自体が広く知られていたのであるから,これにより相当の売上減少が生じたものと推認されるのであり,本件で損害賠償の対象となる本件告知・流布行為自体によって,更なる売上げの減少が生じたのかについては,疑問なしとしない。 また,前記のとおり,本件告知・流布行為のうち,原告フジモトDが実施していた確認試験方法が被告方法特許権を侵害しているとの点については,その内容を告知・流布したことについて被告に過失があったとは認められないから,この事実の告知・流布によって損害が発生したとしても,それについては被告に責めを負わせることはできない。 なお,本件告知・流布行為の中には,平成9年の時期のものも存する, , が それらは主として第1次訴訟の控訴審判決の後にされたものであり被告らの告知・流布行為ではなく,むしろ同判決が被告の請求を認容したこと自体が原告製剤の売上減少に圧倒的な影響を及ぼしたものと考えられる。 以上の点からすると,本件告知・流布行為によって原告らに売上減少による逸失利益が発生した可能性も否定し得ないものの,なおそれが発生したこと及びその額については,これを認めるに足りないといわざるを得ない。 イ無形損害についてHの陳述書(甲144)によれば,原告らでは,被告による種々の告知行為の対策として,MRを動員して,すべての納入先医療機関及び卸売業者に対して事情説明を行ったこと,その他,通常の営業努力を上回る営業努力が必要となったことが認められる。 この中には,本件告知・流布行為によって必要となったものでないものが相当程度含まれていることは容易に推認することができるけれども,本件告知・流布行為がこれらの行為の必要性と全く関係がないということもできない。 そうすると,本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すれば,本件告知・流布行為による無形損害としては,原告らにつきそれぞれ200万円と認めるのが相当である。 (6)不正競争防止法に基づく損害賠償請求についてのまとめ以上によれば,本件での不正競争防止法に基づく損害賠償請求は,①被告方法特許権の侵害のみに関するもの及び品質に関するものに基づく損害賠償請求権は時効により消滅しているから理由がなく,②被告方法特許権と被告物質特許権の双方の侵害に関するものは,原告らがそれぞれ200万円の賠償と遅延損害金を請求する限度で理由があり,③訴訟手続や仮処分手続内での主張立証行為に基づくものは違法性が認められないから理由がない。 2不法行為に基づく損害賠償請求について(1)まず原告らは,被告の前記営業誹謗行為及び訴訟提起・仮処分申立て等が一連の不法行為を構成すると主張する(争点(6) 。)しかし,被告の行為を一連のものと把握することが相当でないことは,前記1(1)イで述べたとおりである。そこで以下,被告の個々の行為についての不法行為の成否を検討する。 (2)不法行為に基づく損害賠償請求のうち,不正競争防止法に基づく損害賠償請求と同一の被告の行為に基づくものは,先に述べたところと同様に,前記1(6)の限度で損害賠償請求が認められるにとどまる。 (3)侵害訴訟の提起・追行及び仮処分の申立て・追行について(争点(6))原告らは,被告が原告ら及び昭和薬品等の卸売業者に対して多数の特許権侵害訴訟や仮処分を申し立てて,係争状態を作出・維持した行為が不法行為を構成すると主張する。 アしかしまず,侵害訴訟の提起・追行については,法的紛争の当事者の裁判を受ける権利は最大限尊重されなければならないことにかんがみると,民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において,その訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴, , 者の主張した権利又は法律関係が事実的 法律的根拠を欠くものである上提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(前記最高裁判所昭和63年1月26日第三小法廷判決 。)そして,この趣旨は特許権侵害訴訟の場合にも等しく妥当するものであり,たとえ特許権者が特許権侵害訴訟を提起・追行し,そのことが知れ渡ることによって,被告とされた者の製造販売する製品が顧客らに買い控えられる事態が生じ,それによって被告とされた者に売上減少等に伴う損害が発生するとしても,そのことは,裁判を受ける権利を保障することに伴い,被告とされた者に反射的に生ずる不利益として想定された範囲内のものにすぎないというべきである。 この点について原告らは,市場における優位性を維持するという営業目的のために訴訟を利用して係争状態を作出・維持することは違法性を有すると主張するが,そもそも特許権は,産業上利用することができる発明を独占的に実施することができる権利であり,その権利行使としての特許権侵害訴訟は当然ながら市場における自己の優位性を維持するという営業目, , 的のためになされるものであって そのような目的を有するからといって訴えの提起・追行が違法とされる理由はないというべきである。 しかるところ,別表3記載の被告により提起・追行された訴え(上訴を含む )には,被告方法特許権の侵害を理由とする侵害訴訟と被告物質特 。 許権の侵害を理由とする侵害訴訟があるところ,前者についてはこれまで述べてきた第1次訴訟及び第2次訴訟の判断内容,後者についてはこれまで述べてきた無効審判事件に係る審決及び審決取消訴訟判決の内容に照らし,上記各訴えの提起・追行が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる事情は存しない。 したがって,上記各侵害訴訟の提起・追行は不法行為を構成しない。 イまた仮処分の申立て・追行についても,それが昭和薬品等の原告ら以外の第三者に対するものである場合であっても,同様の観点からすると,仮処分の申立てが仮処分制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる事情が存するときに限り違法性を有すると解するべきであるが,別表3記載の被告による仮処分の申立て・追行においてはそのような事情は認められない。 したがって,仮処分の申立て・追行は不法行為を構成しない。 (4)刑事告訴について(争点(6))弁論の全趣旨によれば,原告フジモトDは,平成9年11月18日の第1次訴訟控訴審判決及び同日の大阪高裁仮処分決定により原告製剤の製造販売の差止命令を受けたにもかかわらず,その後も原告製剤の製造販売を継続していたことから,別表3の3-7欄記載のとおり,平成10年4月24日に被告が原告フジモトD及び同代表取締役を特許侵害罪で刑事告訴したことが認められる。したがって,この刑事告訴は,被告が第1次訴訟控訴審判決の判断を信頼して行ったと推認されるものであり,告訴制度の趣旨を逸脱又は濫用した違法なものとはいえず,不法行為を構成しない。 (5)仮処分決定の執行について(争点(6)(7))ア名古屋地裁仮処分決定の執行について(ア)仮処分決定が,被保全権利が存在しないために当初から不当であったことが本案訴訟等において確定した場合,その決定を得てこれを執行した仮処分債権者に故意又は過失があったときは,仮処分債権者は,仮処分債務者の権利利益を違法に侵害したものとして,民法709条により仮処分債務者がその執行によって受けた損害を賠償すべき義務があるというべきであるが,その場合には,特段の事情のない限り,債権者には過失があったものと推定するのが相当である(最高裁判所昭和43年12月24日第三小法廷判決・民集22巻13号3428頁参照 。本)件における被告の昭和薬品に対する名古屋地裁仮処分決定は,平成7年10月31日の発令後,平成9年2月14日に被告物質特許権の存続期間満了により取り下げられ,その後に同特許を無効とする審決が確定したというものであるが,この場合も,仮処分決定が,被保全権利が存在しないために当初から不当であったことが後に確定したことに変わりはないから,同様の趣旨が妥当するものと解するのが相当である。 この点について被告は,仮処分決定が仮処分債務者側に十分な主張立証の機会を与えた上で発令された場合には上記のように過失を推定する趣旨は妥当しないと主張する。しかし,本来執行力は,権利関係が本案判決によって確定されて初めて付与されるというのが法の建前であり,仮処分決定は,仮執行宣言と同じく,例外的に本案判決の確定前に,権利関係が未確定なままで執行力を付与するものであるから,権利が存在しないことが後に確定したときは,本案判決確定前の執行によって打撃を受ける仮処分債務者と仮処分債権者との衡平の観点に加え,民事訴訟法260条2項が仮執行宣言が後に取り消された場合に関する仮執行をした原告の無過失責任を定めていることとの均衡からも,たとえ仮処分決定が仮処分債務者側に十分な主張立証の機会を与えた上で発令された, 。 場合であっても 過失を推定する趣旨は妥当するものというべきである, , (イ)ところで 被告物質特許権の侵害に基づく名古屋地裁仮処分決定は被告が,原告らではなく,第三者である昭和薬品に対して申し立て,その執行も昭和薬品に対して行われたものであり,原告らは同仮処分決定における債務者ではない。そうすると,このような原告らが,昭和薬品に対する被告の仮処分の執行が違法であることを理由に,その損害の賠償を請求し得るかが問題となる。 確かに,被告の違法な仮処分の執行による直接的な権利侵害行為は,昭和薬品に対して行われており,原告らはいわば間接被害を受けたという関係にある。しかし,このような間接被害に係る原告らの損害であっても,昭和薬品に対する違法な仮処分の執行が,昭和薬品の権利利益を侵害することに故意又は過失があることに基づいて不法行為を構成する場合において,上記権利侵害行為と相当因果関係を有する損害であるときには,その損害は不法行為に基づいてなお賠償すべき対象となるべきものと解される。 他方,原告らが主張する損害が前記のような相当因果関係を有する損害でない場合には,そのような損害は,被告による違法な仮処分の執行が,昭和薬品ではなく,原告ら自身の権利利益を直接に侵害する不法行為を構成すると評価し得る場合でなければ,賠償の対象とならないものというべきである。 (ウ)以上に基づいて検討するに,前記のとおり名古屋地裁仮処分決定の執行については,前記1(3)ウで述べたことからして,被告に過失があったとの推定を覆滅するに足りる事情は認められず,被告には過失があったといえるから,昭和薬品に対する直接的な権利侵害行為として,不法行為を構成するといえる。そこで次に,本来は争点(8)(不法行為に基づく損害額)に関する事項ではあるが,原告らが主張する損害が,昭和薬品に対する仮処分の執行に係る不法行為と相当因果関係を有するといえるか否かを検討する。 a直接損害について原告らが直接損害として主張するものは,昭和薬品が執行官保管の, , 仮処分の執行を受けた原告製剤について 原告藤本製薬が返品を受け廃棄処分したことによる損害である(なお,弁論の全趣旨によれば,昭和薬品に原告製剤を販売し,返品を受けたのは,原告ら内部で販売を担当する原告藤本製薬であると認められ,原告フジモトDが同損害を受けたとは認められない。この損害は,原告藤本製薬の立場か 。)ら見ると,昭和薬品に対する売上高相当額を得る機会を失った損害ということになるが,その実質は,上記仮処分の執行によって,昭和薬品が原告製剤を転売することができなくなったことにより受けた転売売上高相当額の損害のうち,原告藤本製薬からの仕入値相当額を,返品という形で原告藤本製薬が填補(ないし肩代わり)したものという, 。 ことができ したがって昭和薬品自身の損害と同視すべきものであるそうすると,このような損害については,前記相当因果関係を有するものというべきである。 b昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害について前記仮処分の執行によって,昭和薬品は,原告製剤を販売することを強制力をもって中止させられるに至ったところ,そのような場合,必然的に原告藤本製薬からの原告製剤の仕入れ(更には原告藤本製薬)。, の原告フジモトDからの仕入れ も中止することとなる このように卸売業者に対する販売差止めの仮処分を執行した場合には,必然的・定型的に当該製品の製造販売業者の当該卸売業者に対する販売ができなくなる結果が招来されるのであるから,そのような事態も卸売業者に対する仮処分の執行によって強制的に実現されたものということができる。 そうすると,このような損害については,前記相当因果関係を有するものというべきである。 c他社との取引への影響により受けた損害(a)昭和薬品に対して仮処分の執行がされたという事実が広く認識された場合,他の業者も原告製剤の取扱いを控えるようになる事態が生じることは容易に理解することができる。しかし,ここで問題, () となるのは 昭和薬品に対する権利侵害行為 すなわち販売差止めとの相当因果関係の有無であるところ,この場合の他の業者による原告製剤の販売は,昭和薬品による原告製剤の販売が仮処分の執行によって中止させられた後も,何ら封止されているわけではなく,これら業者に対する原告製剤の販売量の減少も,昭和薬品による原告製剤の販売が仮処分の執行によって強制的に中止させられたことによって実現されたものではない。 そうすると,この原告らの損害は,昭和薬品に対する権利侵害行為との間に相当因果関係を有するものとはいえない。 (b)そこで次に,この仮処分の執行が原告ら自身に対する直接的な権利侵害行為として不法行為を構成するかを検討する。 仮処分の執行は法に則った権利行使手続であるが,それにもかかわらず仮処分が当初から不当であった場合に違法とされるのは,本案判決の確定によって権利関係が確定される前であるにもかかわらず,その強制力によって仮処分債務者の権利利益を直接に侵害することになるという点にある。このことからすると,仮処分の執行の強制力の対象でない原告らに対する関係では,仮処分が当初から不当なものであったというだけでその執行が違法性を有するということはできない。そして,この場合に原告らの受ける損害が反射的なものにすぎないことを考えると,被告によるこの仮処分の執行が原告らに対する関係でも違法と評価し得るためには,それが,昭和薬品への権利行使に名を籍りて,もっぱら原告らの権利利益を侵害する目的で,その違法性を知りながら行ったものであるという事情が認められることを要すると解するのが相当である。 そうすると,本件ではそのような事情は認められないから,他社との取引への影響により受けた損害については,賠償の対象とすることはできない。 d無形損害について昭和薬品に対して仮処分の執行がされたという事実が広く認識された場合に,その製造販売業者である原告らの信用が損なわれることは容易に理解することができる。したがって,昭和薬品との関係においては,原告らに信用毀損による無形損害が生じたものといえる。しか, , し 昭和薬品以外の業者との関係で原告らの信用が損なわれたことは昭和薬品による原告製剤の販売を仮処分の執行によって強制的に中止させたことによって実現されたものではないから,前記相当因果関係を有するものとはいえず,また原告らに対する直接的な権利侵害として不法行為を構成するともいえない。 e以上より,前記直接損害,昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害及び昭和薬品との関係で発生した無形損害については,被告は,不法行為に基づく損害賠償義務を負う。 (エ)なお,以上によって認められる原告らの不法行為に基づく損害賠償請求権については,上記仮処分の執行が違法であることが確定したのが被告物質特許を無効とする審決が確定した平成17年1月ころであり,その時点が消滅時効の起算点となるから,本件では未だ消滅時効は完成していないというべきである。 イ大阪高裁仮処分決定の執行について前提事実記載のとおり,第1次訴訟の大阪高裁仮処分決定は,被告方法特許権の侵害を認めて,原告フジモトDに対し,被告発明方法を用いて原告製剤を製造販売すること等の差止め,原告製剤等の執行官保管及び原告製剤についての薬価基準収載申請取下げを命じた。そして被告は,原告フジモトDの彦根工場及び羽曳野研究所において,執行官保管の仮処分を執行したが,同仮処分は,平成11年7月16日の本案訴訟の上告審判決において,被保全権利が存在しないことを理由に被告敗訴の判決が確定したことにより失効した。 そうすると,この仮処分の執行が違法であることは,上記上告審判決において確定し,原告フジモトDはその送達によって直ちにその違法を認識したものである。したがって,仮に上記仮処分の執行が不法行為を構成するとしても,それに基づく損害賠償請求権は,上告審判決の送達の時から消滅時効の進行を開始することになるから,それから3年が経過した平成14年7月ないし8月ころに消滅時効が完成したものといえる。そして,被告は本件でその時効を援用したから,上記損害賠償請求権は時効により消滅したものというべきである。 したがって,上記仮処分の執行を不法行為とする損害賠償請求は,その余について判断するまでもなく理由がない。 (6)昭和薬品に対する名古屋地裁仮処分決定の執行に基づいて原告らが受けた直接損害,昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害及び昭和薬品との関係で発生した無形損害の額について(争点(8))ア直接損害について(ア)後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 a被告は,昭和薬品に対する名古屋地裁仮処分決定に基づき,平成7年11月10日,昭和薬品の小牧配送センターにおいて,原告製剤の執行官保管の仮処分の執行を行い,原告製剤1箱50アンプル入り・23箱,1箱200アンプル入り・116箱を執行官保管とした(甲124 。)b被告は,同仮処分決定に基づき,同月13日,昭和薬品の名古屋北支店において,同様の仮処分の執行を行い,原告製剤1箱200アンプル入り・合計3箱を執行官保管とした(甲125の各号 。)(, , 。) 以上 執行官保管とされた原告製剤は 合計2万4950本であるc上記仮処分申立ては,平成9年2月14日に被告物質特許権の権利期間満了を見越して取り下げられたが,昭和薬品は,その後の同年3月31日,上記執行官保管に係る原告製剤のほか,昭和薬品が原告藤本製薬から仕入れて保管していたものの,仮処分の執行の対象とならないまま保管し続けていた原告製剤を原告藤本製薬に返品した。その本数及び返品売上高は次のとおりであった(甲142 。)返品数1箱10アンプル入りを1箱1箱50アンプル入りを33箱1箱200アンプル入りを158箱合計3万3260本返品額返品売上高合計622万4750円消費税18万6743円d原告らは,返品を受けた原告製剤を廃棄した。 (イ)原告らが主張する直接損害は,上記執行官保管とされた合計2万4950本に係る損害であるが,これによって原告らが受けた損害は,原告藤本製薬が得られたはずの昭和薬品に対する原告製剤の売上相当額である(なお先に述べたとおり,原告フジモトDに直接損害は生じていないと認められる。。)そして,原告藤本製薬の昭和薬品に対する原告製剤の得べかりし売上額は 前記認定の返品数と返品売上高から1本当たり187 15円 6, , .(224,750÷33,260。小数点第3位以下切り捨て)であるから,合計46(。)。 6万9392円 187.15×24,950 小数点以下切り捨て と認められるイ昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害について(1)(ア)証拠(甲160,161)によれば,昭和薬品に対する原告製剤の月別売上数量の推移は別表13のとおりであると認められ,前記仮処分が執行されてから,同仮処分申立てが取り下げられるまでの間,昭和薬品は原告製剤の販売を中止したことが認められる。 (イ)ところで,被告は,原告らはこの間,従前昭和薬品が原告製剤を販売していた取引先に対して,原告らの関連会社である藤本医薬販売を通じて,原告製剤を直販していたと主張する。 そこで,藤本医薬販売による直販の月別売上数量の推移を見ると,証拠(甲160)によれば,別表13のとおりであると認められ,昭和薬品への月別売上数量の推移と並べてグラフ化すると,同別表添付グラフのとおりとなる(なお同証拠によって認められる原告製剤の総販売数量も記載した。これによれば,仮処分の執行期間中の直販数量は,そ 。)の前後の時期と比べて顕著に増加していることが認められる。 これに加え,平成7年11月20日付けの被告の営業本部RM対策委員会( RM」とは原告製剤のこと)作成の「RM対策」と題する社内 「文書(乙52)では 「昭和薬品㈱の動き」として 「RM納入先に対 , ,し 『都合により販売できなくなった』との案内中「代案として, , 。」,直販で購入するよう,F社のTEL,Fax記入の用紙を渡し,注文後1~2日で宅配で届ける旨案内している 」と記載されていること,原 。 (), 告らグループの常務執行役員であるHの陳述書 甲144 においても「平成7年11月の昭和薬品における差押執行により,昭和薬品を経由することが出来なくなり,直販で販売せざるを得なくなったという事情がありました 」と記載されていることを考え併せると,被告が主張す 。 るとおり,原告らは,仮処分の執行期間中,従前の昭和薬品の販売先に対して,藤本医薬販売を通じた直販を行うことで,昭和薬品の販売中止による売上減少を食い止めようと努力したものと認められる。 (ウ)そこで,昭和薬品が原告製剤の販売を中止したことによって原告らが仮処分の執行期間中に受けた損害額(逸失利益の額)は,①同期間中も昭和薬品が原告製剤の販売を継続していれば同期間中に原告らが昭和薬品に販売できたであろう売上数量から,②同期間中に従前の昭和薬品の販売先に対して藤本医薬販売を通じた直販によって販売した売上数量を控除した売上数量に,③原告製剤1本当たりの利益額(1本当たりの販売価格に利益率を乗じて得られる )を乗じることによって求めるこ 。 。, 。 とができると考えられる 以下 上記①ないし③について順次検討する(エ)仮処分の執行期間中も昭和薬品が原告製剤の販売を継続していれば原告らが同期間中に昭和薬品に販売できたであろう売上数量についてa○○大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻数理科学領域教授(。「」。) のJほかの作成に係る意見書乙48以下Jら意見書というでは,この数量を算定するに当たり,甲第160号証(JD-NET等のデータ の数字を基に ①原告らによる原告製剤の総販売数量 別 ), (表14のE欄)から藤本医薬販売による直販分(同D欄)を除いた販売数量(同B欄。これは代理店・卸売業者を通じた売上数量ということになる )について,仮処分の執行期間中(平成7年11月から平 。 ) (), 成9年2月 の各月の販売数量の対前年同月比率を算定し 同C欄②仮処分の執行期間中の各月の昭和薬品の推定販売数量を,昭和薬品の前年同月の販売数量(同F欄)に①で算定した各月の対前年同月比率を乗じることによって算定することで,従前の経緯から見た販売数量を推定し(同G欄 ,③他方,②と同様に,仮処分の執行期間中の )各月の昭和薬品の推定販売数量を 昭和薬品の次年同月の販売数量 同 , (F欄)を①で算定した各月の対前年同月比率で割り戻すことによって算定することで,事後の経緯から見た販売数量を推定し(同H欄 ,)④これら2つの推定販売数量の平均値をもって推定販売数量の結論とし(同J欄 ,⑤これらのうち特に平成7年11月と平成9年2月に )は仮処分の執行期間以外の期間が含まれていることから,④で得られた仮処分の執行期間中の推定販売数量から,同期間中の昭和薬品の実際販売数量を控除したものを,同期間中に昭和薬品が販売することのできた数量としている(同K欄 。)bこの推計方法は,昭和薬品の推計販売数量を,卸販売全体の販売動向を基礎にして,事前の経緯からの推計と事後の経緯からの推計を複合的に利用して行う点で基本的に合理的なものであるといえる。 ,, 。, しかしながら 上記推計には 次のような問題点もある すなわち上記推計の①及び③では 「原告製剤の総販売数量から藤本医薬販売 ,による直販分を除いた販売数量」についての,対前年同月増減率を算定し,それを推計の基礎としている。しかし,このような直販分を控除しただけの販売数量では,その中に昭和薬品の販売数量も含まれており,昭和薬品を含めた卸販売全体の販売動向を基礎にすることになる。ところが,仮処分の執行期間中は,昭和薬品の販売数量は仮処分の執行の影響を受けてゼロになっているのであるから,仮処分の執行がなかった場合の昭和薬品の対前年同月増減率・対次年同月増減率を卸販売全体の動向から算定するためには,仮処分の執行の影響を排除した,昭和薬品以外の卸販売動向を基礎とすべきである。 cそこでこの観点から,Jら意見書に係る推計を修正すると,別表1。,「」(), 5のとおりとなるすなわち同別表のその他卸販売D欄は甲第160号証によって認められる原告製剤全体の販売数量(E欄)から,昭和薬品の販売数量(B欄)及び藤本医薬販売の直販数量(C欄)を控除したものであり,この増減動向によって対前年同月増減率(F欄)を算定し,Jら意見書による推計と同様の方法で,昭和薬品の推定販売数量について,対前年補正(G欄 ,対次年補正(H欄 , ))その平均(I欄)を求めて,販売減少分(J欄)を推計したものであり,それによれば,仮処分の執行がなければ,その執行期間中に昭和薬品が販売することのできた数量は,198万9618本と推計される。 (オ)仮処分の執行期間中に従前の昭和薬品の販売先に対して藤本医薬販売を通じた直販によって販売した販売数量についてaこの点について,Jら意見書では,①甲第160号証(JD-NET等のデータで,卸販売と直販の双方のデータが記載されている。別表14のE欄 )と甲第164号証(IMS売上データ。卸販売のみ 。 のデータが記載されている。同L欄 )の各総販売数量の差を「直販 。 数量」とした上で(同M欄 ,②この「直販数量」の,甲第160号 )証における総販売数量(同E欄)に対する割合を「直販率」として求め(同N欄 ,③仮処分の執行がなかった場合の推定直販率を,仮処 )分の執行期間の開始前2か月間(平成7年9月及び10月)と終了後1年間(平成9年3月から平成10年2月まで)の直販率の平均値から,8.2%とし,④仮処分の執行がなかったならば,推定総販売数量(IMSデータによる実際の卸販売数量+推定直販数量)に対する推定直販数量の割合が推定直販率である上記8.2%になったはずであるということから,{8.2/(100-8.2)×L}の算定式で推定直販数量を算出し同P欄⑤実際の直販数量同M欄と推定直販数量同 (),()(P欄)の差(同Q欄)をもって,従前の昭和薬品の販売先に対して藤本医薬販売を通じた直販によって販売した数量として推計している。 bこの推計方法は,原告製剤全体の売上げに対する直販率を基礎として,仮処分の執行がなかった場合の仮処分の執行期間中の直販数量を推計するものであり,基本的に合理的なものといえる。 しかし,次のような問題点も指摘できる。 すなわち 上記推計では ①において JD-NET等のデータ 甲 ,,, (160 とIMSデータ 甲164 の各総販売数量の差を実際の 直 )() 「販数量」としている。しかし,実際の直販数量は,甲第160号証において,藤本医薬販売の売上数量として直接明らかになっている上,Jら意見書の記載においても,甲第160号証と甲第164号証の各総販売数量の差の中には,直販数量と小規模卸売業者の販売数量の双方が含まれているとされているのであるから,卸販売量全体の販売数量を把握するには,甲第160号証の藤本医薬販売の販売数量(別表14のD欄)を基礎とするほうが正確である。 次に,上記推計の②では,直販率を算定する分母として,原告製剤全体の販売数量を用いている。しかし,この中には,昭和薬品の販売数量も含まれているから,この推計では,昭和薬品を含めた原告製剤全体の売上げに対する直販数量の比率をもって直販率とすることになる。ところが,仮処分の執行期間中は,昭和薬品の販売数量は仮処分の執行の影響を受けてゼロになっているのであるから,原告製剤全体の販売動向に対する直販率の動向から,仮処分の執行がなかった場合の直販率を算定するためには,仮処分の執行の影響を排除した,昭和薬品以外の原告製剤全体に対する直販数量の比率を基礎とすべきである。 また,上記推計では,④において,直販率を算出する際に,実際の卸販売数量としてIMSデータ(甲164)の数値を採用している。 しかし,実際の卸販売数量を示す証拠としては,それ以外に,甲第160号証のうち,藤本医薬販売の販売分を除いたJD-NET等のデータによるものも存する。そして,甲第146号証及び弁論の全趣旨によれば,JD-NETデータとは,製薬企業と医薬品卸売業者との間の商取引データを電子的に取引するデータシステムによるデータであって,卸売業者から原告らに対して直接に日々送信されるものであるのに対し,IMSデータとは,アイ・エム・エス・ジャパン株式会社が,同社と契約している全国の卸売業者から得たデータを集計したものであり,医家向け医薬品市場の98%以上をカバーするものであると認められ,両者の間では,①卸売業者から卸売業者に二重に卸販, , 売がされた場合には その数はJD-NETデータには反映されない②アイ・エム・エス・ジャパン株式会社と契約していない卸売業者(例えば,甲第160号証の「101協栄薬品株式会社「80」,2西南薬品株式会社」等がそれに当たる )の販売数量はIMSデ 。 ータには反映されない,といった相違のあることが認められる。これらの点からすると,ここでは原告らが販売することのできた数量が問題になっているのであるから,卸売業者から卸売業者に二重に卸販売がされた場合の販売数量を二重に計上するのは適切でないし,また計上する卸売業者の数は漏れが少ないほうが正確であるから,JD-NETデータを用いるほうがより正確な推計となるといえる。そして,先に②について述べたのと同じく,推定直販率から推定直販数量を算定する際には,昭和薬品を含めた卸販売数量全体ではなく,昭和薬品を除いた卸販売数量を用いるべきである。 cそこでこの観点から,Jら意見書に係る推計を修正すると,別表15のとおりとなる。すなわち,直販率(K欄)は,原告製剤全体の販売数量(E欄)から昭和薬品の販売数量(B欄)を控除したものに対する藤本医薬販売の直販数量(C欄)の割合を算出したものである。 そして,こうして得た直販率について,Jら意見書と同一の期間を基に推計直販率を算定すると,5.21%となる。そこで,この推定直販率と,昭和薬品を除く卸販売数量(D欄)を用いて,Jら意見書と同旨の計算式(すなわち {5.21/(100-5.21)×D )により,仮処 , }分の執行がなければ販売されたであろう直販数量を推計した上で(L欄 ,これと実際の直販数量(C欄)との差をとったものが,従前の )昭和薬品の販売先に対して藤本医薬販売を通じた直販によって販売した売上数量と考えられ,その数は163万9871本となる。 (カ)以上より,上記仮処分の執行によって原告らが昭和薬品に販売できなくなり,直販によっても償えなかった仮処分の執行期間中の販売数量は,(エ)と(オ)の差である合計34万9747本と推計される。 (キ)原告製剤1本当たりの販売価格について前記のとおり,前記仮処分の執行の対象となった原告製剤の昭和薬品に対する1本当たりの販売価格は,187.15円である。 しかし,この仮処分の執行は平成7年11月に行われているところ,原告製剤の薬価は,平成7年は253円であったものが,平成8年には227円(前年の89.7%)に低下している(甲140。薬価変更時点は4月1日である。したがって,仮処分の執行期間中に原告らが 。)昭和薬品に原告製剤を販売し続けることができていたとしても,この薬価下落の影響は当然受けたはずであり,販売価格は下落したはずであると考えられる。 そうすると,仮処分の執行期間中の各時点での昭和薬品に対する販売価格は,平成7年の前記販売価格から,前記薬価の下落幅に対応する割(, 合だけ平成8年において下落したものと推定するのが相当である なお上記の下落割合は,被告が原告製剤の一般的卸売価格(仕切価)の推移として算定した金額(乙54)の下落割合ともほぼ一致するものである。。)したがって,原告製剤1本当たりの販売価格は,①平成7年11月から平成8年3月までの5か月間は187.15円,②平成8年4月から平成9年2月までの11か月間は167.87円(187.15×0.897)となるから,これらを加重平均した173.895円( 187.15×5+167.[87×11]÷16)をもって販売価格とするのが相当である。 (ク)原告製剤の利益率についてa原告らは,その訴状における主張の段階から,被告製剤1本当たりの被告の利益の額は56.84円である(甲127)から,それが原告らの原告製剤1本当たりの利益の額と同額と推定されると主張している。そしてこれによれば,平成7年の前記昭和薬品に対する原告製(.),. 剤1本当たりの販売額 173 895円 に対する利益率は 327%となる。 確かに,被告製剤と原告製剤とは,先発医薬品と後発医薬品という関係にあり,また平成7年までは薬価は同額であった(甲140 。)しかし,企業によって利益率が大きく異なる場合があることは決して希なことではない。また,当時,被告は,従来から同一材料の「ノイロトロピン特号」を販売してきており,被告製剤の製造販売も昭和51年に開始しており(甲140 ,しかも昭和63年からは「ノイロ )トロピン錠」の製造販売も行っていて,ワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物製剤についてはその製造販売業務が確立していたと考えられ,また被告製剤のみをとってみても,その販売量は原告製剤と(,),, 比較して圧倒的に多かった 甲139 乙41 のに対し 原告らは原告製剤の販売を大阪府下で平成4年10月から開始したものの,当初は直販のみであったためその販売量はわずかなものであり,平成6年4月ころからようやく卸売業者を通した全国規模での販売を開始したというものである(甲144 。このような原告らと被告の製造販 )売状況の差からしても,原告製剤の利益率が被告製剤のそれと比べて低い可能性は十分にあるというべきであり,原告製剤の利益率が被告製剤のそれと同額であると推定し得る根拠はない。 bまた原告らは,日本製薬工業協会の決算状況をとりまとめた「JPMANews Letter」を提出する(甲141の各号 。しかし,同協会 )は,原告藤本製薬のほか75社の製薬企業のうちの33社の決算状況が総合して記載されているのみであり,これによって原告製剤の利益率は何ら明らかになるものではない。 cこのような原告らの主張立証状況にかんがみ,当裁判所は,平成1,, 8年7月14日の第10回弁論準備手続期日において 原告らに対し書面をもって次の点についての釈明を求めた。 「 ,(), 原告製剤1本当たりの原価 諸経費 変動経費 及び卸値とこれに基づく利益額の主張立証。なお,薬価の変動による利益額の変動も明らかにされたい 」。 これに対して原告らは,原告らグループの常務執行役員であるHの陳述書(甲147)を提出した。そこでは,原告製剤に要する原材料費,人件費,光熱費,試験費用,輸送費等の経費として,平成6年は合計69.26円,平成8年は合計59.98円(平均すると64.62円)であるとされている。そしてこれによれば,昭和薬品に対する原告製剤1本当たりの販売額(173.895円)に対する経費率は37%,利益率は63%となる。しかし,その裏付けとなる資料が何ら提出されていないから,このような陳述書の記載のみで,その記載額を採用することは到底できない。 dこれに対し被告は,原告らの決算状況を,東京商工リサーチ企業情報と帝国データバンク企業情報によって調査した結果を提出している(乙56 。そのうち前者では売上高と税引前利益の額が,後者では )売上高と税引後利益の額がそれぞれ示されているが,これによれば,原告藤本製薬の売上高税引前利益率は,平成7年度が3.3%,平成8年度が1.9%,平成9年度が1.2%であり,原告フジモトDのそれは,平成7年度が1.5%,平成8年度が0.7%であることが認められる。 e以上が本件における原告製剤の利益率に関する当事者の主張立証の状況であるが,この点の立証責任は原告らにあり,かつ原告らがその立証を十分になし得るだけの客観的証拠(決算書や帳票類)を保有していることは明らかであるから,そのような証拠を一切提出しない原告らの立証状況は,甚だ不十分なものといわざるを得ず,それによる不利益は,基本的に原告らが甘受すべきものである。 しかし他方,本件で原告らが請求し得る逸失利益は,原告らが原告製剤を製造し,昭和薬品以外の取引先には販売している状況下で,さらに前記の数量の原告製剤を追加的に製造販売した場合に得られる利益(いわゆる限界利益)であるところ,仮処分の執行期間中に原告らが実際に販売していた数量は,合計1963万7320本である(別表13)のに対し,原告らが昭和薬品に更に販売し得た数量は前記のとおり34万9747本であり,わずか1.78%の数量を追加的に販売するにすぎないから,その追加的販売に要する販管費は,変動費的な性質を有する一部のものにすぎないと考えられ,損害額算定の基礎にすべき利益率は,粗利益率にある程度近いものとなると考えられる。そして,一般に我が国の企業においては,売上高に対する販管費の割合が数十%に及ぶことが多く,そのために粗利益率が数十%となっていても,営業利益率が数%にまで低下することが多いのは公知の事実であり,甲第141号証の各号によれば,製薬企業においても同様の傾向が見られる。 このように考えると,いくら企業によって利益率に大きな差がある場合が希ではないとはいえ,原告製剤において,粗利益率にある程度近い限界利益率が,被告が主張するような税引前利益率程度にすぎないとは到底考えられないところであり,被告の調査結果に係る数値を原告製剤の利益率としてそのまま採用することも相当でないといわざるを得ない。 以上の諸点を総合考慮すると,本件における原告製剤の利益率は,売上高に対して10%を超えないものと認めるのが相当である。 (ケ)以上認定した追加販売数量,1本当たりの販売価格及び利益率からすると,原告らが昭和薬品による原告製剤の取引中止により,仮処分の,( 。 執行期間中に受けた損害の額は 608万円 173.895×349,747×0.1万円未満切り捨て)となる。そして,この損害額は,原告らが被った損, , 害額の合計であるといえるが 原告各自の損害内訳は明らかでないからそれぞれ均等に304万円ずつ損害を受けたものと推認するのが相当である。 ウ昭和薬品による原告製剤の取引中止により受けた損害について(2)(ア)前記のとおり,名古屋地裁仮処分決定の執行によって原告らが昭和薬品に販売できなくなり,直販によっても償えなかった仮処分の執行期間中の販売数量は相当数に上る。そして,別表13によれば,仮処分の執行期間経過後には,その直後から昭和薬品の販売数量が回復し,入れ替わりに直販数量が減少しているから,昭和薬品は直販分振替分についてはその販売数量を取り戻したといえるが,上記のとおり,仮処分の執行期間中に直販では償えなかった販売数量が相当程度存する以上,仮処分の執行期間経過後も同様の影響が少なくとも一定期間は存続するものと考えられる。 , 。 そこで 仮処分の執行期間経過後の逸失利益の有無及び額を検討する(イ)仮処分の執行期間経過後の昭和薬品の推定追加販売数量については,先に述べた仮処分の執行期間中におけるのと同様の方法によって推定することが合理的である。それによって推定したのが別表16(これは別表15に,仮処分の執行期間経過後の推計を加えたものである )。 であるが,このうち対次年補正に係る販売数量(H欄)については,昭和薬品が株式会社アズウェルとなったことにより,その販売数量が平成10年9月までしか存しないことから,対次年補正に係る販売数量もその1年前の平成9年9月分までしか算定することができない。そこで,それ以後の時期については,平成7年11月から平成9年9月までの,平均(I欄)の対前年補正に係る販売量(G欄)に対する割合(J欄)の平均値(0.780)を算出し,それを対前年補正に係る販売量(G欄)に乗じる形で平均(I欄)を算出し,先と同様にそれと昭和薬品の実際の販売数量(B欄)の差をとって減少分(K欄)を推計した。 そして,別表16によれば,減少分(K欄)は,仮処分の執行期間経過後,全般的に減少していく傾向が見られることから,それがマイナスとなる前月の平成10年6月までの1年3か月間,仮処分の執行の影響が存したと認めるのが合理的であり,その本数は合計67万6230本となる。 ,, (ウ)この期間中の原告製剤1本当たりの販売額は 先に述べたのと同様薬価の変遷を考慮する必要がある。 原告製剤の薬価は,平成8年には227円だったものが,平成9年には201円(前年の88.5% ,平成10年には182円(前年の9 ).)(。 。)。 0 5% に低下している 甲140 薬価変更時点は4月1日であるしたがって,先に述べたのと同様に,前記期間中の原告製剤の昭和薬品に対する販売価格は,先に認定した平成8年の前記販売価格から,前記薬価の下落幅に対応する割合だけ平成9年及び平成10年において下落したものと推定するのが相当である。 したがって,原告製剤1本当たりの販売価格は,①平成9年3月の1か月間は前記認定のとおり167.87円,②平成9年4月から平成10年3月までの12か月間は148.56円(167.87×0.885 ,③平成)10年4月から同年6月までの3か月間は134.44円(148.56×0.905)となるから,これらを加重平均した147.11円( 167.87+14[]) 。 8.56×12+134.44×3 ÷16 をもって販売価格とするのが相当である(エ)また,原告製剤の利益率に対する考え方は基本的に先と同様であるが,この期間は販売価格が急速に下落していることにかんがみ,7%と認めるのが相当である。 (オ)以上認定した推定追加販売数量,1本当たりの販売価格及び利益率からすると,原告らが昭和薬品による原告製剤の取引中止により,仮処分の執行期間経過後に受けた損害の額は,696万円(147.11×676,230×0.07。万円未満切り捨て)となる。そして,この損害額は,原告らが被った損害額の合計であるといえるが,原告各自の損害内訳は明らかでないから,それぞれ均等に348万円ずつ損害を受けたものと推認するのが相当である。 エ昭和薬品との関係で発生した無形損害の額について弁論の全趣旨によれば,昭和薬品は原告らにとって重要な卸売先である,, , ことが認められるところ 原告らは 自己の製造販売に係る製品が原因でその昭和薬品に仮処分の執行を受けさせる事態となり,また顧客に対してそれまで販売していた製品の販売を中止させる事態となったのであるから,たとえ仮処分手続に要する弁護士費用を原告藤本製薬が負担したとしても,昭和薬品に対する原告らの信用が損なわれたことは優に推認することができる。 また,原告らグループの常務執行役員であるHの陳述書(甲144)によれば,原告らは,昭和薬品の販売中止による売上減少を食い止める直販のための営業活動に多大な労力を投入したことが窺われる。 これらの点からすると,前記仮処分の執行により,昭和薬品との関係で原告らに発生した無形損害の額としては,原告らそれぞれについて100万円ずつと認めるのが相当である。 オまとめ以上によれば,前記仮処分の執行によって原告らが被った損害の額は,①原告フジモトDが752万円(逸失利益652万円,無形損害100万円 ,②原告藤本製薬が合計1218万9392円(直接損害466万9 )392円,逸失利益652万円,無形損害100万円)となる。 3不当利得返還請求について原告らは,被告が,営業誹謗行為や不法行為により後発医薬品たる原告製剤の市場への進出を妨害して原告らに損失を与え,事実上先発医薬品である被告製剤の独占市場を形成して,原告ら主張の損害額相当の利得を得たから,これが不当利得を構成すると主張する。 確かに,被告製剤の販売が開始された当時は,ワクシニアウイルス接種家兎皮膚組織抽出物による注射剤としては,先発医薬品たる被告製剤と後発医薬品たる原告製剤のみが市場に存在していたから,その注射剤の需要に対する関係では,両者は相互補完的な競争関係にあったと見ることができる(甲133のC見解書の分析でも,原告製剤と被告製剤のシェアの関係について強い負の相関関係が認められている。このように原告らと相互補完的な競争関係にあ 。)る被告が,原告らに対する営業誹謗行為や不法行為を行った場合には,それによって原告製剤の販売量・販売利益が減少し,その反面として被告製剤の販売量・販売利益が増加することになるという原告らの主張も,それ自体としては理解できる面がある。 しかし,営業誹謗行為が不正競争行為とされるゆえんは,競争相手の信用を害する虚偽の事実を告知・流布することが,自由競争の範囲を逸脱した不公正な競争行為とされるからであり,また,上記営業誹謗行為を含めた本件で原告らが主張する行為が不法行為と評価されるのも,同様の趣旨からであると解されるところ,このような不公正な競争行為から守られるべき市場は,原告らと被告とが相互補完的な競争関係に立つとはいっても,原理的にはその他の競争者にも開かれたものであるから,公正な競争が行われた場合に原告製剤の販売量・販売利益が増加し得るとしても,原告らがこれを現実に確保し得ることが法律上保障されているものではないことが明らかである。すなわち,本件で原告らが主張する営業誹謗行為等が違法と評価されるものだとしても,それによって法が本来確保しようとするものは,原告らと被告とが市場において自由で公正な競争行為を展開することそれ自体なのであり,その上での双方の一定の市場利益の獲得という結果までをも,法が原告らや被告に確保し,保障しようとするものではないのである。そうすると,たとえ被告の行為によって原告製剤の販売量・販売利益が減少し,その反面として被告製剤の販売量・販売利益が増加することになったとしても,そのような販売利益の減少と増加は,本来原告らが獲得すべく法によって確保され,保障されていた利益を,被告が取得したものとはいえないから,被告による販売量・販売利益の増加が法律上の原因を欠く利得とはいえない。 したがって,原告らの不当利得返還請求は,その余について判断するまでもなく理由がない。 4まとめ以上によれば,本件請求は,不正競争防止法及び不法行為に基づく損害賠償として,原告フジモトDが被告に対して952万円及びこれに対する不法行為の後である平成17年3月24日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度,及び原告藤本製薬が被告に対して1418万9392円及びこれに対する不法行為の後である平成17年3月24日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 田中俊次 |
|---|---|
| 裁判官 | 高松宏之 |
| 裁判官 | 西森みゆき |